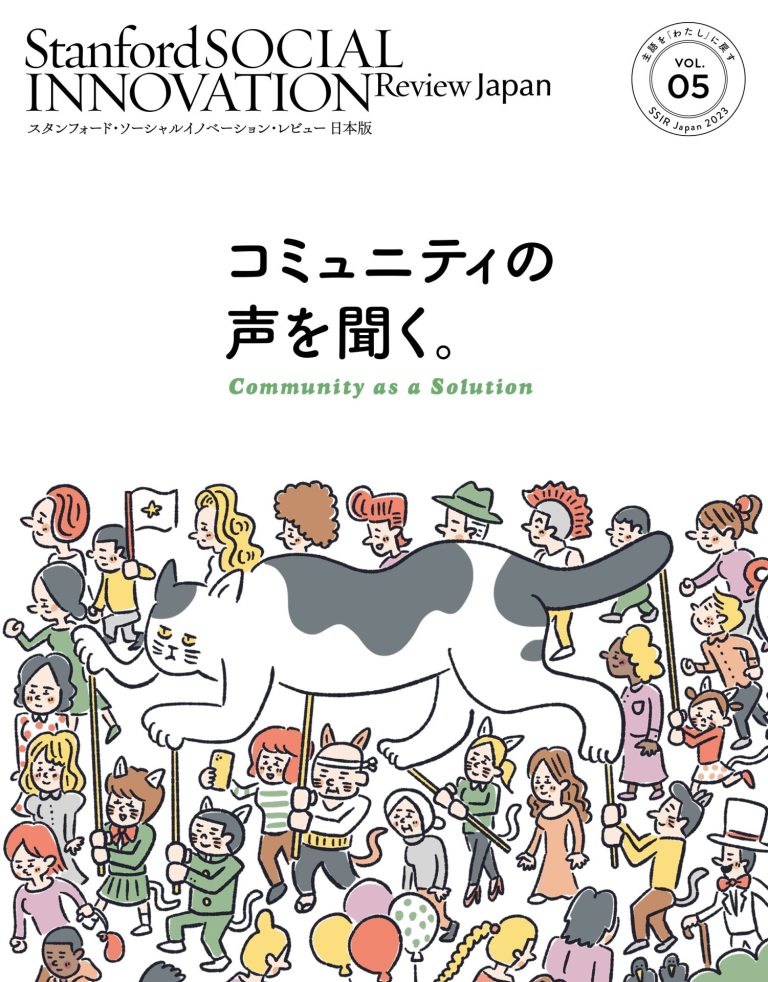市民のニーズと政策をつなぐ クラウドファンディング
チャンス・フォー・チルドレンは事業化の壁をどう乗り越えたか
社会課題の現場から政策提言を行う動きが広がり始めている。
クラウドファンディングを通じた政策の実証実験という取り組みもその1つだ。寄付行為を通じて、自分たちの身近な政策の形成過程に関与することは、草の根民主主義の1つの入り口にもなるだろう。
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 02 社会を元気にする循環』より転載したものです。
秋山訓子 Noriko Akiyama
NPO発の政策提言のうねり
貧困、介護、教育、災害援助……。いま目の前にある社会課題の解決に取り組む非営利団体(NPO)や社会的企業。その課題解決を自分の手の届く範囲だけでなく、制度化して広げようという戦略を明確に持ったリーダーたちが増えてきた。
たとえば、24時間365日のチャットによる相談を受け付けているNPO法人あなたのいばしょ。コロナ禍の2020年に活動を始め、歴史は浅いが、今や1日に寄せられる相談は1200件に達している。誰にも相談できずに苦しみ、聞いてもらいたいと願う人たちがそれだけいるというわけだ。創設者は若干23歳の大空幸星だが、「問題の源流を止めなければいけない」という意識を明確に持ち、寄せられた相談のデータをもとに、発足後1年もたたないうちに国に孤独対策の必要性を申し入れた。その結果、2021年、当時の菅義偉首相は孤独・孤立対策担当の大臣を内閣に置いた。首相が交代した後も続いている。
子どもの貧困対策に取り組むために2010年に事業を始めたNPO法人ラーニングフォーオール。東京や千葉、埼玉で学習支援拠点や子どもの居場所、子ども食堂を開設している。政策提言にも力を入れ、貧困問題の解決のために教育支援を行う60以上の団体と共に「全国子どもの貧困・教育支援団体協議会」を立ち上げた。
なぜこのように政策提言を行うリーダーたちが増えてきたのか。
一つには、NPOや社会的企業が日本にも定着し、目の前の課題解決に加えて、それを広げて自治体や国の制度を変えてシステムチェンジを図りたいと考える若いリーダーたちが登場してきたということがある。
彼らの多くが壁に突き当たってきた。それは、せっかく自分たちがソリューションを見いだし、実践しても、活動をスケールアップするには自分たちのリソースだけでは十分でないということだ。それを広げるために条例や法律をつくり、予算をつけて政策として展開していくことで活動を社会の隅々にまでいきわたらせる。そういう方法をとる動きが徐々に広がってきた。
政策のつくり手側の問題もある。世の中が多様化、複雑化して、これまで政策づくりを担ってきた官僚や政治家だけでは社会課題を網羅しきれないし、効果的な解決法も見いだせない。ようやく国や自治体のリーダーたちもそれを認識してきた。このNPO発(本稿では、NPOという言葉をNPO法人に限らず、社会課題に取り組んでいる民間の非営利団体全般を指す言葉として用いる)の政策形成に、クラウドファンディングを通じた資金調達によって一般市民が大きな役割を果たすことも可能になった。たとえば、スタディクーポンを利用した貧困世帯の教育支援に取り組む公益社団法人のチャンス・フォー・チルドレン(CFC)は、クラウドファンディングを使って集めた資金で政策の実証実験とモデル事業を行い、渋谷区での事業化につなげた。
市民が自分の気になる社会課題を「選んで」その解決のために出資する。そこには「税金を払わされる」のとは違う納得感があり、新しい草の根民主主義の可能性を感じる。ただ、開かれた資金調達による政策化は一筋縄ではいかない。本稿では、CFCの事例を取り上げ、NPOによる民間資金をもとにした政策形成における課題とその対応について述べる。
国の問題としての教育格差
CFCは、塾や音楽教室、サッカー教室などの習い事を含めた幅広い学校外教育で使える、年に15万~ 30 万円ほどの「スタディクーポン」を配布する事業に取り組んでいる。インターネットを通じて利用できる電子方式のクーポンを受け取った子どもたちには大学生のメンターがつき、自分の通いたい塾や習いごとを決め、学習や進路に関してあれこれと相談に乗る。 2011年の東日本大震災をきっかけに被災地の子どもたちを支援する取り組みから始まったが、子どもの貧困や教育格差は東北だけの問題ではない。
日本では現在、子どもの7人に1 人が貧困状態にあるといわれている。昼間は同じように学校に通っていても、放課後をどう過ごすかで学力や体力に差がつき、経済的に困難を抱える家庭の子どもはアートの楽しさも味わえないかもしれない。学校外での教育格差は将来の選択肢を狭めることにもつながる。
CFCの共同代表、今井悠介は「子どもの貧困は日本全国で共通の課題です。だったら、日本のど真ん中で事業をつくり、多くの人に知ってもらって、それから解決策を全国に広げていくかたちにしないとダメだと思いました」と語る。そのための政策化である。「1回クーポンを配ってそこで成果があったとしても、安定的に実施していくには政策として制度化しないと続かない。ですから、最初から政策化したいという考えはありました」。
最初のターゲットは東京都渋谷区に定めた。「渋谷区の長谷部健区長が、あるNPOが主催したイベントに登壇して、『NPOと連携したいから、どんどん政策を提案してほしい』とおっしゃっていたんですね。そういう区長がいるならできるかなと思って」。
長谷部区長は広告会社出身で、退社後に「ゴミを捨てない人を増やす活動」のためのNPOを立ち上げた経験もある。区長に就任した年に、渋谷区の全国に先駆けて開始した「渋谷区パートナーシップ証明」の発行を実現し、いわゆる「同性婚」が可能になった。渋谷区から東京へ、そこから全国へ、という目線で新しい課題にアプローチしているところに今井も注目していた。
区に要請するにあたり、今井は区の予算を使ってほしいとは言わなかった。
「自分たちにはそれまでスタディクーポンで積み重ねてきた知見がありました。それを生かしたかった。最初から区の予算でやってしまったら、区の政策になってしまって、自分たちは口出しができない。自分たちのお金で、まず事業をやって効果を実証して見せて、そこに後から予算がついてくるかたちにしたいと思いました。一緒に寄付を集めてください、それでうまくいったらその翌年から予算化をしてほしいとお願いしました」
現在、さまざまな自治体で、ふるさと納税の仕組みを使って寄付をしてもらい、それを財源に地域の課題解決をするという「ガバメントクラウドファンディング」の試みが行われている。今井も、そんなふうに渋谷区にふるさと納税を活用してもらいたいというアイデアもあったが、結局自前で財源を用意することにした。民間のクラウドファンディングを活用することにしたのだ。税金の代わりに寄付を利用するわけだ。自前のサイトではなく、民間のクラウドファンディングプラットフォーム、GoodMorningを選んだのは「団体の枠を超えた活動にしたい」と考えたからでもあったと今井は話す。「一団体ではなく、教育格差をなくしたいという思いを共にする団体が一緒にやっている新しいプロジェクトだというメッセージを出したかったんです。結果的に、これまでCFCを支援してくれていた人だけではなく、多くの人が賛同してくれました」。
CFCは若者の社会参加支援を行うNPOのキズキ、新公益連盟、ETIC.などの中間支援団体、渋谷区、およびサポーター企業とコンソーシアムを組んで「スタディクーポン・イニシアティブ」を結成。その第一弾プロジェクトとして、渋谷区内における貧困世帯の中学3 年生に「スタディクーポン」を提供するため、クラウドファンディングを実施した。その結果、目標金額の1000万円を大きく上回る、1400万円の寄付を集めた1。これを原資として54人にクーポンを支給。 1年間の試行実施を経て、2019年度からスタディクーポン事業は渋谷区の生活保護受給世帯の子どもを対象とした学習支援事業として採用された。初年度には300万円の予算がついた。その後、千葉県千葉市、佐賀県上峰町、沖縄県那覇市でも事業予算がつき、東京都は2020年からクーポンを配布する市区町村に補助金を出す制度を創設している。

スタディクーポンの仕組み
©Study Coupon Initiative

©Study Coupon Initiative
政策化のための2つの課題
●効果測定
今井はこのような政策の「実証実験」をするにあたり、事業評価を合わせて行うと自治体に事前に申し出た。CFCでは2011年から慶應義塾大学経済学部の赤林英夫教授やシンクタンクの三菱UFJリサーチ&コンサルティングに依頼して事業の評価もすでに行っており、スタディクーポンによって学力の向上という結果が出たことが実証されていた。渋谷区での実証実験の効果測定はプログラム評価の専門家である東洋大学社会学部の岩田千亜紀助教に依頼した。全3回のアンケート調査と1回のインタビュー調査を行い、「活動」「ニーズへの適切性」「アウトプット」「短期アウトカム」「中期アウトカム」「長期アウトカム」の6つの項目について評価した。その結果、対象となった世帯の子どもおよび保護者のニーズを的確にとらえている、子どもの学習習慣、学習意欲の向上などに対して一定の効果が示された、というデータが得られ、低所得世帯への子どもに対する学習支援として有効という評価がなされた2。

©Study Coupon Initiative

©Study Coupon Initiative
●議会対策
政策化を進めるなかで、思ってもみないところから出現した「壁」が「区議会」である。
地方議会というのは、私たちの身近な政治を扱う場でありながら、多くの人はその存在を4 年に1 度の選挙時にしか考えたことがないのではないだろうか。彼らは身の回りの政策を実現するための条例をつくり、予算を審議して成立させている。日本の地方政治の制度では、首長と議会がそれぞれ直接選挙で選ばれ、お互いに牽制しあって、公正な政治や行政を実施することになっている。しかし私たちは自分たちの住む自治体の首長ですら日常的に意識することはなく、ましてや議会はその存在を実感することがほとんどない。 1950年代には約8割だった市区町村選挙の投票率は低下の一途をたどり、最近では45%を切っている3。
CFCの今井も渋谷区で自らの事業を実施しようとしたときに念頭にあったのは区長だけで、区議会議員のことは念頭になかった。ところがクラウドファンディングを発表した記者会見後に区の担当者から呼び出された。「議員が、聞いていないといって怒っている」というのだ。確かに、区議会ではその頃スタディクーポンを含めた「目的を限定して支給する補助金」であるバウチャー制度がネガティブに取り上げられるようになっていた。反対の論点としては「区はどこまでかかわるのか」「区の責任はどこにあるのか」「利用者はどのように選定するのか。そのプライバシーは守られるのか」といったものがあった。話をこじらせないために、と区の職員から今井は議員に接触することを禁じられた。しかしこのままではせっかくクラウドファンディングもうまくいったのに、政策化することができなくなってしまうかもしれなかった。
今井はつてをたどって、この問題に関心があって推進したいと思っている議員を見つけたが、接触はできない。するとこの区議を紹介してくれた人が「今井さんから接触できないなら区議から接触してもらえばいい」と提案してくれた。区議からCFCの活動に視察に行ってもらえばCFC側から接触したことにはならない。区議は区役所に事前に話したうえで活動を視察し、議会でスタディクーポンをポジティブに取り上げた。そこから他の区議で味方になってくれる人も現れた。
今井は一連の経緯からの教訓を「まず、区議会が存在しているということをきちんと認識することが大事。議員たちに話を通さないで進めようとすると壁になってしまうことがある。きちんと話をすれば味方になって心強い応援団になってくれることもあるんです。なにより議会が壁になってしまうと、自治体の職員のモチベーションも下がってしまう。区と組んで何かしようとする場合、職員さんが前向きに仕事を進められるよう、環境整備をする必要があることを学びました」という。
以降、自治体に事業の話をしに行くときには、並行して議会で応援してくれる人を探し、同時にアプローチするようにしている。今井は成功した理由をこう語る。「まず事業として当事者のニーズがあったこと。それから、クラウドファンディングでこれだけの人たちがこの事業に期待していると見せられたこと。そして学力や学習意欲などへの効果も見せられて、政策メニューとして役立つことが実証できたこと。当初は区議会議員の反対などもあったものの、味方になってくれる人たちを得たこと。そして最後まで区長が応援してくれたことで乗り切れました」
東京都は2020年からクーポンを配布する市区町村に補助金を出す制度を創設し、2021年度は国立市が手を挙げた。東京都での展開の背景にも議員からの支援があった。
今井はもともとスタディクーポンを都に広げることまでは考えていた。「渋谷区の副区長から、こういうことは基礎自治体の財政力の差によらずできるように、都や国の予算をつけるべき。そこまでやってほしいと言われていて、『やります。だからまずは成果を見せないと。だから区でやらせてください』とお答えしたこともありました」。
元都議の奥澤高広は当時CFCを応援してくれた1人だ。超党派で応援してもらえるよう、いろいろな議員に話をするといいと今井にアドバイスをした。奥澤はその意味を「どこか1つを味方にすると、対立しているところが反対することもあるから」と話す。政争に巻き込まれず、政策化を推進するためには、まんべんなく味方になってもらうといいというわけだ。といっても、全員に味方になってもらう必要はない。それぞれの党派で1人応援してくれる人を見つけて、そこから党派内に浸透させていけばいいのだ。
そうやって1人ずつ味方を増やし、CFCは都議会での予算化へとこぎつけた。
草の根民主主義の入り口としての寄付行為
今井は、いまでは自治体との協働事業以外の案件でも当該地域の地方議員に相談するようにしている。「CFCの事業は地域と連携するものです。その地域との関係で、議員さんたちにクッションになってもらうようなイメージです。地域の代表ってまさにそういうことだと思うんです」。前出の奥澤も「地方議員の役割とは、身近な困りごとの解決にあたること。NPOと手を携えて政策を実現することで、身近な暮らしを良くすることができます」という。
日本の政治は長らく、票とカネを媒介に結びついた業界団体、政治家、官僚という「鉄の三角形」で政策がつくられてきた。しかし、CFCが実現してきたことはそれとはまったく別のモデルによる政策実現である。
クラウドファンディングでお金を集めて、その予算のもとに自分たちの解決モデルを政策をつくる人たちに見てもらう。実際に問題の解決に成果があったと納得させることができれば、政策化への突破口が開かれるかもしれない。クラウドファンディングで政策の実証実験を行い、モデル事業化するイメージだ。
クラウドファンディングでお金を集められるということ自体、多くの人の共感を得ていることを示す証しにもなる。
税金を「とられる」という言い方をよくする。本当は払いたくないが、義務なので嫌々払う。そこには「自分でお金の使い道を直接決められない」ことへの不満も入っているのではないだろうか。これに対してクラウドファンディングを通じて寄付をする場合、課題解決への取り組みに貢献したいという意思や思いがある。自らが共感した事業を「選んで」出資するので、そこには納得感があり、その事業の成果も気になるだろう。つまり寄付行為を通じて社会課題が「自分事」になるのだ。
日本では、認定NPO法人や、公益財団法人・社団法人に対する寄付は控除が受けられる。そういった法人への寄付は最大で寄付の半額近く控除が受けられる(申告すれば後で戻ってくる)。といっても認定のハードルは高く、NPO法人は5 万以上あるが、そのうち認定を受けたものは2022年1月末現在で1200あまりにすぎない4。ふるさと納税が2000円を超えた分が控除されるのと比べれば、控除額も見劣りがする。
もちろん、税金の使途をすべて個々の納税者が指定することは不可能だし、仮に実現したとしてもそれが社会にとって最適な税金の使い方になるとは限らない。けれども、自分たちの身近な政策については、その立案に関与し、成果をモニターするという意識が育つことが「鉄の三角形」に楔を打ち込むことにもなるのではないだろうか。
そのように考えるとクラウドファンディングを通じた政策の実証実験という取り組みは、草の根の民主主義の1つの入り口とも位置づけられるだろう。
CFCは共感で寄せられた寄付を用いて、閉じた業界利益ではなくて広い社会的ニーズのための政策を実現したのだ。今井はスタディクーポンの国での事業化も目指している。所得下位15%の層の家庭すべてにクーポンがいきわたる状況をつくりたいという。その壁となるのが自治体の財源格差であると主張し、国による補助の拡充を訴えている。実現すれば民間のクラウドファンディングによって生まれた政策の初の全国展開となるだろう。
最後に強調しておきたいのが、民間のクラウドファンディングを使って特定の政策を実現することは、政治を迂回するためではないということだ。むしろ実現のためには政治ファクターは無視できない。今井と奥澤のコメントに見られるように、政治とNPOが最終的に目指すところは同じなのである。社会の歪みを正し、新しい価値をつくりだすことをどちらも目指している。そのための方法論が違うだけで、いわば同じ山を違う登山口から登っているようなものだ。目指すところが同じとわかれば協力し合って登ることもできるのだ。
(文中敬称略)
【写真】Pawel Czerwinski on Unsplash
秋山訓子
東京大学文学部卒業後、朝日新聞社入社。横浜支局、政治部、アエラ編集部などを経て、政治担当の編集委員。政治部では首相官邸、自民党、民主党、外務省などを担当。著書に『ゆっくりやさしく社会を変える NPOで輝く女たち』『女は政治にむかないの?』(講談社)、『不思議の国会・政界用語ノート』(さくら舎)、『コーヒーを味わうように民主主義をつくりこむ』『クラウドファンディングで社会をつくる』(現代書館)など。ロンドン政治経済学院(LSE)修士。
- https://cfc.or.jp/archives/news/2017/12/01/20230/
- https://eduwell.jp/article/cfc-shibuya-study-coupon-solve-educational-inequity-part1/
- https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/turnout/kuhead-turnout/
- https://www.npo-homepage.go.jp/about/toukei-info/ninshou-seni