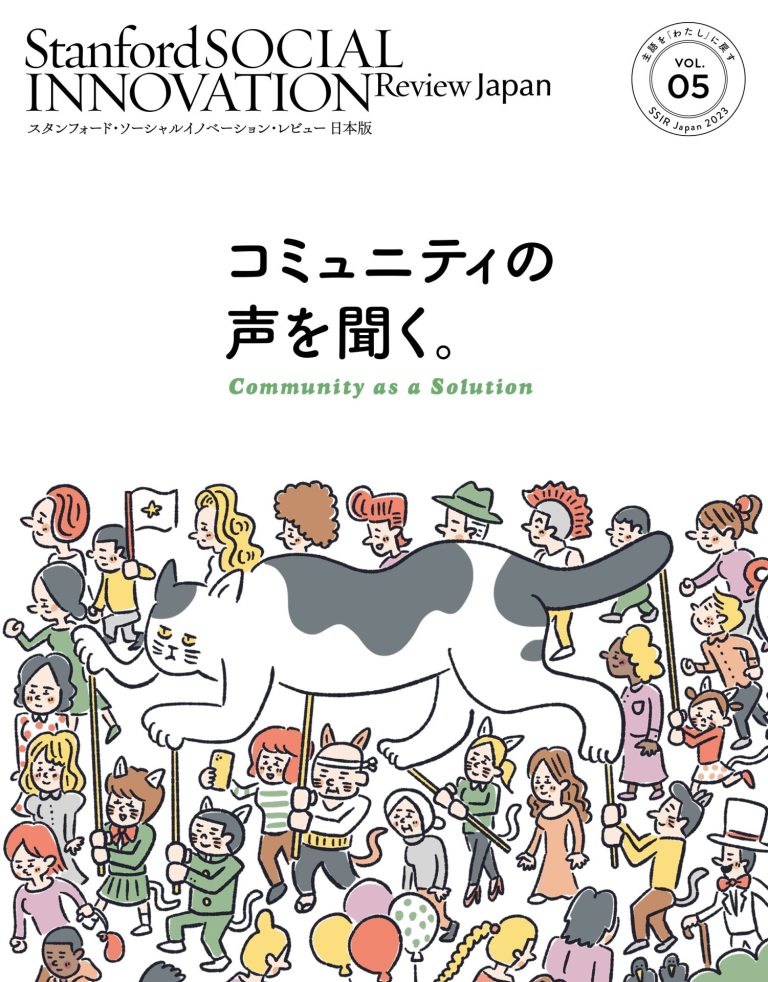途上国での「実証実験」をシステムチェンジの突破口に
アメリカ、インドネシア、日本に拠点を置き、グローバルに活動している国際NGOコペルニクは、国連ですら手が届かない“ラストマイル”と呼ばれる村々へ、ソーラーライトや簡易浄水器などのシンプルなテクノロジーを届け、受益者の生活の質を大きく向上させてきた。近年はノーベル経済学賞受賞者が率いる研究所との実証実験や、VRを用いた途上国ニーズの把握など新たな方向に舵を切ったが、そこに至るまでには「規模の拡大か、システムの変革か」という葛藤があった。
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 01 ソーシャルイノベーションの始め方』より転載したものです。
中村俊裕 Toshihiro Nakamura
シンプルなテクノロジーをラストマイルへ
「途上国の課題を、いかによりよく、スマートに解決していけるか」
コペルニクを立ち上げて12年たちますが、創業前に定めたこのミッションは、いまも変わっていません。
そのミッションを達成するために着目したのが、「シンプルなテクノロジー」でした。
きっかけは、まだ私が国連職員としてインドネシアで勤務していた2006年に出合った「ライフストロー」です。これは電気も使わず、中に入っている何重ものフィルターで簡単に水を濾過できるストロー状の製品で、価格は1000円以下。浄水器といえば数百万はする高価なもの、という固定観念を持っていた私は、大きな衝撃を受けました。
そして同時にこう確信しました。「こうしたシンプルなテクノロジーがラストマイルと呼ばれる援助の手すら届かない場所へ届けば、きっと大きなインパクトをもたらすはずだ」と。
その理由を、電気の通っていない村々での「明かり」の問題で説明しましょう。通常、こうした場所で使われているのは灯油ランプですが、ここに大きな問題があります。直接的なものでは、危ない(火事の危険性)、健康に悪い(有害な黒い煙、マラリアと並ぶ健康被害の一因)、高価である(辺境ゆえの物価高、かつ収入の2割が灯油代に)といったことが挙げられます。間接的なところでは収入が減る(手元しか明るくならないので家事や内職を夜にできない)、教育の機会が減る(勉強できるほどの明るさがない)と、キリがありません。
では、この村に太陽光でLEDの明かりがともるシンプルなランプがあったらどうでしょうか。灯油に使っていたお金は貯蓄や別のことに使えます。健康を害する可能性も減り、子どもは教育の機会を得られ、貧困のループから脱する道も見えてきます。
こうした考えから開発された製品が、ソーラーライトと呼ばれるものです。実際にコペルニクはこの製品を届けることで、東ティモールで1カ月に使われていた灯油代を94%削減することができました。
こうした「届ける」を実現するにあたって、コペルニクが採用したのはクラウドファンディングの仕組みを活用した、次ページの図のような3者間マッチングのビジネスモデルです。このビジネスモデルを通じて、設立から10年、コペルニクは27カ国、約70万人の人たちに累計35万個のテクノロジーを届けることができました。
規模の拡大か、システムチェンジか
創業してから4、5年の間は、テクノロジーをリスト化し、現地コーディネーターが選んだものを寄付者の力を借り、それを使う人たちに「直接届ける」ことに注力してきました。やれば必ずインパクトは出るし、当初のミッションである「途上国の課題を、よりよく、スマートに解決していく」という姿にも近づいている実感がありました。
ところが、2015年頃、ある壁に突き当たりました。私たちがソーラーライトに着目した当時は、製造している会社はほとんどありませんでした。しかも、それをラストマイルに届けるプレイヤーもごくわずかでした。ところが、数年もたつとメーカーの数はもはや数え切れないほどになり、パナソニックなどの日本企業もソーラーライトの製造を始めました。いまではキャンプグッズにもなっているため、見たことがある人も多いでしょう。
極めつきは、国連からの次のような依頼でした。
「ミャンマーで、コペルニクのようにラストマイルにソーラーライトや調理用コンロなどのシンプルなテクノロジーを届けたいので、プロジェクトのデザインを手伝ってくれませんか?」
国連との協業は、インパクトの加速という面でも願ってもないことです。しかも、自分たちが始めたニッチなものが、メインストリームに認められていくことに喜びを感じました。
一方で、ほんの少しだけ、モヤッとするものがこみ上げてきたのも事実です。単純に図式だけを見ると、コペルニクと国連が「競合」することにならないか、と。
当時、もうひとつモヤモヤしていたことがありました。共同創業者でCOOのエヴァ・ヴォイコフスカがアショカ・フェローに選ばれたことをきっかけに突き付けられた大きな問いについてです。アショカ・フェローに選出されるとさまざまな支援を受けられるのですが、そのなかに「グローバライザー」というプログラムがあります。これは、アショカ・フェローとアショカのネットワークから選ばれた経営者・起業家、専門家とが、「どうすればもっとインパクトを出せるのか」について3カ月かけて議論し、効果的な戦略を導き出すというものです。
そのプログラムを受けるなかで非常に考えさせられたのが、次の図に示した3つの円です。
テクノロジーを直接現地に持っていく「DirectService(直接支援)」を10倍に拡大して「Lots of Direct Service(多くの直接支援)」にしたところで、届けられる範囲は限られているのではないか。それよりも、たとえばソーラーライトというテクノロジーがシステムとして自然に届いていく仕組みを構築したほうがより大きなインパクトをもたらせるのではないか。私たちが目指すべきなのは「System / Pattern Change(システムチェンジ)」ではないかと投げかけられたのです。

「ソーシャルセクターのR&D」機能という強み
国連との協業で感じたジレンマや、アショカの支援プログラムで得た気づきからは、コペルニクの存在意義や活動の限界について突き付けられているように思いました。
確かに、当時は東ティモールやインドネシアでのソーラーライトの普及の成功で、1つのムーブメントを生み出せたと感じていました。ですが、私たちが「よりよく、スマートに解決」したい途上国での課題は、「明かり」だけではありません。穀物ロスや、零細農民の低収入といった農業の課題から、プラスチックごみのような昨今、耳目を集める課題までを含みます。しかも、その課題も日々状況が変化していきます。国連も巻き込んで数多くの協力団体の力を借りられるようになったとはいえ、直接届ける仕組みだけでは拡大する需要や変化するニーズに対応し続けることはできない。どうやったらそこを突破できるか。その方法を模索しながら1年、2年と足踏みする期間が続きました。一時は自分たちで製品開発をしようかと考えましたが、これでは根本的な解決にはなりません。システムチェンジからも遠ざかってしまうし、あくまでテクノロジーを届ける面を磨いてきた私たちがいきなりメーカーと同じことをしようとしても、すぐにはうまくいかないのは明らかだからです。
迷走から浮上するきっかけは、コペルニクに寄せられる声のなかにありました。活動を始めた当初から、さまざまなメーカー企業から「こういう製品のアイデアがあるが、本当に途上国のニーズとマッチしているかアドバイスしてほしい」「つくった製品が本当にラストマイルで役に立つのか、テストしてほしい」といった依頼を数多くいただいていました。ただ、途上国のなかでもとくにアクセスの悪いラストマイルの村々で本当に役立つ製品は、製造工程の上流にあるニーズの調査から関わらなければ生まれません。結果的に、コペルニクでもラストマイルのニーズに合致した製品の開発に白紙の状態から関わり、テストする機会が増えていきました。
私たちは、この「課題を見つけてはテストする」、いわば「ソーシャルセクターのR&D」という機能こそ、他の団体にはない自分たちの強みなのではないかと気づいたのです。


RCTとの出合いから生まれた「ソリューションズカタログ」
ソーシャルビジネスの文脈で、R&Dをするという道が見えてきたことは、改めて援助業界を客観的に見ることにつながりました。
国連をはじめ、多くの援助機関では未だ、「ビフォー/アフター」のアセスメントが主流です。これは、たとえば「給食の無償提供を始めた後、子どもの学校出席率が上がった」など、援助の活動を行う前と行った後の状況を比べて援助の効果を測定、理解するというアプローチです。ただ、アセスメントに関して適正な予算配分がなされておらず、ビフォーのデータを集めていないがためにアフターとの比較ができないなど、このようなシンプルな方法でのインパクト評価すらなされていないことも多いのが現状です。
一方、調査手法はめざましい進化を遂げていて、特に、ランダム化比較実験(RCT)には大きな可能性があると感じていました。RCTとは、受益者を測定したい介入策を行う群と行わない群(コントロール群)の2群にランダムに分けて実験を実施し、2群の変化の差を比べて介入策の効果をより緻密に検証するというものです。10年ほど前は途上国支援ではほとんど使われていませんでしたが、RCT発祥の医療・製薬の分野では大きな成果を上げて、徐々に公共セクター部門でも浸透し始めていました。現在では、EBPM(エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング)、つまり証拠に基づく政策という大きな流れができつつあります。
コペルニクでは、当初からエビデンスやインパクトの測定にこだわっていました。ビフォー/アフターの比較に留まらずRCTなどのアプローチを導入し、実証実験によってどのような活動・介入をすれば、どのような課題をどれほど解決できそうか、という情報を積み重ねていけば、援助業界の効率化にもつながるのではないかと考えたのです。
もちろん、最初からうまくいったわけではありません。インパクトに関するデータや分析をより体系的かつ積極的に導入するということこそが次のステップと確信していましたが、そこにたどり着くまでに残念ながらコペルニクを離れていく人もいました。
幸運だったのは、後にノーベル経済学賞を受賞するアビジット・バナジー氏、エステール・デュフロ氏らが創始したMIT(マサチューセッツ工科大学)のJ-PAL(Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab)と協働できたことでした。J-PALは、貧困問題に関して、RCTによるエビデンスに基づいた解決策を見出し、政策提言を行っている世界的な研究所です。インドネシアの農村部で、零細農民の収入が減少する時期の収入を補填するためにどのように介入すればよいかに関するRCTで共働したのですが、この経験はコペルニクにとって多くの学びをもたらしました。
実験の設計、データ化、そしてそれをわかりやすく伝えることを徐々に磨いた結果、たどり着いたのが「ソリューションズカタログ」というアイデアです。
実証実験で効果のあったさまざまな解決策を「カタログ」化し、どんな場所でどんな製品がどのくらいのインパクトをもたらしたのか、実証実験の結果を誰でもアクセスできるよう公開することで、世界中で活動するNPOやNGOが、より自分たちに合った、効果的なテクノロジーやアプローチの導入に踏み切ることができると考えたのです。
世界各地で次々と効果のあるテクノロジーやアプローチの導入が高い成功確率で起こっていけば、アショカに問われたシステム全体の変革にも貢献できます。
アダプションとスピンオフの二刀流へ
コペルニクの歴史は、まさに試行錯誤の連続ですが、いまもまだ答えが見つかったと言える状況ではありません。目下の悩みは、肝心のソリューションズカタログにあります。このカタログは、「水・衛生・健康」「農業・漁業」「環境・エネルギー・気候」などという課題ごとに実証実験で得られたソリューションとその効果、プロジェクトの実施場所、関連するSDGsの項目で構成されています。
当面の目的としては、このカタログから閲覧者が抱える課題に対するソリューションを選び、自身の課題に適用してもらうことです。コペルニクが直接介入するのではなく、当事者に任せることでどんどんとプロジェクトが増えていくという仕組みです。直接支援によって単体で援助の規模・範囲を「拡大」する戦略から、ソリューションの選択肢を提供して現場の人たちに「再現(レプリケーション)」してもらう戦略へのシフトです。実際、ソーラードライヤーなどでこのレプリケーションはある程度成功していますが、私たちが期待していたレベルにはまだ到達していません。
この状況を打開するためのヒントは、身近なところにありました。
2020年、コペルニクからスピンオフするかたちでパーフェクトフィット(Perfect Fit)という会社が立ち上がりました。インドネシアで女性の生理の問題に向き合う会社です。そもそも生理は、話題にすること自体がタブーということも多く、しかも最も流通している生理用品は使い捨てで、ごみ問題の原因のひとつとなっています。
当初、この課題に対しては、インドネシアで最も貧しい場所のひとつであるスンバ島で、コペルニクとして再利用可能な生理用品で使い捨ての製品を置き換える実証実験を行いました。すると、製品についてだけではなく、生理がタブー視されていること自体にも大きな関心が集まりました。関心を示した企業や組織のなかにはサステナブルな化粧品の製造・販売を手がけるザボディショップ、そしてユニセフも含まれています。
こうした動きを受けて、この実証実験をリードしていたコペルニクの女性職員2人が、この事業を「会社としてやりたい」と申し出てくれたのです。登記から資金提供、ウェブサイトの制作、ビジネスプランづくりまでコペルニクとしてサポートし、2020年に会社として立ち上がりました。
カタログを用意して、それを基にソリューションを広げていくことを「アダプション」と呼んでいますが、パーフェクトフィット設立の経験を通じて、ただカタログを用意するだけでなく、熱意のある人間が特定の製品やソリューションの普及を引っ張っていくことでインパクトを加速することができるのではないかと考えるようになりました。これをアダプションに対して「スピンオフ」と呼んでいます。
この仕組みは、早速コペルニク内部でシステム化し、「ネクストCEOプログラム」と名づけました。すでに次のプロジェクトも決まっています。2019年にアメリカミズアブとも呼ばれるブラックソルジャーフライの幼虫をカモの飼料に利用する実証実験を行ったのですが、これに関わったバリ人のスタッフが、独立して実証実験を引き継ぎ、インパクトを広げたいと手を挙げてくれました。Magi Farmの名前でスピンオフするこの会社は、レストランや一般世帯から出る生ごみをブラックソルジャーフライによって処理し、さらにその幼虫を高タンパクの飼料として販売することを計画しています。

VRテクノロジーで途上国ニーズを把握する
新型コロナウイルスの感染拡大で、コペルニクは改めて存在意義を問われることになりました。現地に行くことができないなかで、現地のニーズをつかまなくてはならない。手詰まりの状況に直面して、かつて使用したあるテクノロジーが頭をよぎりました。
2017年、アジアの社会的企業が集まる国際会議で、リコー株式会社の360度カメラ、RICOH THETA(リコーシータ)を使用してインドネシアのラストマイルでの課題をVR映像で見せたのです。この試みは出席者からも高い評価をいただきました。
この技術は、いまこそ使えるのではないか。移動は制限されましたが、コペルニクのメンバーやパートナーは世界中に散らばっています。現地で途上国の現状を撮影し、そのVR映像を見せることで、企業や大学に課題を理解してもらおうと考えたのです。
その後、メルボルン大学の学生向けに、VRで現地のニーズをつかむ教材を制作したり、リコーと組んで、インドネシアでクラウドソーシングの仕組みを使って広く課題を集め、選ばれた人にリコーシータを提供して撮影してもらうというプロジェクトを実施したりしました。集めた360度映像を使って、リコー社員と新規事業アイデアを考えるワークショップも行いました。
メルボルン大学の学生からは、「このご時世で不可能だと思っていたが、バーチャルに現地視察ができた」、リコー社員の方からは、「通常の映像よりもその風景を見たという感覚が生まれ、現場の理解を深めることにつながった」とのコメントをいただきました。
こうした反響を受けて「VRのコンテンツを増やしていけば、コレクティブ・インパクト(個別にアプローチするだけでは解決できない複雑な社会課題を、行政、企業、NPOなどの立場の違う組織が手を組み解決していくこと)
を起こせるのではないか」と考えた私たちは、どうすればインドネシア以外のネットワークに広げられるかを検討しました。
その手がかりとしてピンときたのが、私が以前働いていた国連です。国連には、世界各国で活動する「国連ボランティア」がいて、その数は9000人に上ります。さまざまな国連機関に所属し、多様な課題に接しています。彼ら彼女らとつながれば、より豊富なコンテンツを作成することができるはずだと確信し、国連との共働にこぎつけました。
このプロジェクトでは、応募のあった国連ボランティア50人以上から10人を選定し、リコーから提供されたリコーシータを渡し、現地の課題を動画で撮影してもらいます。2021年12月5日の国際ボランティア・デーにローンチ予定なので、本稿が掲載される頃には、すでにその成果が新しい取り組みにつながっているかもしれません。

システムチェンジとパッションを持った人をつなげる
現在コペルニクでは、「途上国の課題を、いかによりよく、スマートに解決していけるか」という当初から掲げているミッションの達成を目指すにあたって、「どのような仕掛けをしていけば、システムチェンジをうまく起こせるのか」にも意識して取り組んでいます。そのために、外部のアダプションと内部からのスピンオフのバランスに注目したり、新しいテクノロジーの発掘を積極的に行ったりしていますが、そのなかで改めて感じるのは「パッションを持ってやっている人の力」です。
直近の取り組みで、日本の国際協力NGO向けに実証実験のトレーニングプログラムを行いました。コペルニク以外のNGOやNPOでも実証実験に取り組めるようになれば、さらにシステムチェンジが加速すると考えて始めたのですが、非常に大きな手応えを感じました。参加者からは、たとえば「持ち運びできる妊婦用のエコー」で助産師さんのモチベーションを高め、かつ出産のリスクを低減させる、といったアイデアが次々と生まれています。
一緒にソリューションを考える人が増え、「カタログ」を皆の力でつくり、熱意のある人が先頭に立って普及させていく。そのサイクルを回し続けていけば、確実に世界は変わっていくでしょう。
【取材協力】廣畑達也
【写真提供(文中)】コペルニク
中村俊裕 Toshihiro Nakamura
コペルニク共同創設者兼CEO。京都大学法学部卒業。英国ロンドン経済政治学院で比較政治学修士号取得。国連研究機関、マッキンゼー東京支社を経て、国連開発計画(UNDP)に勤務し、東ティモール、インドネシア、シエラレオネ等で、ガバナンス改革、平和構築、モニタリング・評価、自然災害後の復興などに従事。2009年、国際開発をより効果的なものにするというビジョンのもと、エヴァ・ヴォイコフスカとともにコペルニクを創設。2012年、世界経済会議ヤング・グローバル・リーダーに選出される。同会議の「グローバル・アジェンダ委員会2014-2016」の「持続可能な開発」委員も務めた。大阪大学COデザインセンター招聘教授。