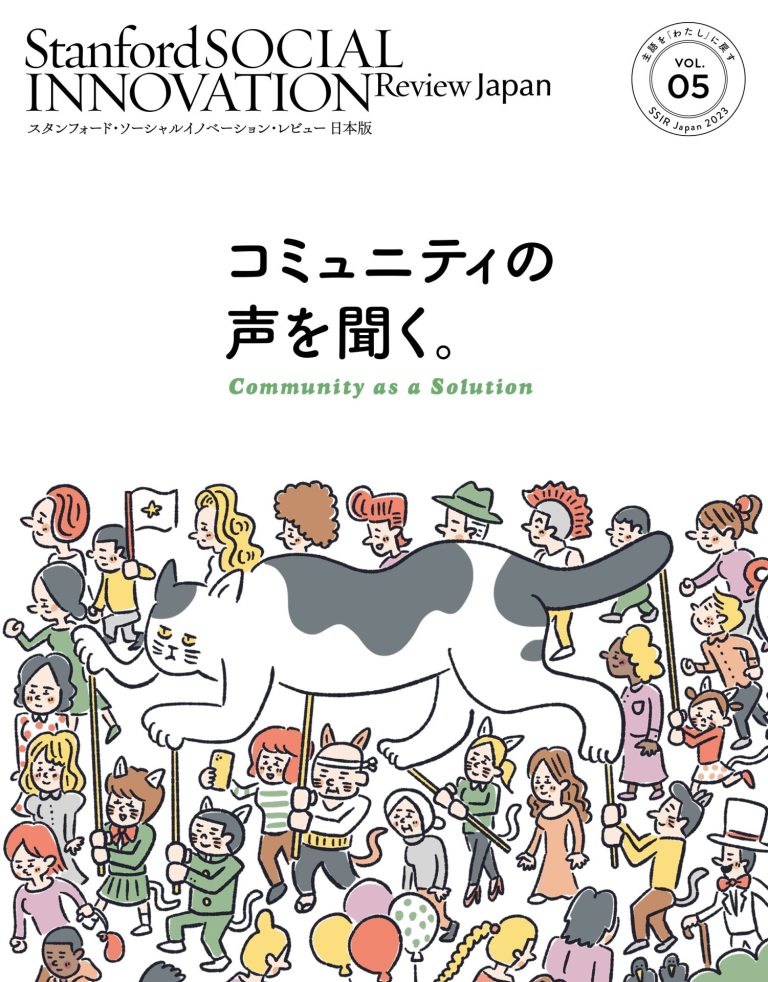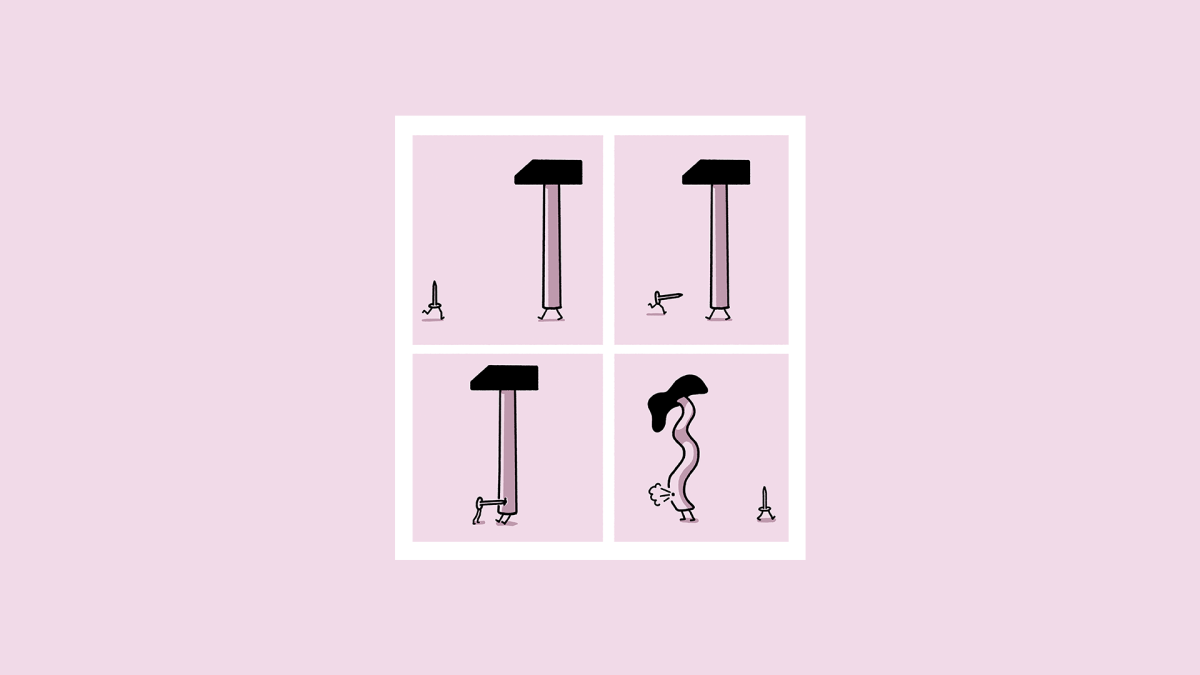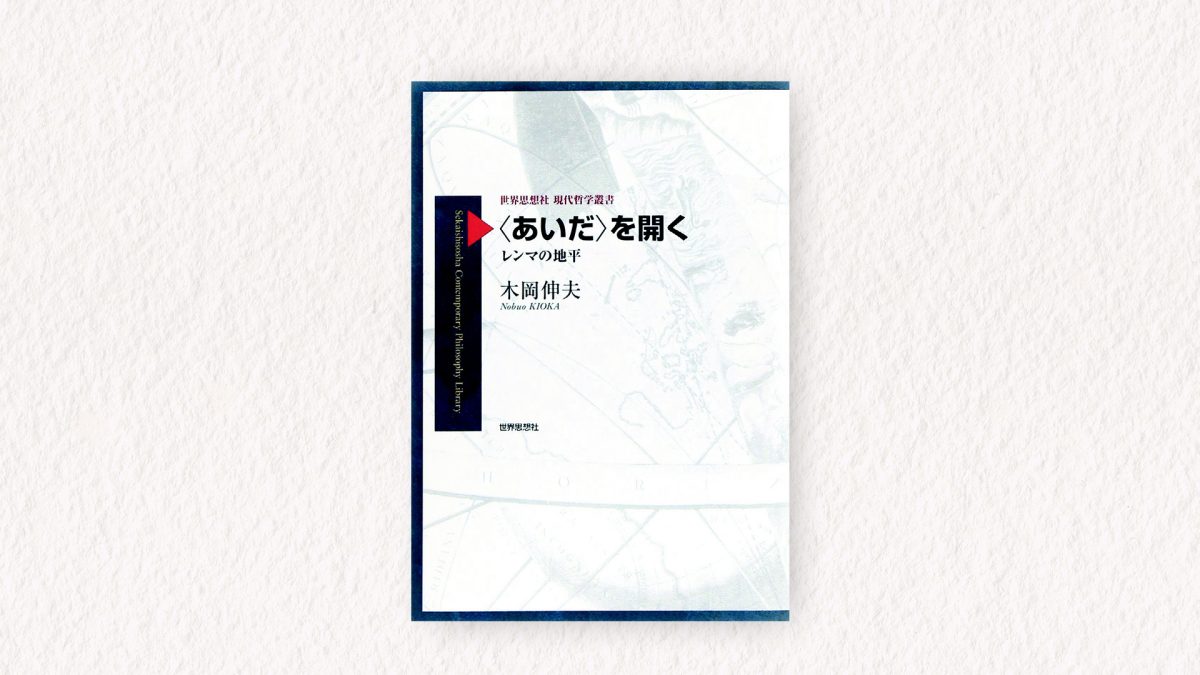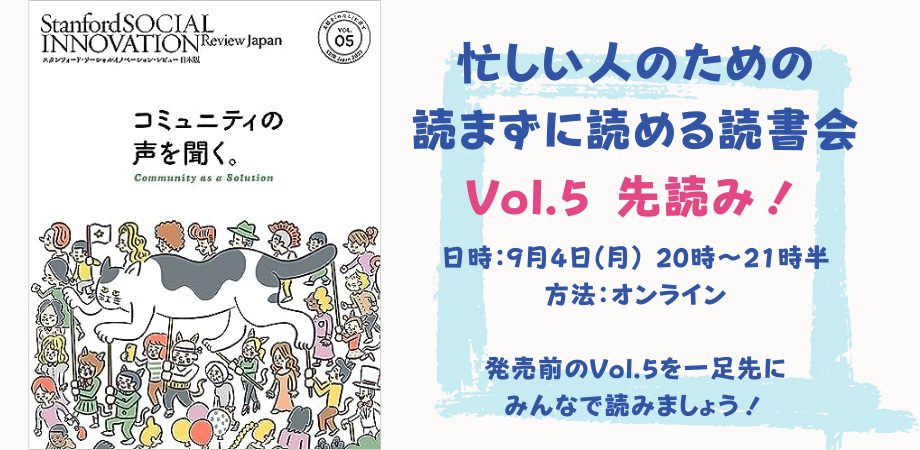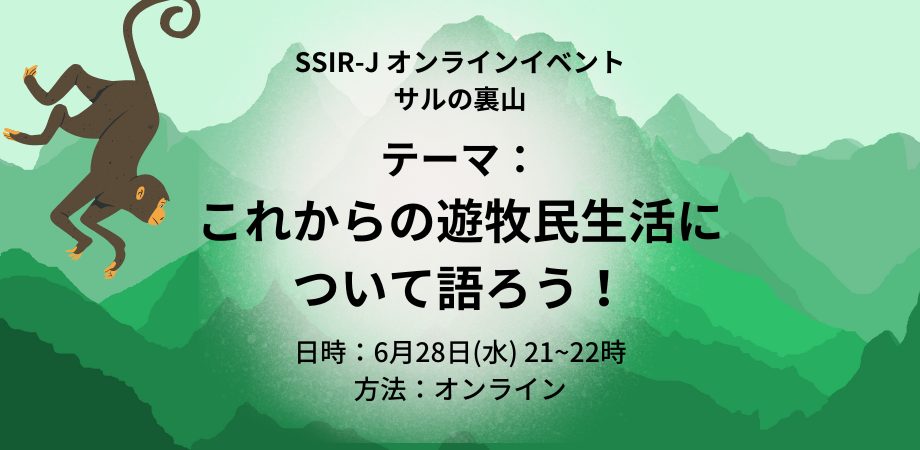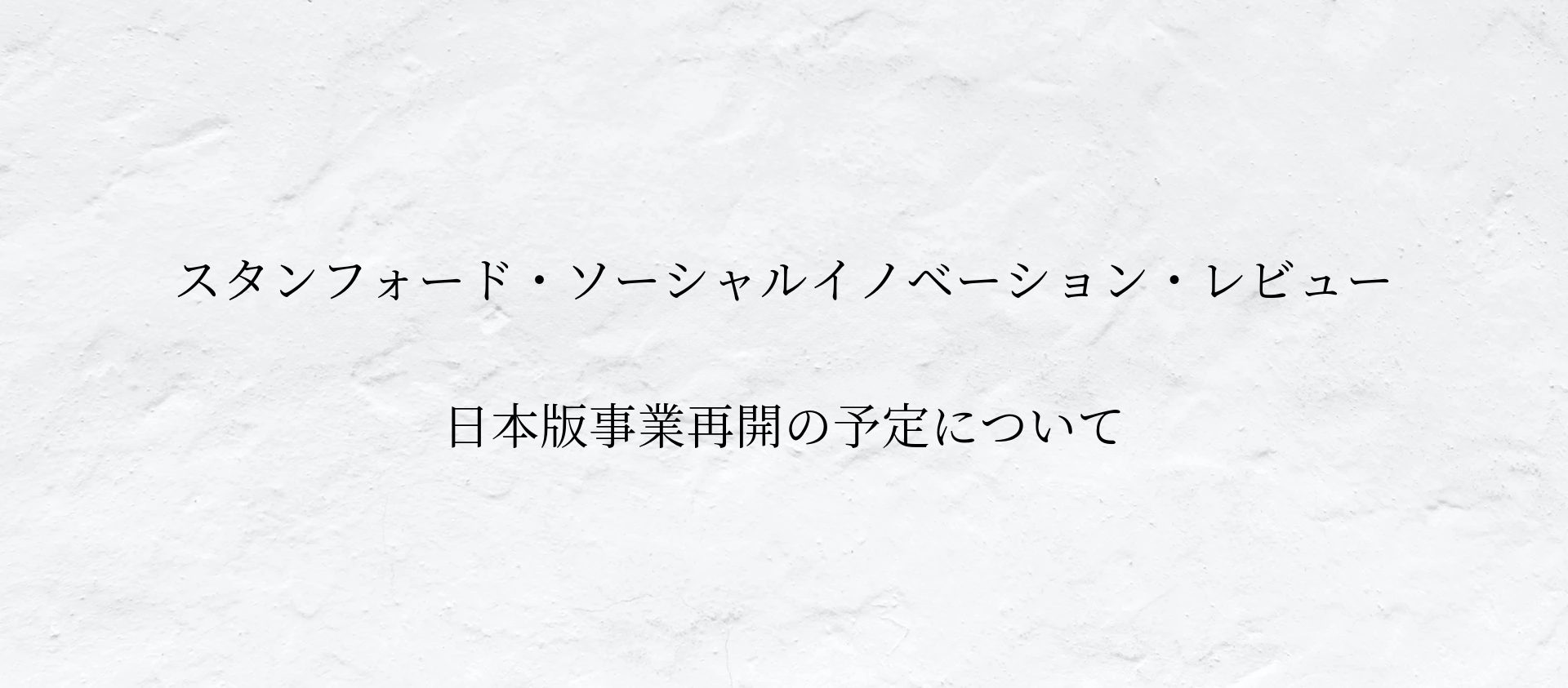
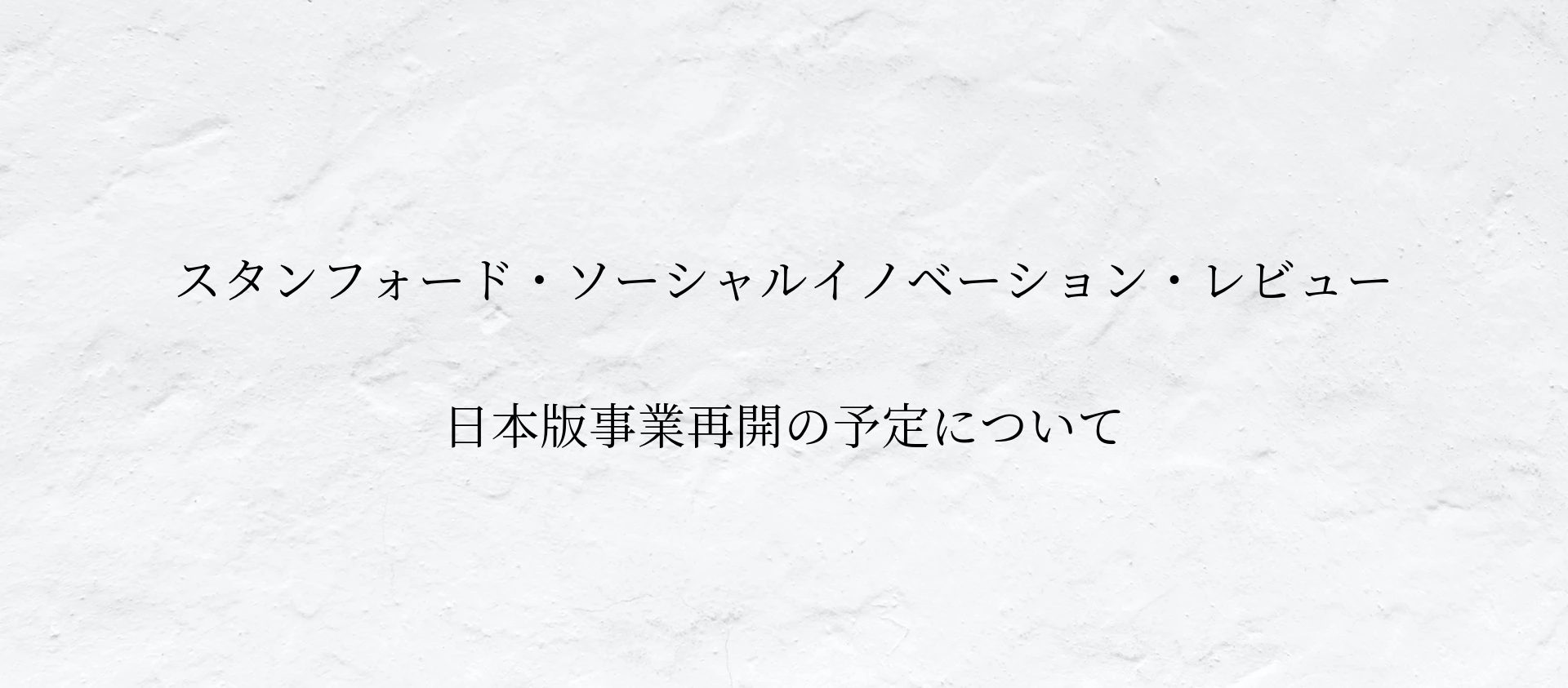
最新記事
SSIRの翻訳記事やSSIR-J本誌掲載記事を限定公開しています。
イベント
SSIR-J コミュニティで実施される、イベントや読書会、協働プロジェクトをご紹介します。
-
わたしと人類と選挙(スピーカー:加生 健太朗さん)【サルの裏山】
「サルの裏山」では、SSIR-J コミュニティメンバーの「素顔」をその人が今一番話したいテーマでSSIR-Jスタッフが深掘りします! SSIR-J会員(メンバー・ビジター)限定のイベントになりますので、会員登録がまだの方...
-
【SSIR-J Vol.5 先読み】読まずに読める読書会
忙しくて、忙しくてなかなか本が読めない…。そんな人のための読書会を開きます。 読む1冊は、9月7日にいよいよ発売されるスタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 第5号『コミュニティの声を聞く。』です。今...
-
これからの遊牧民生活について語ろう!【サルの裏山】
SSIR-Jの人気イベント「サルの裏山」がリニューアルしました。今までSSIR-Jスタッフが今一番話を聞きたい人に「ここだけの話」を聞く会だったのが、2023年からは聞き手をSSIR-Jコミュニティメンバーに託し、担当し...
-
『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー日本版 VOL.04』刊行記念 「覚悟をもって越境する人たちのための『コレクティブ・インパクト』 」梅田惠×番野智行×井上英之×中嶋愛 トークイベント
「異なるセクターが協力し合わなければ、複雑な社会課題は解決できない」。あたりまえのように思えます。でもその「あたりまえ」のことを実行に落とし込めないために、善意、人、お金をいくらつぎ込んでも社会システムの根本的な変化を起...