複雑な問題解決にデザインの力を活かす
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 03 科学技術とインクルージョン』のシリーズ「科学テクノロジーと社会をめぐる『問い』」をもとに制作したSSIR-J Webオリジナルコンテンツです。
筧 裕介 Yusuke Kakei
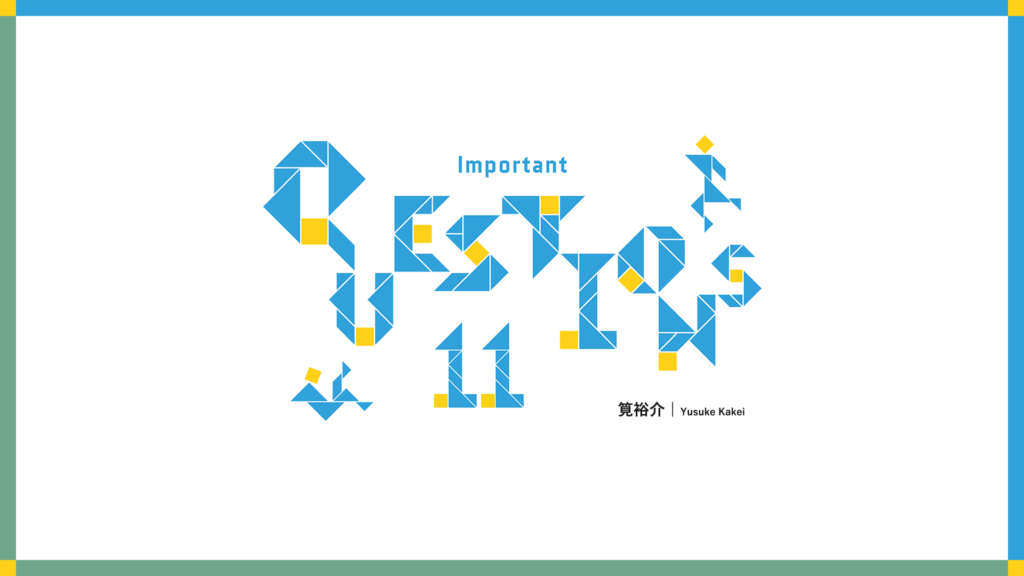
なぜ、サイエンスの知恵が現場で生かされないのか。これは長年にわたって地域の課題解決に取り組むなかで募ってきた問いだ。その要因の1つとして考えられるのが、アカデミックな研究者と現場のあいだを大きく分ける「言語の壁」ではないだろうか。
私は10年以上前に社会人経験を経て大学院に入った。それまでは企業のマーケティングを支援する仕事で、いかに企業価値を高められるかに注力していた。2001年9月11日のNYでの同時多発テロ事件の被災をきっかけに、世界そして日本には深刻な社会課題があちこちにあるという問題意識が芽生えた。従来型の利益追求だけの仕事ではなく、そうした社会課題を解決するためにデザインの力を活かしたいという思いが募り、都市や社会全体のシステムをデザインする知識を学ぶために大学院に入った。
しかしアカデミックな世界に入るとまさに「言語の壁」に直面した。あまりにも言葉遣いが違いすぎてついていけず、理解できるようになるまでに3年程度かかったと思う。
その背景には研究者側と、現場の実践者側の、両方の問題がある。専門分野における研究と情報交換に閉じがちなアカデミックな世界では、そこで使用される言語は意図せずとも外部の人間にとって複雑でわかりづらいものとなる。そしてときに「外の人がわからなくても仕方がない」というスタンスをとってしまう。
一方で現場側も、そもそもアカデミックな言語がわからないし、それをわかろうとする人も少ないという問題がある。こうした双方向のスタンスが、両者の分断を深く広いものにしてきたという側面はあるだろう。
両者をつなぐ取り組みとして、大学や企業のなかでオープンイノベーションを推進する部門がつくられたりしているが、成功事例は少ない。うまくいっているのは、研究者が自分の科学的知見や技術を活かして起業するケースがほとんどではないだろうか。海外では大学の研究者が起業することは多いが、日本ではそのような仕組みも整っておらず、失敗のリスクもあるのでハードルが高くなっている。
研究者は「自分の研究を社会実装すること」にもっとこだわってほしいという思いはある。サイエンスの活動とは、突き詰めればそこで得た知見がいかに社会に還元されるかに帰結するはずだからだ。
もちろん、すべての研究者が起業すべきとは考えていないし、基礎研究が得意な人はそれをとことん追求すべきだ。ただ、もしそこで生まれた知恵を実践知に変えていく人が出てくれば、より社会実装が進むだろう。
その役割を担うのが「デザイナー」だと考えている。こうしたデザイナーに求められるのは、単に「中間に立って翻訳する能力」ではなく、「自分の専門領域を持って両方の言語を操る能力」である。
その意味で「ドクター(博士号取得者)」が増えていくことが必要ではないか。日本では博士号取得者自体が少ないが、その大きな理由の1つは、アカデミックな世界において博士号取得後の就職先が不足していることだ。近年は社会人ドクター(就業しながら、もしくは一旦退職した後の博士号取得者)が増えつつあり、社会と研究の接点を増やすという意味で、大きな期待を持っている。
複雑な問題を解決するためには「誰とやるか(Who)」が重要になる
言語の壁を乗り越えてアカデミックと現場の両方の世界が交われば、もっと大きな社会的インパクトを出せるはずだ。
複雑な問題を解くためにまず必要となるのは、「どうやるか(HOW)」の前に「誰とやるか(WHO)」ではないかと考えている。当然のように複雑な問題は単独では解決できず、多様なアクターが必要になるからだ。その領域に深い知見を持つ人たち、とくにアカデミックな領域で専門性がある人とコラボレーションしてサイエンスの知恵を取り込めれば、飛躍的に実効性を高められるだろう。
近年取り組んでいる活動も、「どうすれば解けるか」ではなく、「この人たちとコラボレーションできたら解けるかもしれない」という可能性をイメージできたときに始めたものだ。
たとえば認知症の活動は認知症未来共創ハブへの参画が大きなきっかけになった。これまで認知症の問題は医療の分野で議論されがちだったが、未来共創ハブは日本で始めて市民、行政、医療、大学の多様なアクターが手を組んだプラットフォームだ。
とくに大切にしているのが「認知症の当事者の思い・体験と知恵を中心にすること」だ。これは、従来の医療や政策に当事者の声が十分に反映されてこなかったことへの反省がある。当事者の声を改めて丁寧に集め、それをもとに共創ワークショップ、政策提言、記事や書籍などのコンテンツ制作・普及に取り組んでいる。
科学的リテラシーを高めるために何ができるか
認知症の他に近年注力しているのが「脱炭素まちづくり」の活動だ。脱炭素、認知症どちらの問題に対しても、社会的な意識が十分に醸成されていないと感じている。認知症はいまでも偏見や誤解が根強くある。脱炭素についても、世界的な視点からすれば周回遅れで取り残されている段階にある。
その理由の1つが、サイエンスに対するリテラシーが軽視されていることではないか。脱炭素の問題について、日本ではサイエンスに基づいた長期的な視点よりも、短期的な視野で物事を考える傾向にあると感じている。
なぜなら、今社会を担っている大人たちは、脱炭素を実現しなくてもぎりぎり困らない世代だからだ。さらに、東日本大震災をきっかけに、脱炭素よりも目の前の経済的危機やエネルギー不足の解決のほうに注力されるようになったこともある。
実は震災が起こる前までは、日本はこの分野で最先端を走っていた。1970年代のオイルショック以降、日本は石油資源へのエネルギー依存を脱却して世界トップレベルの省エネ国へと成長した。原発もその中核産業として育ててきた。そのさなかに震災が起こり、「環境問題をやっている場合ではない」状態になった。その間にヨーロッパはパリ協定やSDGsの流れで改革が進み、日本が出遅れてしまったという経緯がある。
しかし、度重なる災害や異常気象によって、近年ようやく気候変動の深刻さが身近な問題として捉えられるようになった。今こそサイエンスに対するリテラシーを高めて、それぞれの地域の課題解決にどう活かすのかを考えるときではないだろうか。
ではリテラシーを高めるとはどういうことなのか。それは決して「複雑なものを単純化して伝える」ことではない。むしろ「複雑なものを複雑なままにしたうえで、わかりやすく伝えられるか」が問われている。そこにデザインの力が活かせるはずだ。
たとえば認知症の人が見ている世界というのは、一般にイメージされる「物忘れ(記憶能力の低下)」とひとくくりにできない。進行スピードも症状も人によって異なり、記憶以外の五感や運動機能にもさまざまな症状があらわれる。約100人の当事者へのインタビューに基づいてWebと書籍で表した『認知症世界の歩き方』では、代表的な症例をいくつか説明しながらも、「一人ひとりによって感じ方が異なる」複雑な世界のありようを、認知症当事者や家族など医学的知識がない方でも理解できるようにデザインした。実際に当事者のご家族の方から、「なぜそういった行動をするのかを理解して、接し方が変わった」などの反響があった。
2022年から全国で展開している「脱炭素まちづくりカレッジ」でも、気候変動の問題の複雑さを伝えるチャレンジに取り組んでいる。このまま改善されなければ社会がどんな姿になるかをシミュレーションした映像やワークショップで「未来体験」を行い、そのあとに社会としての解決策や自分にできるアクションを考えてもらう。主に地域のリーダー人材育成を目指すプログラムではあるが、次世代を担う子ども向けの出張授業も行っている。
私はデザインとは、「正解のない、いろいろな要素が入り混じった複雑な問題を解くこと」であり、「美しさや楽しさをもって人や思考を未来に飛ばすもの」であると考えている。どうすれば異分野の人たちをつなぎ、やっかいな問題を解決してよりよい社会をつくれるだろうかと考えること自体に、わくわくしてこないだろうか。


