外国人と日本社会の「間」に立つ者として
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 05 コミュニティの声を聞く。』のシリーズ「コミュニティの創造と再生をめぐる『問い』」より転載したものです。
林 晟一|Seiichi Hayashi
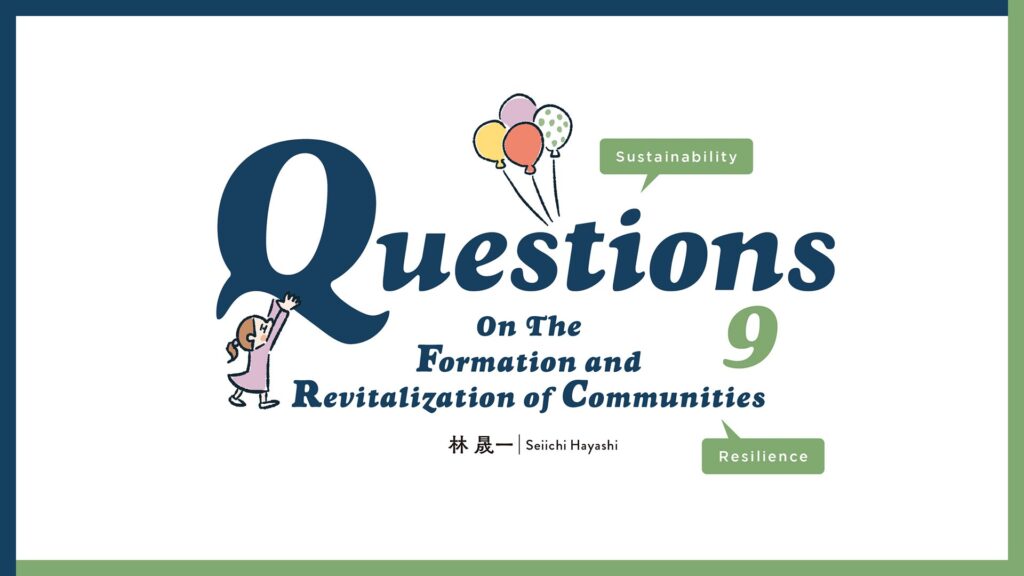
鬱陶しいけれど、逃れることができないもの
私にとって「在日」(在日韓国・朝鮮人)のコミュニティはどこか鬱陶しいものであり、それでいて、社会で生きていく以上は逃れられないものでもあった。私が子どもの頃は、在日コミュニティには民族マイノリティならではの側面がくっきり残っていて、日本人風の「通称名」を悪、「本名」を正義と捉える風潮も根強くあった。民族アイデンティティを子どもに残そうという意欲がとても高かったのだ。もちろんそれは「よかれ」と思ってのことなのだろうが、在日3世として、ずっと通称名で日本の学校に通っていた私にはとても暑苦しいものだった。
そこから逃れようとしながら、私は自分のアイデンティティを形成してきた面がある。しかしいまでは、在日コミュニティならではの温かさや絆というものもたしかにあると感じている。結局自分も、在日コミュニティから目に見えない恩恵を受けて育ってきたのだ。
2022年末に刊行された著書『在日韓国人になる』には、在日コミュニティを批判している箇所が少なからずある。それでも、この本を読んだ在日の友人の母親からは、「いい人がいるからお見合いしないか」とのお誘いがあった。まったく興味がないので丁重に断ったけれど、このように「おせっかいを焼いてもらえる」のも、コミュニティのある種のアドバンテージなのだろう。就職にしても結婚にしても、規模は縮小したとはいえ在日コミュニティのつながりはいまだに健在らしい。
「日本人」対「在日」の構図に埋もれてきた声
日韓の歴史認識問題や、「在日」をめぐる一部日本人のいら立ちは、多くの人が知るところだろう。一方で、在日コミュニティ内で二重、三重に抑圧されてきた人たちについては、あまり語られてこなかったように思う。在日の女性やLGBTQの人々に関わる、複数の差別や抑圧が交わるインターセクショナリティの問題は、見過ごされがちだったのではないだろうか。
日本人コミュニティ同様、もしかするとそれ以上に、在日コミュニティは男性優位社会で、「男らしさ」の規範を重視しやすかった。民族学校の部活では、ボクシングやサッカーなど体をぶつける激しいスポーツが好まれた。私も幼少期に参加していたチェサという朝鮮半島流の法事では、儀式をすませたあと男性から先に食事をとった。女性の分が配膳されるのは男性が食べ終わってからだった。小さいときから「朝鮮男はこうあれ、朝鮮女はこうあれ」といった規範を何度耳にしたことだろう。在日家庭における父親のDVは2000年代の映画などで多少取り上げられはしたものの、広く議論されることはなかった。
1980年代から発生した一部日本人による民族学校生徒のチマチョゴリ切り裂き事件は、在日の悲劇として語られる。当時、民族学校に通う男子生徒の制服はブレザーで、女子生徒の制服だけが民族衣装であり、事件の主たるターゲットは正確には「在日女性」だった。在日朝鮮人が中心となって築いてきた民族学校は、「民族教育の権利」という理念に賛同する日本のリベラルからしても守るべき対象であったが、民族学校内部での体罰、性差別、ハラスメントなどの課題は「見えないもの」とされやすかったのではないか。
このように、「日本人コミュニティ」対「在日コミュニティ」という対立軸が設定されることで、埋もれてきた課題がある。これからの在日コミュニティをよりポジティブなものとするためにも、これまで埋もれてきた側面に目を向けながら明日を見据える必要があると考えている。
社会から疎外されるほどコミュニティは強固になる
現実を見れば、在日韓国・朝鮮人の数は減少しつづけており、在日コミュニティそのものは縮小再生産の一途をたどっている。民族学校を出て在日系企業に就職する人の数はかつてほどではなく、日本の学校に通って日本の企業に勤め、日本人と結婚する在日も多い。そういう意味では、「『在日コミュニティ』なるものは、いまもあるのか」を問う必要があるかもしれない。
しかし、在日が社会から疎外されればされるほど、在日コミュニティの結束が強くなる側面があるのも事実だ。
2002年9月に小泉純一郎元首相が北朝鮮を訪れ、金正日元国防委員長が過去の北朝鮮当局による日本人拉致を認めたことで、日本社会における在日バッシングが強まった。現在でも、SNSを見れば「朝鮮人は帰れ」「チョン」などといったヘイトスピーチが垂れ流されている。そうしたなか、日本社会から完全なよそ者として扱われていると自覚せざるをえなくなった在日が、コミュニティを心のよりどころとするのも不思議ではない。
1980年代から90年代に東京都江戸川区の公立小中学校に通い、日本人らしくあることを疑わなかった在日3世の私も、2002年以降、「日本人と同じように生きてきたのに社会から拒まれた」というある種の被害者意識を強めた。だからといって、私の場合は親や親族となるべく距離をおきたかったから、在日コミュニティとの絆を深める気はなかった。けれど、そういう人たちがいてもおかしくないし、それもまた生きる戦術の1 つであろう。
「間」に立つ者として少数派と連帯していく
在日コミュニティが縮小再生産にあるなか、そこから影響を受けて育った人たちがこれからも在日コミュニティを維持しようとするのなら、コミュニティの翼ウィングを広げていく必要があるのではないか。
社会科学では「ミドルマン・マイノリティ」理論と呼ばれるものがある。これを踏まえていえば、ホスト社会とニューカマーの「間」に立ち、経済的に一応安定した生活を送る人(ミドルマン)には、社会で果たすべき役割がある。
今後も日本に住む外国人が増えつづけることは間違いない。戦後日本の最初期の移民ともいうべき在日は、実質的な「移民国家ニッポン」社会のミドルマンとして、他の外国人を支える立場にあるべきではないか。
日本で永住権を取りたくても取れない外国人からすれば、国籍や参政権の有無などの違いはあるが、権利の面で日本人とだいぶ変わらなくなった在日の立場は恵まれて見えるだろう。在日には、日本社会とニューカマーのコミュニティの間にある者として、後者に寄りそい、同じ方向を見つめながら、目の前の日本人コミュニティに朗らかに語りかけていく必要があると私は思う。
今年6月に強行採決された改正入管難民法をめぐる動きをみても、日本人の多くは外国人政策にあまり関心がなさそうだ。しかし在日にとっては、外国人政策の動向は死活問題といっても過言ではなく、同法のもと抑圧されるかもしれない外国人のことは決して他人事ではない。これからもし日本経済が大きく傾いたら、排外主義者が「出ていけ」と後ろ指をさすのは、「彼ら」であると同時に「私」であるのだから。
それならば、味方は多いに越したことはない。在日コミュニティを民族性(エスニシティ)に関わらないかたちで開いていく必要がある。在日という言葉自体、人数の面からして、もはや韓国・朝鮮人の専売特許とみなすことはできない。その言葉とともにコミュニティを大きく開き、多様なルーツを持つ人たちが「在日」を名乗り合う未来をつくれないものだろうか。
マイノリティの境界を越えて「在日」の翼を広げる
外国にルーツを持つ人だけでない。性的マイノリティやさまざまなハンディキャップを抱える人々も、いつだって排外主義者のターゲットとなりうる。みんなでこの世を生き抜くためにも、他のマイノリティとの境界を越えて、コミュニティの外郭を広げていくことは重要だ。
在日は排外主義者の怒りをなだめすかし、やり過ごしつつ抵抗しながら、さまざまな人々と少しずつ連帯を深めるべきだろう。
もしそこで、在日コミュニティが純粋な在日コリアンというものに固執して、他のマイノリティとの連帯に抵抗するのであれば、それはヘイトスピーチを垂れ流す日本の排外主義者と大きな違いはない。ホスト社会とニューカマーのコミュニティの間に立つ在日の存在意義が問われることになるだろう。同質の集団に安住すれば心穏やかではある。けれどその平安は、しばしば外集団への根強い差別に裏打ちされたものとなりうる。
「多文化共生」のスローガンが各所で掲げられているが、それはこれから目指すべき高尚な理念などではなく、現実にはとっくに進行していることでもある。大阪でヘイトスピーチに反対するパレードがあったとき、在日とともに声をあげたのはゲイの日本人青年だった。後日、その青年たちがソウルでLGBTQのデモに参加したとき、今度は在日の青年がソウルに駆けつけた(木村元彦『橋を架ける者たち』集英社新書)。彼らは互恵関係を育みつつ、コミュニティ間の境界と国境を同時に越えていたのである。
人種、民族、国籍、性別、性的指向、障害などをめぐる差別に直面するとき、差別される側の人々は少しでもコミュニティをまたいで横の絆を探るほうが得策だ。在日の権利獲得の歴史は、まさに日本人や国際社会のサポーターとともに歩んだものだった。そのことを思えば、私たちには在日コミュニティを開き、隣人の手をとり、希望を共創する使命があるはずだ。ささやかな願いも込めて、私はそう考えている。
【構成】中村未絵


