社会変化は個人の内面から始まる。
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 05 コミュニティの声を聞く。』より転載したものです。
メア・タラー
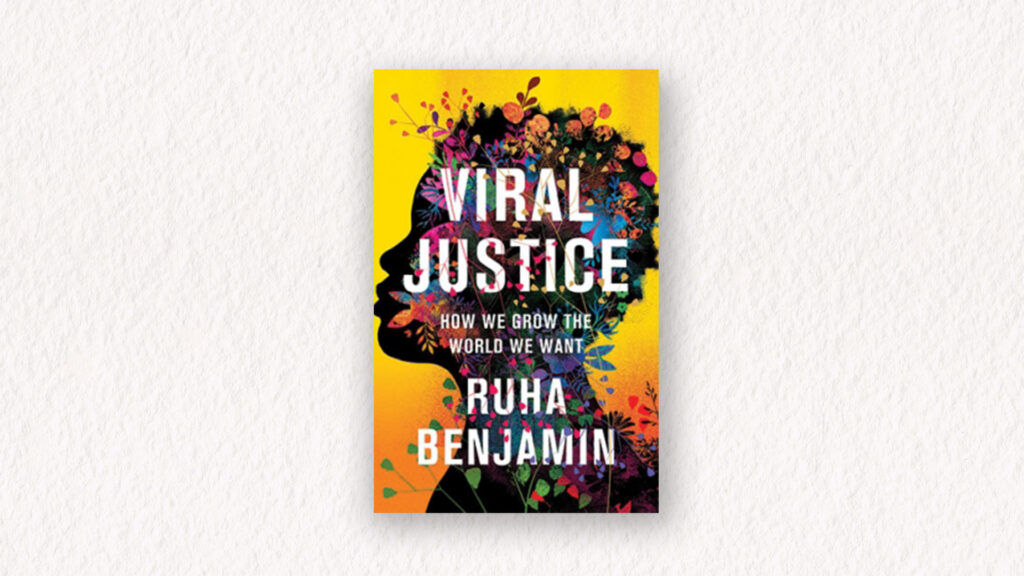
「Viral Justice: How We Grow the World We Want」
ルハ・ベンジャミン Ruha Benjamin|Princeton University Press|2022
新たな社会変化の枠組みをウイルスになぞらえるとは、思い切った試みだ。ルハ・ベンジャミンは著書『人から人へ正義を拡散する――自分たちの望むような世界を育むためにできること』(Viral Justice: How We Grow the World We Want)で大胆な説を展開している。
「人類最大の敵はウイルスではない」。プリンストン大学の教授(アフリカ系アメリカ人研究)で、アイダ・B・ウェルズ・ジャスト・データラボ(Ida B. Wells Just Data Lab)のディレクターを務めるベンジャミンはそう訴える。
本書で「ウイルス」とは、死を招く感染症のことではなく、コレクティブ(集合的)な世界構築モデルのことを指している。そのモデルをベンジャミンは、人々の価値観や大切にしたいことの優先順位を望ましいものに並べ直す「世界の再構築(reworlding)」と呼ぶ。
本書における社会変化の理論の基本的なコンセプトは「人から人に感染する力」だ。個人の内面で生まれたものが、他者との関わりを通じて外へと広がることで、人々の選択や行動が好ましい方向へと変わる。ベンジャミンはさらに「口先では正義を唱えながら、実際には不公正なシステムに加担している自らを直視しよう」と言う。それによって私たちの内面にある力を意識して拡散できるようになる。「人の考えや習慣、行動は、周囲によって形成されると同時に、周囲の環境形成にも影響を与えている。その影響力を自分たちの手に取り戻そう。本書は一人ひとりがその一歩を踏み出すための呼びかけである」。
ベンジャミンは、自身の生い立ちと社会学的考察を行き来しながら、アメリカの医療、教育、収監制度に幾重にも織り込まれた差別を分析し、そうしたシステムが「さまざまな側面でいかに人々を苦しめているか」を解明している。冒頭では、アメリカの黒人は暴力への恐怖に絶えずおびえながら暮らしていると述べ、「幼い頃は、眠っていても常に身構えていた」と自分の人生を振り返る。「銃弾が飛んでくるのではないかと夜な夜なおびえ、眠れなかった。だからこそ、夜中にブリオナが警察に射殺された事件には衝撃を受けた」。ブリオナ・テイラーは、2020年3月にケンタッキー州ルイビルの自宅で就寝中に警官に射殺された黒人女性だ。警官は計32発を発砲し、麻薬密売人を捜査していたと主張した。本書では、こうした黒人が置かれている深刻な状況を裏付ける主張や事例が列挙され、暴力の現実だけでなく、世代を超えて広がる影響や細胞にまで染みついた恐怖心が綴られている。
この恐怖の蓄積による影響を、行動保健学の研究者であるアーリーン・ジェロニムス教授は「摩耗(weathering)」と呼んだ。ベンジャミンはこの概念を引用しながら、「いたるところに存在するストレス要因や抑圧要因がいかにして体内に取り込まれ、予防可能であったはずの病気を引き起こし、寿命を縮めているか」を説明する。そして、そうしたストレス要因や抑圧要因は、さまざまな構造的不平等の元凶であり、人間がつくり上げたシステムに由来するものだと主張する。「制度と個人が持つ根拠なき偏見によって、過酷な環境が日々つくり出され、再構築され続けている」。
アメリカの医療制度には人種差別がはびこっているが、もっともらしい言い訳でカモフラージュされている。黒人が病気になれば、「遺伝性疾患」とか「、予防接種や治療をためらったせいだ」とされる。「黒人の皮膚は厚くて丈夫」だから白人ほど痛みを感じないという、まことしやかな説まである。こうした差別を取り繕う行動から、「摩耗」が2つの意味において重要であることが浮かび上がってくるとベンジャミンは言う。1つは「公衆衛生において認識すべき考え方」であること、もう1つは「黒人差別があらゆる人の生活と未来に悪影響を与えていることを理解し、それを正面から指摘するための枠組み」であることだ。
「摩耗」はまた、数百年前から黒人を苦しめてきた奴隷制や収監、死ぬまで逃れられない警察の取り締まりと監視の産物でもある。国家的暴力であり、制度に組み込まれた残虐行為であり、血圧上昇や老化の促進、精神面における健康問題を引き起こしているとベンジャミンは追及する。医療の人種間格差は、生物学に起因するものではなく、時間とともにつくり上げられた社会現象であると本書では繰り返し指摘されている。
この構造を変えようとする動きは官僚主義と政治に絡めとられて、一向に進まない。それでもベンジャミンは悲観していない。こうしたシステムによる危害を一掃するうえでは、一人ひとりの気づきとそれに対して責任を負うことが第一歩だと主張する。「身近なところから始めてほしい。たくらみを暴き、私たちを苦しめる根本原因を突き止め、相互のつながりを受け入れ、もういい加減前に進もう」。
制度の欠陥を埋めるためには、一人ひとりが少しずつ自力で取り組んでいくしかないと呼びかける。「魔法が使えなくても、世界を変えることはできる。作戦を練り、励まし合い、自分たちの関係性を新たに描き直すだけでいい。心から望んでいる世界を育んでいこう。常に愛情を忘れずに行動しよう」。
さらに、「脅威は、周囲の人間でも、境界の向こう側にいる人間でもない。いまも昔も、鏡に写る自分こそが脅威である」と指摘する。だからこそ、前に進むためには「新たな考え方を個々人が身につけ、人との関係を立て直すために種をまき、制度化された不公正を根絶し、新たな可能性を構造的につくり上げていく必要がある」と提案する。
もちろん、この戦略の成否は一人ひとりの意欲にかかっている。自らを改革し、やるべきことをやり、アメリカで暮らす人々の健康とウェルビーイングのために努力しようとする自発性が欠かせない。とはいえ、社会から取り残された人々への暴力が蔓延し、政治的断絶が深まる時代においては、本書の唱える楽観論は絵空事に思えるかもしれない。
しかしベンジャミンの主張によれば、システムと社会の変化を実現させるために一人ひとりができることを思い描こうとするとき、「人から人へ伝える力」こそが、その道筋を示してくれるという。人間関係や、人と人との結びつきには大きな力が秘められているのだ。個々人の試みは、自らの信念や使っている言葉を問い直すところから始まる。正義を重んじる言葉、システムの不正義を非難する表現を意図的に使えば、小さな変化を起こせるという。「個人商店主なら、カナダ・トロントのジェラード通りにあるドーナツ店グローリー・ホールのように、『白人が黒人に同情して白人至上主義を批判するだけでは何も変わらない。白人自身が向き合うべき問題と捉えない限り解決しない』と書かれた看板を掲げ
ることから始めてみるのもいい」。
システムにおける不正義と摩耗に対してベンジャミンが提案する解決策の背景には、警察や刑務所といった制度の廃止(アボリション)への強い願いがある。国家的暴力や、人種差別的な取り締まりと監視がもたらす摩耗に終止符を打つために、次のように主張している。「この文脈において、正義とは警察の改革ではない。〔逃亡した黒人奴隷を捕まえて所有者のところに連れ戻す〕奴隷パトロールとして始まり、必要なものだという思い込みと時代遅れな価値観によって引き継がれてきた制度を徐々に廃止していくことである」。また、「取り締まり、刑罰、刑務所」のための予算を打ち切り、最終的に廃止することの重要性を繰り返し説き、「正義への共感を広めたいという思いは、警察のない世界をつくりたいというアボリショニストの挑戦と連帯するものだ」と述べる。
取り締まりに代わるものとして本書が提案しているのが、政府による社会サービスのインフラ投資だ。その一例として、ワシントン州シアトルで2020年の警察に対する抗議デモの最中に発足した「シアトル連帯予算(Seattle Solidarity Budget)」という連合体を紹介している。参加組織は200以上で、同団体が求めているのは「監視のために警察の予算を増やす」のではなく、公益テクノロジーに投資して「デジタル・スチュワード(デジタル情報、デジタル資産の管理人)が市民と協力する」態勢づくりだ。彼らは、予算とは市や州、国の価値観を反映した「モラルを表明する文書である」と主張し、主な活動は「公教育に関する会合の主催、市の議会や集会への参加と提言」である。シアトル連帯予算が音頭を取って始まった地域と行政機関の集合的な取り組みで、「警察予算が2年連続で削減されたほか、最も周縁化された市民を支援する投資が実現した」という。ベーシックインカムの支給実験プログラムもその1 つだ。
とはいえ、黒人監視や刑務所に充てられる連邦政府の年間予算は1970年代以降、何十億ドルという単位で増えており、アボリションを提言する政治家はほとんどいない。非現実的で突飛な解決策にしか思えないのだろう。一方で、ギャラップが2020年に実施した世論調査では、警察に対する信頼度が過去最低水準に落ち込んだ。こうした世論の変化は、いずれ警察の取り締まり方針が変わり、予算が減額される前兆かもしれない。
本書の中で、アメリカにおける黒人奴隷制の歴史を読んでいるとき、パキスタン在住の筆者は大英帝国の負の遺産に思いを巡らせていた。世界各地で行った植民地化の名残や、弾圧が招いた摩耗の影響がインド、パキスタン、バングラデシュを含むインド亜大陸の国々でいまだにくすぶっている。大英帝国の度を越した行為に関する記述を、イギリスの教科書で目にすることは滅多にない。イギリスには自責の念もなければ、国家としての内省も不十分なのだ。表向きは大英帝国の非を認めても、大半の国民はそ
れに対して償うのは論外だという意見で、賠償すべきだという話も持ち上がらない。
よって、本書にも書かれているように、米英をはじめとする帝国主義国家の「世界の再構築」を実現するためには、ベンジャミンの言う「根本的なウソ」、すなわち能力主義という神話に国家として向き合い、それを正さなくてはならない。私たちの社会はそのウソを土台にして築き上げられている。
必要なのは、学習環境の変革であり、「レンガを一つひとつ積み重ねるようにして、若者の心に新しい土台を築き上げていかなければならない。真実を語ることでしか、若者の信頼を得ることはできないのだ」。
ベンジャミンは、教育における「世界の再構築」を実現する方法として、学校を「共感と連帯を育む場」と捉え直すことを提案する。具体的には、「和解と修復的正義のための対話プロセスの教育」「有色人種の教師の採用と雇用維持の優先」「教育課程に黒人の歴史と民俗学を盛り込むこと」などを挙げている。この3つ目の提案は言うまでもなく、全米を巻き込んで議論となっている重大な争点だ。「批判的人種理論(Critical Race Theory)」という旗印の下で歴史教育を誤って解釈している親や教師が、アメリカでひた隠しにされてきた数々の歴史を学校で教えることは許されないと非難している。
本書は、人間の持つ逞しさを称えて締めくくられている。人間は、ささやかな行為に意味を見出し、平凡さに美しさを持たせ、1つの種から豊かな庭を育てることができると説く。1人の人間が別の誰かのために存在すれば、隣人はコミュニティに、コミュニティは都市に、都市は国家に、国家は大陸に、大陸は世界に発展していく。
人を思いやる行動はコレクティブな共感へと増幅し、やがて、ベンジャミンが提唱する「世界の再構築」が動き始め、ありとあらゆる支援が意味を持つようになる。「人から人に正義を拡散していくことは、暗黒世界を救うことでも理想郷をつくることでもなく、『私たちみんなの社会』をつくることだ」。
新型コロナウイルスの感染拡大によってこれまでとは違う現実が生まれ、ソーシャルディスタンスやマスクの着用がニューノーマルとなった。コロナ禍で失われた命を弔うことができず、別れを告げることも、もう一度抱きしめることも、社会的にも宗教的にも死者を送り出すことが叶わないいま、世界はますます孤立化しているように思える。そんなときだからこそ、「私たちみんな」であることを忘れてはならない。本書は、パンデミックに苦悩する世界、人種と肌の色による差別に染まったアメリカにおける「不変の美しさ、負けを認めない喜び」を謳った1冊である。
【翻訳】遠藤康子
【原題】Cultivating, Seeding, and Planting a Better World(Stanford Social Innovation Review Fall 2022)
Copyright©2022 by Leland Stanford Jr. University All Rights Reserved.


