他者とつながる場があるだけではコラボレーションは生まれない。当事者の不安克服に焦点を当てた3本柱のアプローチを紹介する。
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 04 コレクティブ・インパクトの新潮流と社会実装』より転載したものです。
アダム・セス・レビン
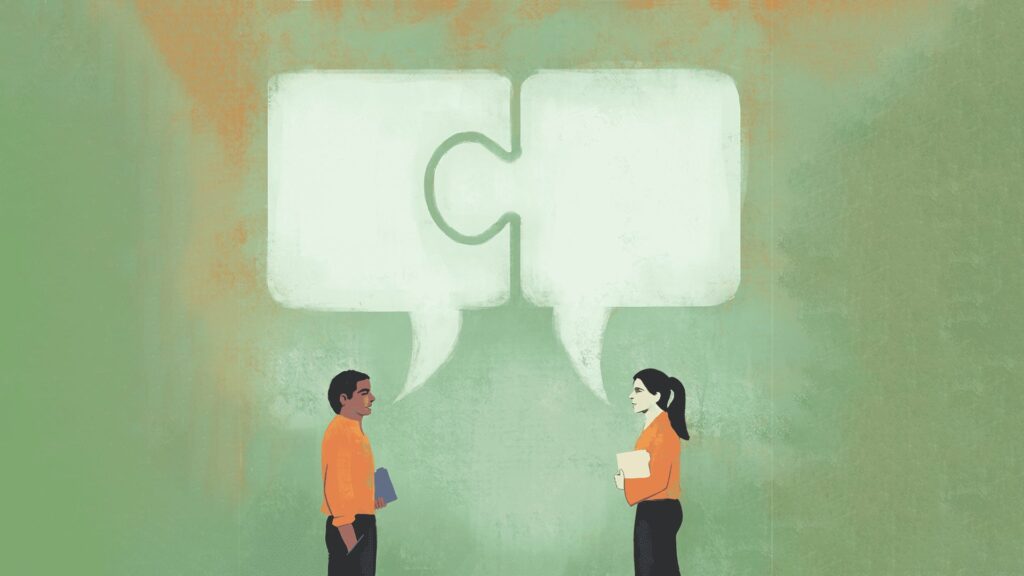
2017年に私はドン・グリーン、ジェイク・バウワーズとともにリサーチ・フォー・インパクト(research4impact, r4i)を立ち上げた。これは、複雑な社会課題の解決を目指す研究者、実践者、政策立案者をつなぎ交流と情報交換を可能にするリンクトインのようなオンラインプラットフォームで、ユーザーは自分のプロフィールを登録して他のユーザーとやりとりができる。
共同設立者の私たちは、以前から研究者、実践者、政策立案者をつなぐ活動をしており、それに大きな意義を見出していた。なぜなら、異なるネットワークに属する人たちがそれぞれの知見や現場で得た学びを持ち寄れば、気候変動対策や貧困撲滅、教育改善、投票率向上など、お互いに危機感を抱いている問題の理解や解決につながると感じていたからだ。にもかかわらず、相互のつながりは非常に弱かった。
そうした状況下で、私たちのもとには多種多様なネットワークに属する人たちから、「知見を広げて共同で研究できるような、新しい協力関係を築くにはどうすればいいのか」という声が続々と寄せられ、それに応えるべくr4iを立ち上げた。
最初の10カ月間で、388人のユーザーが詳細なプロフィールを作成した。彼らは手間ひまかけて自己紹介文や活動テーマ、関心の高いトピックを書き込み、写真を掲載した人も多かった。誰もが、新しいボランティア活動に参加する際にありがちな壁を乗り越えて飛び込んできてくれた。ユーザーは見知らぬ者同士でありながら、r4iという場が提供する価値を活かそうと、自らの能力と貢献意欲を示した。この様子を見て成功したも同然と喜んだ私たちは、これから新しいコラボレーションが続々生まれることを疑わなかった。
ところが、その期待は裏切られた。立ち上げからの10カ月間で、r4iを介して他のユーザーに働きかけたのは7人にすぎなかったのだ。
のちに社内でr4i 1.0と呼ぶようになった当時のプラットフォーム形態の失敗から、私たちは重要な教訓を得た。考え方の異なる人たちが新たな関係を育むうえで必要なのは、能力や意欲や機会だけではなく、他にも不可欠な要素があったということだ。私なりの言葉で言わせてもらうと、それは「リレーショナリティ(関係性への信頼)」だ。つまり、「相手はこちらの望む関係性を理解してつながろうとしてくれるはずだ」、そして「自分も相手とうまく関係を築けるはずだ」という確信が必要だったのだ。
このような考え方は、「相手との関係においては、まず関係を築くことが大切だ」という同語反復のように思えるかもしれない。しかし重要なポイントは、人が見知らぬ他人と交流する際に抱く不安を考慮する、という点である。
この不安が大きいと、私たちは相手との関係をどう構築していけばいいのかわからなくなってしまう。協力関係をどう始めればいいのか、果たして相手はそれに応じてくれるのか、と尻込みするわけだ。人は関係のつくり方がわからなければ、そもそも他者と接することすら諦めてしまうものだ。
つまり、リレーショナリティを明確に持てないままでは、他人は他人のままということだ。だからこそ、リレーショナリティとは何か、なぜ人は関係性について不安を抱きがちなのかについて理解を深めていけば、r4iのユーザーたちがその学びを活かして新たな関係を構築できるようになるのではないか、と私たちは考えた。
新しい関係への不安
r4i 1.0 が失敗した理由を探ろうと、プロフィールを作成しながらも他のユーザーへのコンタクトはしなかった数十人に連絡を取り、躊躇した理由をたずねた。
問い合わせに応じてくれたユーザーは全員、r4iを通じて他者とつながることができる利点を認めた一方で、相手とどう関わればいいのかわからないと感じていた。あれこれ思い悩み、連絡を取ろうと考えつつも躊躇してしまったのだという。相手は本気で自分と協力したいと思うだろうか。自分の知識や経験を評価してくれるだろうか。こちらが相手の知識や経験を評価していることを信じてくれるだろうか。どうやって協力を切り出せばいいのか。どんな言葉遣いが適切あるいは不適切なのか。相手はこちらの時間を尊重してくれるだろうか。相手はこちらに何を期待するだろうか―。このような懸念によって関係性への信頼を持つことができず、積極的に他のメンバーと関わろうとする意欲が削がれていた。
ここで出てきた「期待」という表現には何らかのヒントがありそうだ。「期待」という言葉は「新たな協力関係を求める理由は人によってさまざまである」ということを意味している。
なかには、あくまでも自分が意思決定できる分野にとどまりながら、自分の知見を広げたり特定の問題への理解を深めたりしたいという人もいるだろう。たとえば、環境保護活動家と気候研究者は、現場での洪水発生状況と洪水の全国的な傾向に関する研究について、情報交換する機会を求めているかもしれない。その場合、ごく簡単なやりとりだけで何かが始まるかもしれない。
一方で、具体的な目的を伴った協力関係の場合もある。何かを共同で所有したり、意思決定の権限や説明責任などを伴うような関係だ。
たとえば、近隣住民による合同清掃活動、公衆衛生当局と地域のリーダーによる予防接種の推進活動、研究者と投票推進活動家による投票率向上施策の調査などが考えられる。
ゆるやかな協力関係でも、より本格的な協力関係でも、当事者たちの期待がそもそも不明瞭であれば、何の進展も見られずに終わるだろう。
3本柱のアプローチ
では、こうした膠着状態を打破するにはどうすればいいのか。本稿では3本柱のアプローチを提案し
たい。
- リレーショナリティとその重要性について認識を高める
- 協力相手を探す人たちが、その「理由」だけではなく、「どんな協力関係を築きたいのか」を明確に伝えるように促す
- 当事者のリレーショナリティへの不安を軽減できるようなリーダーや組織を育成して支援する
1本目の柱である「リレーショナリティとその重要性について認識を高める」ためには、はっきりと言葉で表現することが大切だ。たとえば、私はr4iの責任者として、「社会課題の解決を目指す新たな協力関係を築こうとするときに、ベストな方法とは何か」という質問をよく受ける。
このような質問をしてくる人は、自分が協力関係を構築したい「理由」も添えることが多い。「地元で洪水が多発していますが私たちには洪水への知見がないので、その専門家に相談したいんです」というように。
こうした場合、私はいつも、リレーショナリティの重要性を強調しながら回答するようにしている。たとえば「あなたにとって必要なのは、ただ洪水に詳しいだけではなく、その知見の共有に意欲的で、あなたからも提供する情報や専門知識や現場での経験に価値があると思ってくれるような人なんですよ」と。
こう回答すると、いつも怪訝な顔をされる。自分に必要なものを説明するとき、普通はこのような言い方をしないからだろう。
2本目の柱は、「協力相手を探す人たちが、その『理由』だけではなく、『どんな協力関係を築きたいのか』を明確に伝えるように促す」である。誰かと協力したい人は関係構築を目的としているのだから、そんなことは当然だと思うかもしれない。とはいえ、前述した通り、私たちは他者とのコミュニケーションにおいてリレーショナリティを見落としている。その一因は、典型的な社会的認知の構造にある。たとえば対人行動を評価する際、私たちは「自分は持っている知識を効果的に伝えることができているか」といった「(主に話し手の)能力」を意識することが多く、「こちらが先方の専門知識に価値を感じていることが伝わっているか」といった「相手のニーズを汲み取れているかどうか」には無頓着になる傾向がある。言い方を変えれば、私たちは必ずしも、自分が相手とどのように協力しようとしているかを明確に示しているとは限らないのだ。しかし、意識してリレーショナリティを巡る不安の解消を目指せば、新たな協力関係が生まれやすくなる。
ここで、私が2019年に大手の市民団体と共同実施したフィールド調査で得られた結果を紹介したい。アメリカの各地にある同団体支部のリーダー456人にメールを送り、彼らが現場で直面している課題に役立つ知見を共有してくれる、ボランティア研究の専門家を紹介すると提案した。
無作為で抽出した一部の受信者には、専門家を紹介する「理由」に焦点を置いた基本メッセージだけが届くようにした(多くの支部リーダーが熱心なボランティアを集めるのに苦労している状況への理解を示し、エビデンスに基づいたボランティアの意欲の高め方について専門家と意見交換できる場を設けると提案した)。
それ以外の受信者には、上記の基本メッセージに加え、現場のリーダーたちとのやりとりにおいて専門家がどのように取り組もうとしているかという、リレーショナリティに関する文面を盛り込んだ。たとえば、専門家側は支部リーダーが多忙であることを理解してできるだけ効率的に知識を伝えようとしている点や、支部リーダーの専門性を高く評価し、その活動と組織に大いに関心を持っている点などを盛り込んだ。
その結果、後者のメールへの回答率は、基本メッセージだけのメールの2倍以上となり、専門家とリーダーとのあいだに生まれた協力関係も倍増した。さらに、熱心なボランティアの新規獲得にもつながった。
3本目の柱は、「当時者のリレーショナリティへの不安を軽減できるようなリーダーや組織を育成して支援する」である。仲介役となるマッチメイキング事業者や組織のリーダーたち、あるいはファシリテーターなどがこの役割を担えるだろう。これは既にr4iの事業で立証されている。r4i 1.0 の失敗を受けてユーザーたちに話を聞いたあと、2018年に私たちはより実践的なマッチメイキング手法の開発に取り組み始めた。それを活かして私たちの事業はr4i 2.0 に発展した。
r4i 2.0 では、エビデンスに基づいた独自の手法「マッチメイキングを通じたリサーチインパクト(Research Impact Through Matchmaking, RITM)」を開発した。 これは、互いの共通点を特定してリレーショナリティを育む仕組みを通じて、多様なユーザーのなかから社会課題について共通の関心を持つ人たちをマッチングするものだ。RITMでは、いくつかのテクニックを使っている。
たとえば、ユーザーの業務的知識、専門知識、実務経験などを双方に伝える「役割の割り当て」を行う。
また、「他者との交流はお互いにとって有益な学習機会である」と表現したり(そうすることで誰もが協力関係の構築に前向きなマインドセットを持てるようになる)、ユーザーの協力関係への期待値を誰もが理解できるように、その人の目的を簡潔に言い換えたりする取り組みを行った。
さらにr4i 2.0 では、セクター横断のコラボレーションに不慣れな人々に前向きな関心を抱いてもらうための働きかけも行っている。たとえば、実践者と地域の政策立案者を集めて、彼らのどんな活動に科学的な研究が役立ちそうかを共有してもらい、ニーズに合いそうな研究者を紹介したいと提案した。
こうした、個々の課題に応じたマッチメイキングを提案する方法は奏功し、2018年以降、r4i 2.0 では308 件の新たな協力関係が生まれている。
本稿で紹介した3本の柱で構成されるこのアプローチは、協力関係の構築を妨げるものとして克服すべき「リレーショナリティへの不安」の解消に焦点を絞った方法である。このアプローチによって、誰かと協力しようとする人が直面する核心的な問題に、当事者目線で意識を向けられるようになる。この方法論は、社会が直面する差し迫った問題の解決に欠かせない「つながりの文化」を強化するのに役立つだろう。
【翻訳】遠藤康子
【原題】How to Foster Collaborative Relationships(Stanford Social Innovation Review Summer 2022)
Copyright©2022 by Leland Stanford Jr. University All Rights Reserved.


