手続き的正義の重要性
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 03 科学技術とインクルージョン』のシリーズ「科学テクノロジーと社会をめぐる『問い』」より転載したものです。
江守正多 Seita Emori
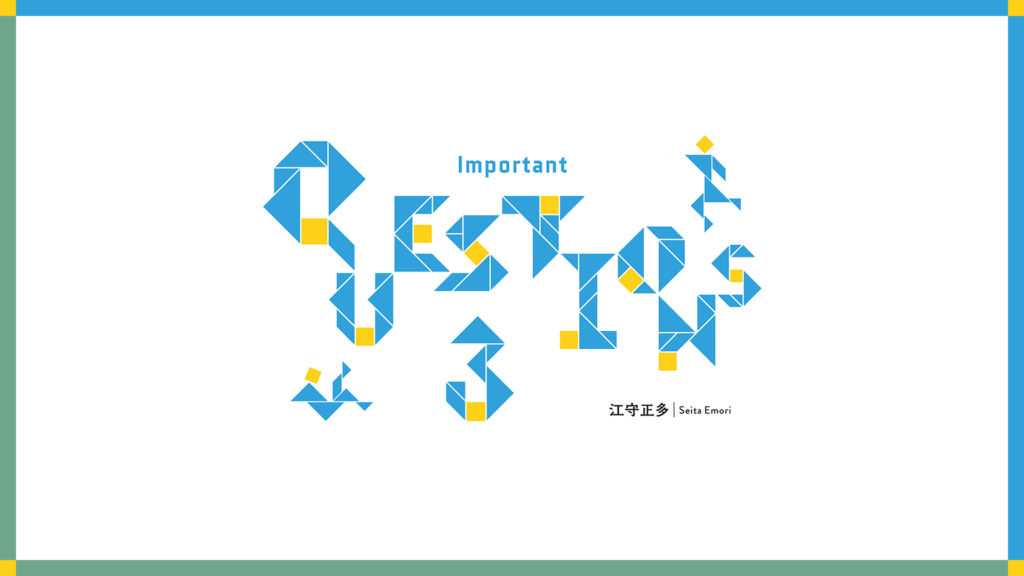
エネルギー・環境分野における参加型政策決定
気候変動問題の解決に向け、どのような脱炭素技術を選択するか。どのようなエネルギー政策を選択するか。こうした「選択」をめぐる議論に時に筆者自身も参加しながら、「誰がどのようにその決定をすべきか」を考え続けてきた。
象徴的な出来事を示したい。東日本大震災・福島第一原子力発電所事故から1年後の2012年、当時の民主党政権は2010年に自らで決定した「第3次エネルギー基本計画」の見直しに向けた準備を進めた。それまで経済産業省と資源エネルギー庁が主導していたエネルギー基本計画の策定に、一般の人たちにも加わって意見表明してもらうという趣旨で「エネルギー・環境の選択肢に関する意見聴取会」が全国11カ所で実施された。 2030年のエネルギー・環境に関して政府のエネルギー・環境会議が取りまとめた3つの選択肢に対し、「討論型世論調査」も実施された。
上記3つの選択肢について、20歳以上の男女6800人を無作為抽出して世論調査を実施、そのうち286人が2日にわたる討論に参加して「エネルギー・環境とその判断基準を考える」をテーマとした議論やエネルギー・環境問題の専門家と意見交換を行った。
2014年4月に「第4次エネルギー基本計画」が発表されたときには民主党は既に政権の座から離れていたが、エネルギー・環境に関する政策決定を、インクルーシブな参加型手続きを踏んで行った点は画期的だったと評価している。参加型政策決定の意義の1つは、参加者たちにオーナーシップ、つまり当事者意識が生じることだ。自分の意見がその後の政策に反映されるかどうかにかかわらず、参加者は議論に参加したテーマには興味を持ち続けるだろう。もう1つの意義は、政策に新たな視点が入りうることだ。専門家や関係者だけの議論では見落とされてしまう視点が採り入れられるという期待がある。そして、感覚的に答えがちな単なる世論調査と違い、熟議を経た意見を聞くことに重要な意味がある。
最近始まった「気候市民会議」も参加型政策決定の実践事例といえる。脱炭素社会をどのように実現すべきかなどをテーマに、無作為選出された一般の人たちが議論し、結果を国や自治体の政策に生かしていく取り組みだ。年齢や男女比などを母集団の比率と同様になるようサンプリングし、熟議を経て政策提案につなげる。フランスやイギリスは2019年に政府・議会レベルで気候市民会議を発足させ、2020年に実施した。日本でも積極的な自治体にまだ限られてはいるが、各地で開催されている。札幌市では2020年11月・12月に「気候市民会議さっぽろ2020」が行われ、市民から選出された20人が「札幌は、脱炭素社会への転換をどのように実現すべきか」をテーマに議論し、脱炭素社会のビジョンや実現時期など計70項目について意見を投票した。結果は市の気候変動対策の行動計画などに活用されている。同様の取り組みは川崎市(神奈川県)、所沢市(埼玉県)、武蔵野市(東京都)でも行われている。
再生可能エネルギー施設にまつわる懸念
参加型という点では、従来手法として行政が政策実施前に案を公表して意見を募るパブリックコメントや、政治家・閣僚たちが一般の人たちと対話型集会を行うタウンミーティングも知られている。だが、開催後に案が改まったような事例はほぼなく、行政側が政策を説明し、反対者たちに不満を述べさせるガス抜きの場と化しているように見える。
市民が包摂されるべきは政策決定の場だけではない。いま、各地で再生可能エネルギー施設の乱開発への反対運動が起きている。背景にあるのは脱炭素という「大義名分」のもとに乱開発が進むことへの懸念である。その地にゆかりのない企業や外国資本が、山地などを安く購入または借用し、樹木を伐採して整地し、ソーラーパネルを敷き詰めていく。その結果、景観破壊、自然環境破壊、土砂崩れの危険といった問題が実際に起きている。再エネ関連施設の近隣住民が、施設建設の決定プロセスの外側に置かれてしまっていることが、こうした状況を招いている要因の1つといえる。
科学者は倫理的課題の議論に尻込みしがち
新たな技術を社会に実装していく段階では、その技術の受容や利用をめぐって生じうる倫理的・法的・社会的課題(ELSI:Ethical, Legal and Social Implications / Issues)を議論しておく必要がある。
脱炭素技術の選択や普及についてもELSIの観点で議論できないかと考え、科学技術振興機構(JST)のプログラムで「脱炭素化技術の日本での開発/普及推進戦略におけるELSIの確立」という課題に取り組んでいる。ここでも鍵となる問いは「社会の重要な技術的戦略や推進戦略を誰が決めるべきか」だ。従来は、専門家・官僚・関連産業界団体・関連自治体の首長といった狭いサークルで議論と意思決定がされてきたが、その議論で参照される評価基準は主にコストや供給安定性といった定量的なもので、倫理・社会、公平性・分配、文化的価値といった数値で測りにくい課題は、さほど議論されないまま方針や戦略が決定されてきたように思う。
かつて日本原子力研究開発機構(JAEA)から、原子力分野の将来ビジョンをつくりたいので検討に加わってほしいと要請され、迷った末に参加することにした。最初の会合でまず伝えたのは「前向きなビジョンを描きたいのであれば、倫理的課題に向き合う必要がある」ということだった。原子力をめぐる倫理的課題には、たとえば高レベル放射性廃棄物最終処分の問題がある。現代の人間が出した廃棄物を後世の人間が10万年にわたり管理しなければならない。
私のこの発言に対する反応は賛否両論だった。「原子力の技術者が嫌がる」「技術者が考えることではない」と否定的な人もいれば、「こういう議論はするべき」と肯定的な人もいた。最終的に、ビジョンには「原子力をめぐるELSIへの対応」といった語句が盛り込まれた。
日本の科学者や技術開発者はELSI、特に倫理的な課題の議論に消極的だと感じる。よくある反論は「倫理的な価値は人により異なるから議論の土台に乗るものではない」「客観的な指標で検討できる話に絞るべきだ」といったものである。もちろん科学者や技術開発者には、倫理的な議論をするだけでなく、政策的な意思決定に資する科学的根拠を示すという役割もある。現に科学者たちが執筆する「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」の評価報告書を根拠に「パリ協定」のような国際的枠組みが採択されている。
しかし、科学者や技術開発者の判断や発言に主観やバイアスは入りうる。たとえば、科学者が気候変動リスクについて語るとき、「可能性は低いが大きな変化が起きうる」といった話をどれだけ強調するかは、その発言者の価値判断に左右される。いくら科学的な議論に徹しようとしても、分けられない部分はかならず出てくるのだ。
だが一方で、科学の客観性を疑うような言い方をすると「組織的な温暖化懐疑論・否定論」 がエスカレートするおそれもある。社会学者の研究によれば、こうした懐疑論・否定論の多くは化石燃料企業やその関連組織を中心に広められている。これは非常に厄介な問題で、組織的な懐疑論・否定論に対抗しようとするあまり、メディアが温暖化のメカニズムを過度に単純化して伝えるなどの弊害も生じている。
「手続き的正義」が確保されているか
国際社会では、脱炭素化を進めていくという大きな方向性は共有できているとはいえ、2050年の脱炭素達成までの時間は限られている。脱炭素化を進めるという大きな合意を前提に、個々の政策とその実施については、さまざまなステークホルダーに配慮しながら速やかに進めていかなければならない。
このとき重要となるのが、「手続き的正義」を確保したうえで対策を立て、速やかに実施していくことだ。手続き的正義とは、決定に至るプロセスの公正さを指す概念である。決定されたことが自分の意見と違っても、決定に至る過程が納得できるものであれば、その決定を受け容れやすくなる。決定されたことの内容自体に正義を求める「実体的正義」の概念とは対極的だ。
手続き的正義の重要性を象徴している事例の1つが、2018年から19年にかけてフランスで起きた「黄色いベスト運動」である。燃料費が高騰して国民の不満が高まるなか、2017年5月に誕生したマクロン政権は、地球温暖化対策と財政赤字削減のためとして燃料税の増税実施を決定。
その結果、フランス全土で大規模なデモが起き、一部は暴動化した。結局燃料税の増税は予算案から削除され、事態収拾のためマクロン大統領は税制、民主主義、環境、移民問題などをテーマとする「国民大討論」を2カ月余りかけて全国で行った。あらかじめ国民の声に耳を傾けたうえで燃料税引き上げを撤回していたなら、死傷者も出すようなデモにはつながらなかったかもしれない。
より最近では、オランダの家畜削減政策の例もある。2022年6月、オランダ政府は2030年までに家畜からの窒素排出量を半減させる計画の一環として、家畜数を3割減らした農家の事業を買い取る方針を発表し、これに対して農家や農業団体が強く反発している。政府の姿勢は農家には一方的な「ルールの押し付け」に見えるのだろう。
脱炭素という課題に対しては、将来にわたって大きな影響をもたらす政策決定をきわめて厳しい時間的制約のなかで行っていくことが求められている。そこに多様なステークホルダーの意見を反映させ、手続き的正義を確保しつつ、実効性のある決定を打ち出していけるのかが問われている。
【構成】漆原次郎


