当事者の希望をみんなで叶える
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 05 コミュニティの声を聞く。』のシリーズ「コミュニティの創造と再生をめぐる『問い』」より転載したものです。
徳田雄人|Takehito Tokuda
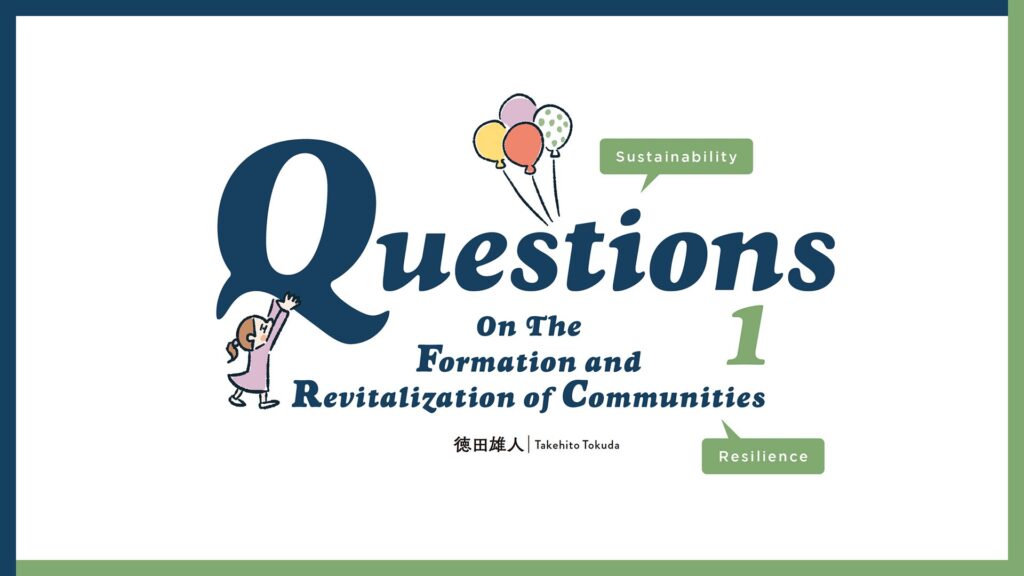
「認知症の人」に対する固定化されたイメージ
私が認知症をテーマに活動を始めたのは、NHKに勤めていたときに番組ディレクターとして認知症を取材したことがきっかけである。
初めて認知症の方に取材するにあたって、医学系の書籍を5冊ほど読んでから行ったのを覚えている。認知症と聞くと「触れてはいけないこと」といったバリアを感じる人は少なくないのではないだろうか。私も同じで、認知症の方とコミュニケーションをとるためには医学的な知識が必要に違いないと身構えていた。しかし、実際に会ってみるとそんな準備は必要なかった。わからないことがあれば、本人に聞けばよかったのだ。
認知症の番組では、新薬や介護に関する情報を紹介することがほとんどだ。それは一般的に認知症が医療やケアの問題として捉えられているからである。しかし、そこに私はモヤモヤとしたものを感じていた。実際に認知症当事者の方やご家族に話を聞くと、医療やケアも大事ではあるものの、むしろ「認知症の人」に対して多くの人が持っているイメージから引き起こされる生活上の課題がとても大きいと思ったからだ。
認知症の人に対する典型的なイメージとは、「何もわからなくなる」「単一の行動パターンがある」「多くが介護施設に暮らしている」という、症状の最も進んだ状態を捉えたものである。実際に認知症と診断されてただちにこのような状態になることはまずない。
こうした偏ったイメージができたのは、メディアが重度の認知症の人や介護の大変さばかりを取り上げてきたことにも一因がある。認知症と診断されてもちょっとした工夫で楽しく暮らしているという人の話はあまり取り上げられない。最近では、認知症当事者が発信する機会も増えてきているが、いまだに介護の苦労話だけが再生産される傾向は変わっていない。
こうした話からは浮かび上がってこない認知症の人の生活における実際のニーズとは、たとえば次のようなものだ。以前に取材させていただいた千葉県に住む優子さんは50歳のときに認知症と診断されて退職、夫が在宅で働きながら介護をしていた。優子さんは定期的にスポーツクラブのプールに通っていたが、認知症と診断されたことを伝えると、最初クラブ側は戸惑いを示した。
しかし、実際に困るのは更衣室で自分のロッカーの場所がわからなくなることだけだった。夫も女性の更衣室までは付き添えない。そのことをクラブと共有したところ、必要に応じて職員がサポートをしてくれることになり、優子さんは継続してプールを使うことができた。このような臨機応変の支援が得られるかどうかで、認知症と診断されてからの暮らしの質は大きく変わる。スポーツクラブが利用できないというような困りごとは、医学では解決できない。
「ともに暮らす」を前提に地域や社会を設計する
さまざまな現場を取材して、私は「認知症の症状が同じ程度でも住む場所や環境によって生活の質が大きく違うのはなぜか」という問題意識を持つようになった。
この問題意識に正面から取り組むため、私はNHKを退職した。目指したのは認知症の人を含めた誰もが暮らしやすい地域づくりだ。
どのようなアプローチがいいのか試行錯誤していた時期に出合ったのが、イギリスで広がっていた「認知症フレンドリーコミュニティ」という、認知症による課題をコミュニティモデルで解決しようという考え方だった。英国アルツハイマー病協会の定義によれば「認知症フレンドリーコミュニティとは、認知症の人が高い意欲を持ち、自信を感じ、意味があると思える活動に貢献、参加できるとわかっている、そうした環境」である。根底にあるのは、障害が個人の問題ではなく、社会全体の設計によってつくり出されるとする「障害の社会モデル」という概念だ。このモデルの視点から見ると、認知症の人の直面する困難は、認知機能の低下によるものだけでなく、社会環境がその人のニーズに適切に対応していないことにも原因がある。
「認知症フレンドリーコミュニティ」は、認知症によって引き起こされる社会課題に個別対応していく「認知症対処社会」の対極にあるものだ。既に日本では認知症の人が600万人以上いると推計され、世界全体でも2050年までに1 億人を突破すると予測されている。認知症の人がごく少数で特別だった時代の社会から、高齢化が進んで認知症の人が「普通にいる」社会へと移行するなかで、社会やコミュニティのほうが変わっていくのは必然の流れでもあるだろう。
取り組みが進んでいるイギリスでは、たとえば大手スーパーマーケットのチェーン店が定期的に「スローショッピングの日」を設けている。その日は店内BGMを切って静かに買い物ができる環境をつくり、レジで気兼ねなく時間をかけて支払いができる「スローレーン」を設けていた。
また、プリマス市の市営バスでは、降りるバス停がわからなくならないようにバス停名を書いたカードを運転手に見せて、到着したときに声をかけてもらう工夫が行われていた。こうしたアイデアは認知症の人たちに限らず利用されている。このように、認知症の人たちがともに暮らすことを前提に、社会や地域を設計していこうという発想が「認知症フレンドリーコミュニティ」の基本にある。
認知症当事者の「私」を主語に 目指したい社会を描く
現在、私は東京都町田市、静岡県富士宮市、福島県いわき市、岡山県岡山市、愛知県名古屋市北区などで認知症フレンドリーコミュニティを目指す活動のお手伝いをしている。
地域によって活動の中身は異なるが、ベースとなるのは「認知症の当事者と家族」「解決するリソースを持っているかもしれない民間企業やグループ」「両者の間に入って問いを深める行政」という立場の違う三者による協働である。
たとえば東京都町田市では、2015年から取り組みを開始し、まず市役所、医療福祉関係者、NPO、認知症の人とその家族、そしてコンビニやコーヒーストアチェーン、郵便局など地域を構成する企業も参加するまちづくりワークショップを開催した。そこで出てきた意見をもとに「まちだアイ・ステートメント」を発表した。これはイギリスでの取り組みを参考にしたもので、「認知症の当事者としての私」を主語に、目指したい社会について言語化したものだ。
たとえば「私は、支援が必要なときに、地域の人からさりげなく助けてもらうことができる」「私は、趣味や長年の習慣を続けている」「私は、地域や自治体に対して自分の経験を語ったり、地域への提言をする機会がある」といったステートメントが含まれている。
「まちだアイ・ステートメント」をまとめる過程でできた関係性から、町田市ではさまざまなプロジェクトが生まれてきた。そのなかには、コーヒーチェーン店で定期的に開催される認知症カフェ、デイサービスと自動車会社が協力して始めた認知症の方たちによる洗車の仕事づくりなどがある。また、行政と当事者グループが協力して地域で放棄された竹林の整備活動も行っており、タケノコや竹炭の販売は認知症当事者の収入源になっている。
課題や関係をひらくことで「別ルート」の生活が見えてくる
認知症と診断された場合のこれまでの標準的なライフステージを考えてみよう。多くの人が仕事を退職して自宅で家族と過ごす。やがてデイサービスに週数回通うようになる。そのうちに社会性がなくなり、ADL(日常生活動作)も低下していくと、介護施設に入所する。そこでは一日中TVを見て過ごし、活動量も食欲も落ちて、最終的に病院に入るというパターンだ。
しかし、同じ人が診断を受けた後も働く場などにつながっていればどうだろうか。地域のなかで役割ができ、収入も得て、仲間もいるという、「別ルート」を進むこともありえるかもしれない。
後者のようなルートを簡単に選べない理由の1つに家族との関係がある。
認知症の当事者と家族の利害はときに対立する。たとえば本人はできる限り外出もしてこれまで通りの暮らしをしたいと望んでいても、家族は何かあると心配だから家にいてほしいと考えてしまいがちだ。
このジレンマを解決できるのがコミュニティだ。地域に認知症であることを理解して対応してくれる交通機関があり、「スローショッピング」ができるスーパーがあれば、家族も「あそこなら1人で買い物に行っても大丈夫」と思えるかもしれない。生活の質を高めるためには、そうした社会的インフラを整えるだけでなく、その人が活躍できる場所や仲間となる人たちがいることも重要だ。
そしてなにより、当事者が自分自身の偏見から解放され、認知症になっても生き生きと暮らしていくことができるのだ、というイメージを持てるような、社会全体の価値観の変化も必要である。
社会インフラとして展開していくための課題
ここまで「認知症フレンドリーコミュニティ」の可能性について示してきたが、最後にいま私たちが感じている壁についても共有しておきたいと思う。
当初、私は、認知症の人たちが地域で質の高い日常生活・社会生活を送るために、いろいろなセクターの人たちが当事者たちとつながる「種まき」をすれば、そこから自然と解決策の「芽」が出るだろうと思っていた。しかし、それはいささか楽観的すぎる考えだったかもしれないといまは感じている。
たとえば、町田市でのコーヒーチェーン店と協働した認知症カフェのような取り組みを、違う地域の人たちが取り入れようとして継続できなかったケースがあった。なぜ続かなかったのか。それは、そこに至るまでのプロセスが違うからである。多くの人は「認知症カフェ」という目に見える成果に注目しがちだが、協働の際に重要なのは「何のためにやるのか」という理念やゴールを共有できていることである。
町田市の場合は、ワークショップを重ねて「まちだアイ・ステートメント」という共通のゴールを設定することができたが、そうした理念やゴールが共有できていないと、プロセスのなかで齟齬が生まれ、なんとかかたちにしたところで持続しない。
私たちの事業では、立場の異なる三者を集めてコミュニティづくりを進めるプロセスの研修も行っているが、そのプロセスがどんな地域でも再現できるわけではない。そもそも私たちのところに声がかかるのは、地域内に協働の必要性を感じている人たちがいるからであり、そういう意味では基礎体力がある地域だ。基礎体力や下地がない地域でもできることはないだろうか。「認知症フレンドリー社会を生活のインフラとして、全国に展開していくには何が必要なのか」という問いの答えを、模索し続けているところである。
【構成】中村未絵


