「個才」を解き放つ新しい学び方
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 03 科学技術とインクルージョン』のシリーズ「科学テクノロジーと社会をめぐる『問い』」より転載したものです。
福本理恵 Rie Fukumoto
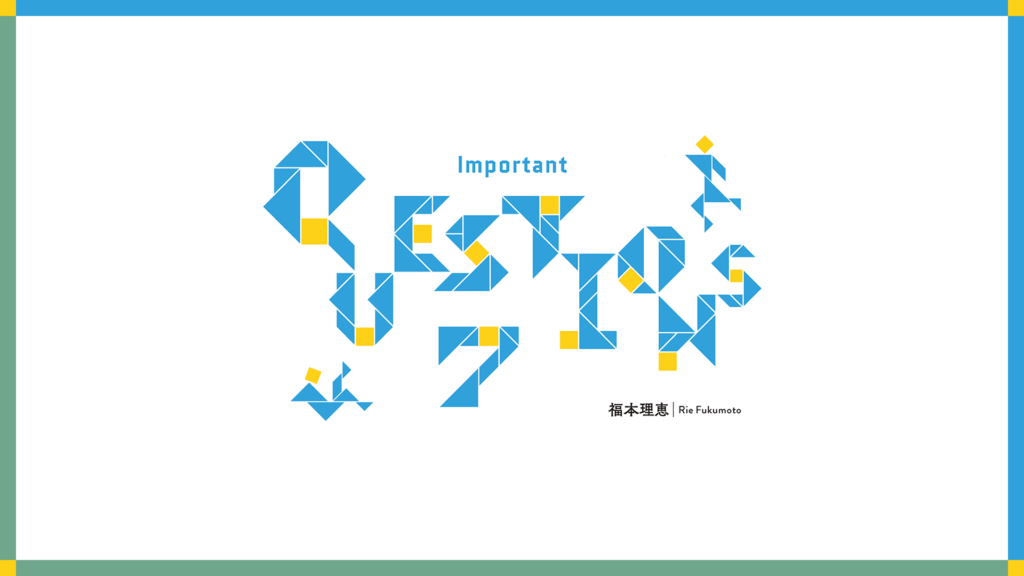
データを大量に集めれば「人間」はわかるのか
日常生活のなかで「共感」という感覚を伴うとき、人間の心の動きはとても複雑だ。その複雑なものを科学的に証明するには、数字での裏付けがなければならない。しかし、緻密な実験をすればするほど、私の中に葛藤が芽生えた。そもそも共感性とは、数字で測れるものなのか、と。
私は大学院時代、人間の知性や心の領域について研究していた。たとえば、人間関係を構築する土台となる母親と子どもの「共感性」はどう育まれるのか。その仕組みを明らかすることが研究テーマだった。
共感性の神経基盤には、ミラーニューロンという模倣(非言語のコミュニケーション)の神経基盤が関係している。そして、ミラーニューロンが位置する脳の領域は、「ブローカ野」という言語中枢を司る領域でもある。人間の進化の過程から考えると、共感する際には言語の前に非言語でのコミュニケーションが必要だったのではないかという仮説を立て、実験では、人の表情が変わる動画や、指を動かす動作を見せて、NIRS(近赤外分光法)で計測。1/1000 秒刻みで蓄積されていく膨大なデータをもとに、脳の賦活状態を科学的に分析していた。
しかし、私の実験で得られたデータは、あくまで人間の一部の要素にすぎない。これらの要素を統合しても、人間の知性や心の動きの全体像を語ることはできず、こぼれ落ちるものが生まれてしまうのだ。「私の研究はどのようにして人々の日常の暮らしを豊かにし、社会に接続できるのだろう」。その「解」がわからなくなった。
科学技術の定義に基づく手法を駆使すると、こぼれ落ちるものが必ず出てくる。データを大量に集め、統計的な処理をすることは、個人間の差異や、個々人が持つ才能(個才)を排除することでもあるからだ。研究のなかで矛盾を感じた私は、「科学は『分断』を越えられるのか?」という問いを抱き続けている。
曖昧さを受け入れることが、分断を埋めるカギ
心理学の手法だけでは、目の前にいる人たちを救えないのではないか。そんなジレンマを感じ、より目の前の人にダイレクトに働きかけられる「食」の領域に足を踏み入れた。「種から育てる子ども料理教室」や、農と食から教科を学ぶ「Life Seed Labo」を立ち上げるなど、「食」領域で学びや実践を続けるなかで気づいたのは、「食」は科学技術を発展させてきたきっかけになっているということだ。
人は食事をしなければ死んでしまう。食事をつくり、誰かと食事をともにすることは、命を明日へつなぎ心身を整えることにもつながる。「火」の使用は人間の大きな発明の1つだ。さまざまな調理法も、科学技術や歴史や文化も、「食」とともに発展してきた。「食」はあらゆる学びの原点であり、人間の生きる根底に「食」がある。
2014年、東京大学先端科学技術研究センターで、プロジェクトリーダーとして「異才発掘プロジェクトROCKET」の立ち上げに携わった。ROCKETとは、「食」も含めて、いろいろな分野にちらばっていた多様な知の領域を統合する学びのプログラムである。私たちが目指したのは、人工知能やロボットに代替されないよう、子どもを社会の枠から解放することだった。当時、日本における不登校の子どもたちは約11万人。特異な才能を持ちながらも学校教育になじめない子どもたちが、自由に学べる居場所がないという課題がこのプロジェクトの背景にある。学校という枠にとらわれず、子どもたちの「好き」を尊重する教育ができないかという試みだ。
最近、「ギフテッド」や発達障害、不登校という言葉が教育業界でよく話題になる。しかし、安易に「ギフテッド」という言葉を使えば、ギフテッドではない子どもが排除されてしまう。同時に、ギフテッドの子どもが排除されてしまうこともある。言葉によって、「線引き」が生まれ、分断という予期せぬ副作用が出てくる。これは決して他人事ではなく、ROCKETで「異才」という言葉を使い、いまは「個才」を提唱している私自身が心にとめておかなければならないことだ。
これまで科学技術は曖昧さを排除することで発展してきたが、その枠を外し、これまでに生み出してしまった分断を埋めていくフェーズにきているのかもしれない。私がたどってきた道筋も、その分断を越えるための試行錯誤の連続だった。曖昧さを排除しないことでかなえられるインクルーシブなかたちがあるのではないかと私は思う。そこに科学技術が生んだ「分断」を乗り越えられる可能性が見つけられないだろうか。
科学の枠組みからこぼれ落ちるものと、いかに向き合うか
ROCKETで痛感したのは、子どもたちの知性や特徴を科学的に定義することの限界だった。たとえば、繊細な色彩感覚を持っていて、美しいウェブサイトをつくっているにもかかわらず、自分の中では納得ができなくて「完成」できない子どもがいる。そういう子どもたちは、社会の価値基準や枠組みの中では時間を守れないダメな人間だと烙印を押されてしまう。そういう凸凹は、科学であらかじめ定義された「知能」の枠にあてはまらないのだ。
そもそも科学で決められているパラメータの定義では、一つひとつの小さな行動の積み重ねを捉えきれない。科学的に知能を表すパラメータを抽出する時点で、こぼれ落ちてしまうものをどう表現していくか。人間の可能性を生かし、生かされていく社会を創っていくために、この問題は避けては通れない。
現在私が代表取締役を務める「SPACE」では、8つの領域のアセスメントを使って子どもたちの特徴を表現している。パラメータの限界を知りつつ、それでもアセスメントをつくった理由は、学校の成績は1つの基準にすぎず、人間の知能の様相はもっと複雑だということを少しでも可視化したかったからだ。世の中に情報はあふれているが、情報を受発信するセンサーは、一人ひとり違う。視覚で情報を認知しやすい人もいれば、聴覚や触覚で認知しやすい人もいる。自分のセンサーの状態や感度を知るきっかけになるものが、いままで存在しなかった。だから、私は子どもたち自身が「自分の学び方の癖」を見つけるフレームをつくりたかったのだ。
たとえば、音は人によって感じ方が異なる。音に対して敏感な子どもは、学校生活で先生や生徒たちの声が混じっただけで、必要な情報が受け取れず、勉強に集中できなくなってしまう。音に対して敏感であることに自分自身や周りが気づかなければ、負のループから抜け出せない。アセスメントで可視化することにより、一人ひとりの情報の受け取り方や発し方の特徴、興味関心の傾向を見つめるきっかけが得られる。
一方で学校のほうも、子どもたちのセンサーがどんな状態なのかを知らないまま、学習が進められている。本人の心身の状態や認知特性の違いによって情報の受け取り方は変わるので、それを前提に学習環境を組まなければ、個別最適の状態に近づくことは難しい。私たちがSPACEで取り組んでいるのは、そのための見える化だ。
いま必要なのは前提を問い直す力
ROCKETで重視したのは、知識を習得することではない。既存の科学技術で明らかになっている前提を疑う、まさに「問う」ことだった。たとえば、子どもたちに食物連鎖について質問すると、教科書通りの知識としてはみんな知っている。しかし、誰もその「現場」を見たことはないのに、本当だと言えるのか? そこで、私たちは子どもたちと東北のある漁村で1週間、魚が鳥に食べられる様子を観察した。すると、トンビがとった魚をカラスが奪い取るのを目撃し、魚をさばくと内臓の中にカニの赤ちゃんがいることも経験した。子どもたちの中で食物連鎖に対する認識が変わり、いままでの知識が正しいかどうかを問うことができるわけだ。問う力とは、自分の実体験に基づいてこそ、輝きを放つものだと思う。
科学技術は試行錯誤の連続の蓄積だ。その成功と失敗のプロセスを知ることで初めて、なぜ、素晴らしい発見なのかが理解できる。しかし、現行の教育制度では、その部分がすっぽりと抜け落ちている。科学技術で明らかになった膨大な情報を知ることが最優先になっていて、結果を導くまでのプロセスが学びの中に落としこまれていないからだ。AIやロボットに代替されないためにも、子どもたちに試行錯誤の機会を与えることが教育には必要ではないだろうか。
「個才」を解き放つことこそがイノベーションにつながる
管理のしやすさや正確性を追求するならば、ロボットでもいいという話になるだろう。そのなかで人間性をどう育んでいくのかが問われる時代にきている。消耗されるような人間ではなく、創造し続ける人間をどう育んでいくのか。そのためには、遊びの部分を担保して、枠を外してあげることが大切ではないだろうか。
私が出会ってきた子どもたちは、ある種の在野の研究者であり、職人だ。子どもたちを自由に解き放つと、彼らは興味の赴くままに、さまざまな領域を横断的につなぎながら、自分で知の体系を創りあげていく。科学技術で緻密に定義を決めて分析し、専門性を高めていくようなこれまでの教育とは相反するかもしれないが、彼らのユニークさの中にこそ、イノベーションの種があるのではないかと感じている。
【構成】高崎美智子


