なぜ多くの韓国の若者が極度の社会的離脱を経験しているのか、そして彼ら・彼女らが再び社会と関わることができるようになるにはどうすればよいのか。
シン・ヒョン Hyun Shin
ピョ・ジョンワン Jeongwan Pyo
キム・ヘウン Haeun Kim
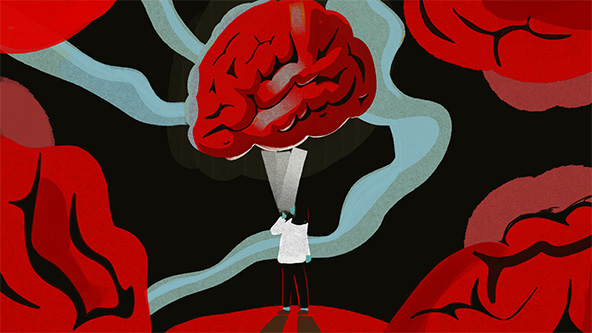
「1年間、家から出ることはありませんでした。その間、風呂にも入らず、汚れた自分の姿を見るのが怖くて窓を開けることさえできませんでした」10年以上も社会との交流を避けて生きてきた若い女性は、韓国放送公社(KBS)のインタビューでこう語った。
中学1年生の時にいじめに遭い、対人恐怖症になったある青年は、その後高校を中退し、最終的に8年間もの間、対人交流を避ける生活を送った。韓国の週刊紙ハンギョレ21のインタビューで、彼は「人間が怖かった。肉食動物のように感じていた。学校の食堂に行くのが怖くて、昼食も食べられなかった」と語った。
韓国では、多くの若者が、自発的に社会から身を引く、いわゆる「極度の社会的離脱1(Extreme Social Withdrawal 、以下「ESW」とする)」を経験しており、これは、その一部にすぎない。ESWとは、個人が限られた空間に長期間留まり、最小限の社会的交流しか行わない状態を指す。仕事や対人関係の問題が原因で陥ることが多く、韓国では驚くほど一般的である。
韓国政府は、(6か月以上の2)ESWを経験したことがある若者(若年層ESW)の数を、若年成人1,100万人の5%にあたる54万人と推定している。これは、2023年に同国の保健福祉省が19~39歳の2万人以上を対象に実施した調査に基づく。この54万人という数字自体無視できないものではあるが、自己隔離という性質上、人数を正確に見積もることが難しく、実際には、より広範囲に及んでいる可能性がある。2022年に、韓国の青少年芸術活動を行う非営利団体「ONEUL(今日)」が社会から離脱している期間を一般的な定義である6か月以上から1か月以上に引き下げた基準で調査をしたところ、19~34歳の若年成人800人の26%が「該当する」と回答している。
若年層ESW は、一般的に絶望感、孤独感、不安、うつ病に苦しみ、薬物依存や自殺のリスクが高い。孤立(isolation)は、家族、労働力としての可能性、そしてより広い意味で韓国社会全体のウェルビーイング(幸福感)にも影響を及ぼす。韓国政府が年間 65 億ドルと試算する社会への実質的なコストに加えて、韓国は現在、世界で最も低い出生率と世界で最も高い自殺率にも直面している。若年層ESWの回復は個人だけではなく、国家にとっても重要な問題であると言える。
これらの若者が幸福を感じられず、社会と積極的に関わることができない背景には、文化及び社会構造的な要因が大きく影響している。そのため、この問題に対処するには、社会的な取り組みが必要である。あらゆる分野の組織には果たすべき役割があり、何が効果的かを把握するための実験的なアプローチが求められている。まだ規模は小さいが、韓国の非営利団体のNEET Lifersは、若年層ESWの社会参加の障壁を取り除き、将来の支援モデルの指針となり得る専門的なプログラムを試験的に運用している。
韓国におけるESW
ESWは、日本語で「ひきこもり」と呼ばれ、「引く」と「籠る」という文字が表す通り、社会から身を引いて(”to withdraw”)、孤立する(”to isolate oneself”)状態を指す。これは 1990 年代に日本で大きな社会問題として顕在化し、当初は日本特有の文化現象だと考えられていた。しかし、現在までに研究が進み、ESW は世界中の国や地域によってその程度や理由は異なるものの、普遍的な社会現象であることが明らかになっている。
韓国では、若者文化とカウンセリングの研究者であるホソ湖西大学校のキム・ヘウォンが2022年に実施した調査で、多くの若年性ESWは内向的、低い自尊心、低いレジリエンス(回復力)、完璧主義などの性質を持っていることが分かった。大多数は高学歴(64%)、経済的には中流階級以上(64%)、第一子(60%)、または両親自身が第一子(74%)である。また調査では、韓国におけるESWの主な原因の1つとして、儒教文化が挙げられている。儒教文化において、個人(特に第一子)は、社会的役割と責任を過度に期待され、教育やキャリアに関する激しい競争に巻き込まれる傾向があるためである。
一生懸命働いて親の期待に応えなければならないという大きなプレッシャーが、韓国の若者を長時間の勉強へと駆り立てている。2018年の調査によると、韓国の小学生は1日平均6時間49分を勉強に費やす一方、余暇には1日わずか49分しか費やしていない。また、2009年のOECD統計によると、韓国の高校生の週平均勉強時間は約50時間で、日本は32時間、米国は33時間、フィンランドは30時間だった。2014年の韓国政府調査によると、その時間数はさらに増加しており、週65時間だった。
幸運にも名門大学に入学できたとしても、その後すぐに、社会的に地位が高く高給な仕事を得るための競争が始まる。韓国の経営者組織である全国経営者協会が売上高上位500社の2023年下半期採用計画について調査したところ、採用競争倍率は81倍になると予測された。つまり、応募した大学新卒者81人のうち、わずか1人しか就職できないということになる。
キムの研究は、集団主義的な文化の中で生きることで個人の選択が困難になること、そして校内暴力や学業不適応などの経験を持つことが、ESWの一因になっていると指摘している。加えて、ESWはこれらどれか1つの経験ではなく、時間をかけて重なり合う経験の結果として生じており、若者が直面している困難を自身で表現できない場合に悪化する可能性があることを示唆している。
また、多くのESWは、富、知識、人間関係といった資本が不平等に継承される社会構造の中で、「金のスプーン (“a gold spoon”)3」を持って生まれた人々と自身の境遇を比較して、相対的な剥奪感を経験している。社会福祉の専門家である全北国立大学のユン・ミョンスクが2022年に行った研究によると、若者のこの剥奪感と、自分の努力だけでは将来を良くすることができないという絶望感は、結果として若者の社会的孤立を助長している。将来に対する希望が持てない若者は、韓国のみならず、多くの国で増加している。
最後に、ESWは孤独(loneliness)を経験する可能性が高く、場合によっては自殺に陥りやすいことも記しておく。高麗大学心理学部教授であるホ・ジウォンによると、深い孤独を経験した人は、生涯で自殺を試みる可能性が4倍~17倍も高くなるという。2020年、韓国の自殺死亡率はOECD諸国の中で最も高く、特に若者の自殺率が高かった。2019年から2020年の間に、10代の自殺率は9.4%、20代の自殺率は12.8%も上昇した。韓国ではESWのリスクがある多くの若者がうつ病などの精神的な問題を抱えており、これらの若者たちには特別な配慮が必要である。
関係性構築プログラムが齎すもの
若年性ESWが直面しているのは文化的、社会構造的な課題にも関わらず、多くの韓国人は、政府や他の機関によるこうした若者たちの支援に対して疑問を抱いている。ブルーホエール・リカバリー・サポート・センターのディレクター、キム・オクランは、京郷日報のインタビューで、社会からの評価は厳しいと語る。「大多数の人々は、なぜ一生懸命働くことなく家にいる若者を助けなければならないのか理解できません」
このような社会的認識は若年性ESWの自責の念と自己嫌悪を強め、必要な支援を受けるための社会復帰を更に難しくしている。
しかし、キムの研究からは、若年性ESWの変わりたいという強い願望と意欲が伝わってくる。この若者たちは他者との関係を築きたいと望んでおり、その社会復帰には支援が必要なのだ。キムの研究で取り上げられた若年性ESWの若者たちは、家族からの関心、忍耐、自分への信頼感、小さな成功体験、カウンセリングやメンタリング、コミュニティを主なニーズとして挙げている。
つまり、ESWに対処する1つの方法は、これらのニーズに応える関係構築プログラムを開発することにある。香港理工大学看護学部のジョリーン・ヨンと彼女の同僚は、ESWの心理社会的回復のための介入方法に関する既存の研究をまとめ、効果的な回復プログラムを生み出す5つの領域を特定した。それは、「つながり」「希望と楽観」「アイデンティティ」「人生の意味」「エンパワメント」である。これらの領域は、効果的な関係構築プログラムの基礎となり得る。しかし、若年性ESWにとって、プログラム提供者や専門家と新しい人間関係を築くことは非常に難しい。ある程度の信頼関係を築いたとしても、若年性ESWは、プログラムが強制的であると感じたり、過度に干渉されていると感じたりした場合、抵抗したり、身を引いたりする可能性がある。この文脈で、秋田大学の公衆衛生専門家ロゼリン・ヨンと同精神保健専門家金子善博は、若者が自分自身や自分の状況について自由に話せる自己省察と対話セッションの有用性を強調している。他の若年性ESWとの関係を築くことは、自らを変化させ、アイデンティティを見出し、社会と再びつながる動機づけとなる。
包摂性の実践
まだ限定的で実験的ではあるものの、非営利団体NEET Lifersは、効果的な関係構築プログラムがどのようなものかを垣間見せてくれる。ソウルを拠点とするこの団体は、就職も教育も訓練も受けていない若者 (NEET) が社会復帰できるよう支援している。事務局長の パク・ウンミは、1つのプログラムの開発から始め、この非営利団体を設立した。当時、彼女自身も失業中の身であった。「失業すると、誰もが社会との断絶を経験します」と、ソーシャルエコノミーメディア Eroun.net のインタビューでパクは語った。「グループに属していないと、交友関係が狭まり、孤独を感じます。日常生活が乱れ、無能または役に立たないと感じ、うつ病やパニック障害につながる可能性があります」
定年退職した男性グループがカフェに集まり会社員生活を模倣することで退屈や無気力と闘うという日本の漫画小説「パラダイスカンパニー」に触発されたパクは、2019年に架空の会社「ニートカンパニー」を設立し、失業中の若者を架空の従業員として採用し始めた。この会社には物理的なオフィスはなく、給与も支払われなかったが、若年層ESWや他の参加者は、採用プロセス、就業体験、退職プロセスなど、会社との関わりについての疑似体験を通じて有益な学びを得ることができた。2023年、成均館大学校の社会福祉学部のペ・ジョンヒは、ニートカンパニープログラムを修了した519人の参加者を調査し、プログラムによって社会的支援(4.7%)、心理的活力(5.4%)、レジリエンス(7.1%)、自尊心(5.7%)が向上したことを確認した。
NEET Lifersはその後、若年性ESW に特化したプログラムの提供を開始し、これまでに約 1,000人の若者を支援してきた。参加者は、毎日オンラインで出勤と退勤の報告を行ったり、業務を報告したり、定期的に同僚と会議を行うなど、職場と同じような日常生活を送る。各人がそれぞれ業務の目標 (外国語の勉強、絵画、運動、皿洗いなど) を設定し、同僚と展覧会に行くなどの交流活動に参加する。プログラムは通常3~4か月続き、その後、参加者は成果報告会で、自身の成果や経験を共有し、互いに達成を祝い合う。このプログラムを通じて、若年性ESWは、自分自身を見つめ直し、日常生活を取り戻す過程で小さな成功体験を積み重ね、そして何よりも他の人と繋がる機会を得ることができる。その結果、若者たちの考え方が変わり、キャリアやライフスタイルに関する視野を広げることができるのだ。
NEET Lifersは、若者がグループで活動する対面型コミュニティのNEET Officeや、失業中の若者が出会ってともにプロジェクトを開発するオンラインコミュニティのNEET Connectなど、参加者主体の新しいプログラムも生み出している。財団やインパクト投資家の支援を受けて、過去5年間で、その支援対象者は2,000人に達し、若者たちが内面の強さを取り戻し、社会と再び繋がることを支援してきた。
今後の展開
次の重要なステップは、ESWが生まれる背景には、社会構造的な要因が大きく影響しているという認識を社会に広め、若年性ESWに対する包括的な支援体制を構築することである。
この問題が韓国より早い段階で顕在化した日本には、1,000を超える民間のESW支援機関があり、支援組織にとって参考となるモデルを提供している。また、2019年時点で、全国67の自治体が、ひきこもりやその家族を対象とした「ひきこもり地域支援センター」を運営している。
韓国では、引き続きより多くの非営利団体が支援プログラムの実証実験を行うとともに、人々の認識を変えるための啓発活動に取り組む必要がある。同時に、企業や政府も、やるべきことがあるはずだ。韓国政府は、ESWを抱える若者のニーズを理解し、効果的な支援システムを構築するために努力すべきである。企業は、社会貢献活動資金を通じて、効果的な非営利プログラムを支援することを検討するべきである。そして、大学もまた、多くの若者が社会から孤立する直前まで接点を持つ機関である以上、他のセクターと協力して若者をエンパワメントできるようになる必要がある。
国連の持続可能な開発目標(SDGs)における「誰一人取り残さない」というスローガンは、包摂的な社会の重要性を示している。韓国をはじめとする世界中で、多くの若者が社会から孤立している状態において、彼ら・彼女らに手を差し伸べることは、この目標を達成する上で非常に重要であり、決して見過ごされるべきではない。あらゆる組織が、ESWの若者を救い、回復させ、社会に復帰させるためのより良い方法を見つける必要がある。
著者紹介
シン・ヒョン(Hyun Shin)は、漢陽大学の教授であり、漢陽グローバル社会イノベーション財団の副会長を務める。また、スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー韓国版の編集長、そしてインパクト・リサーチ・ラボ株式会社のCEOも兼任している。
ピョ・ジョンワン(Jeongwan Pyo)は、インパクト・リサーチ・ラボ株式会社の研究員であり、インパクト測定やインパクトコンサルティングなどの研究プロジェクトに携わってきた。
キム・ヘウン(Haeun Kim)は、インパクト・リサーチ・ラボ株式会社のCOOである。数多くのインパクト測定プロジェクトを実施し、社会イノベーションやインパクト測定、インパクト投資、非営利団体に関する記事やレポートを執筆している。
【翻訳】井川 定一(SSIR-J副編集長)
【原題】Drawing Young People Out of Social Isolation in South Korea (Stanford Social Innovation Review, March 26, 2024)
【イラスト】ラフィ・マルハバ、The Dream Creative
訳注
1 Extreme Social Withdrawal(ESW)は、日本において「極度の社会的ひきこもり」、「ひきこもり」として訳されている場合も見受けられるが、英語のESWとの微妙なニュアンスの差を表すために、ここでは「極度の社会的離脱」とした。Withdrawalを「離脱」としたのは、高齢化と社会との関係を示す「離脱理論(Disengagement Theory)」を参考にした。
2 訳者追記
3 「金のスプーン」は、2015年の流行語で裕福な家庭に生まれた人を指す韓国のスラング。英語の“born with a silver spoon in his mouth(裕福な家に生まれる)”に由来し、親の資産・年収によって人物を、ダイアモンド・金・銀・銅・泥のスプーンにランク付けする「スプーン階級論」の1つ。



90年代に日本で社会問題となった「ひきこもり」が、約30年を経て韓国でも深刻化するということを、当時の日本や韓国の人々は、どこまで想像できていたのでしょう。この記事は、多くの社会課題の出現が国や地域を超えて「タイミング」の問題になりつつあるということ、だからこそ、国境を越えた「課題解決」と「知の共有」が必要であることを示唆する素晴らしい記事であると感じました。
記事にある通り、現在の韓国では、「ひきこもり」は個人の問題と捉えられがちとのことですが、FRJ2025にてむすびえ理事長の湯浅氏が述べたように、この認識は、30年前の日本も同様でした。しかし、あれから様々な調査や議論を経て、日本は現在、社会構造が「ひきこもり」を生み出す要因だと認識しています。日本のこの変化は、韓国における「ひきこもり」の認識を変える可能性があり、韓国の取り組みは日本の活動にも多くの示唆を与えてくれると思います。
素晴らしい記事を書いてくださったSSIR韓国の皆さんに感謝します!
韓国SSIR-Kの皆さんとのオンラインセッションに参加しました。
韓国でも若者の孤独と孤立が大きな課題になっているのを感じました。居場所がないと感じていてもあなたが悪いのではないといえるとわかったこと、誰かとのつながりが心の支えになることを知れてとてもよかったです。日本と韓国の文化・社会的な要因を比較していて、改めて日本の状況を知る機会にもなりました。
SSIR-Kの皆さんから直接話を聞けて良かったです。