「私たちのやりたいこと」が出発点となる
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 03 科学技術とインクルージョン』のシリーズ「科学テクノロジーと社会をめぐる『問い』」より転載したものです。
関 治之 Haruyuki Seki
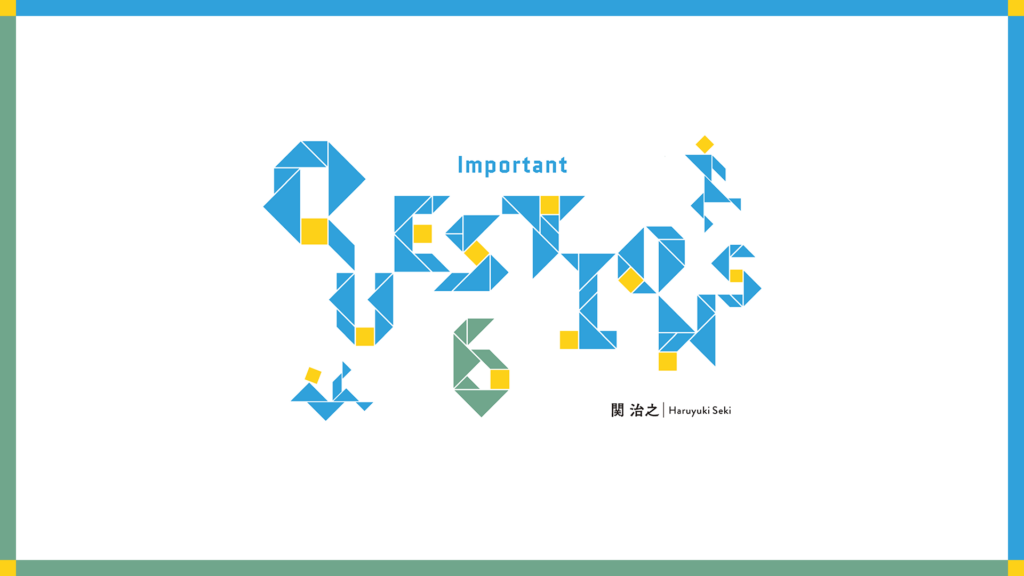
テクノロジーは人を幸せにするのだろうか
「テクノロジーは本当に人を幸せにするのだろうか」という問いが、コード・フォー・ジャパン設立のきっかけとなった東日本大震災時の活動以降、ずっと私のなかでくすぶってきた。テクノロジーを使うことで、人々は幸せになっているのだろうか。むしろ生きづらさにつながっているのではないか。手段が目的化しがちなテクノロジーを、人は正しい目的のために使えるのだろうか。
私自身はもともとエンジニアで、プログラミングが大好きだった人間だ。インターネットが登場したときのワクワク感、人々がつながり新しい価値が生まれていく科学技術のポジティブな側面は、いまも自分の活動のモチベーションになっている。一方で、次第に「AIが仕事を奪う」といったテクノロジーの発展に対するディストピア的な世界観が現れるようになり、各人が自分の情報端末から見たいものだけ、信じたいものだけを取りこみ、つながりたい人とだけつながる、いわゆるフィルターバブルによる「社会の分断」も実際に生まれている。
しかし、結局のところ科学技術そのものは中立的なものであり、「手段」に過ぎない。それが人を幸せにするかどうかは、「誰が何にどう使うか」によって決まる。科学技術を扱うための知識やルール、「規範」のようなものが社会のなかで形づくられていかなければ、悪い社会を生み出す原動力になる可能性もあるだろう。つまり「テクノロジーは人を幸せにするのか」という問いを掘り下げていくと、「人の幸せのためにテクノロジーを使うには、どういう仕組みが必要か」という問いになるのだと思う。
地域住民の「やりたいこと」がシビックテックの出発点
私の活動領域である「シビックテック」とは、市民がテクノロジーを活用して社会や地域が抱える課題の解決を目指す取り組みのことをいう。かつては資本を持つ企業などだけがサービスをつくっていたが、いまでは誰もが身近な課題を、自分たちでテクノロジーを使って解決できるようになった。
コード・フォー・ジャパンでは、地域住民がテクノロジーを利用しながら行政と一緒に地域課題を解決するコミュニティを応援している。たとえば、自治体のホームページからでは地域の保育園の状況を知るのが難しいと感じていた有志が集まって、オープンデータを利用しながらつくった保育園マップがある。それがプロトタイプとなって、のちに自治体が正式なサービスとして提供するに至っている。こうしたことは、行政だけでは実現できなかったことだろう。「こういうサービスが欲しい」「こんな地域にしたい」という地域住民の声がテクノロジーによって可視化され、結果として行政との合意形成がしやすくなるということは既に各地で起き始めている。テクノロジーを使って多様な人たちの意見をより取り入れやすくする。
そういう事例を重ねることで、行政や企業が想像でつくったものではなく、住民のニーズを反映したサービスが生まれていく。
しかし、そこには難しさもある。地域住民とひと言でいっても、多様な人たちが含まれているからだ。行政主導であれば最終的にはトップダウンで決めることができるかもしれないが、シビックテックのような民主的なプロセスでは「公園をどうしたいか」というテーマ1 つとってもさまざまな意見が出てきて、合意形成に非常に時間がかかる。何より大事なことは、そもそも「こうしたい」と参加する人たちが地域にいなければ、シビックテックは始まらない。
実際、コード・フォー・ジャパンはさまざまな地域から依頼や相談を受けるが、「地域づくりに参加したい」と手を挙げる住民が少ない地域をこれまでにも見てきた。ITエンジニアがいて新しい技術が使えたとしても、「どんな町や社会にしたいのか」を主体的に考えて、手を動かす地域住民の参加がなければシビックテックは成り立たない。たとえば私が知らない地域に入って、「新しいテクノロジーでこんなことができるから、やりましょう」と言ったところで、その地域にとって本当に必要なことなのかはわからない。
「来年のお祭りをもっと楽しくしたい」など、内容はなんでもいい。地域の人たちの「やりたいこと」が出発点となり、やりたい人たちが集まって実際に手を動かしてつくったものが周りに受け入れられて広がっていく。それがシビックテックのかたちなので、手を動かす住民が集まる地域コミュニティがないと始まらないのだ。
行政に対するアンケートを見ていても、行政に期待をしておらず、自分たちが主体的に議論をして地域や暮らしを変えていこうという姿勢を持つ住民は少ないのが現状だ。これは特に過疎地で顕著だが、都市部は都市部で地域との距離があって、住民が地域づくりに参加する主体性を持ちにくいという課題がある。
市民がルールを変える側としての経験が少ないことも、こうした状況を生み出す理由の1つだろう。まだ「正解を探す」教育が主流の日本において、中高生のときから校則をみんなで話し合って変えていくような経験を積み重ねられる社会になれば、このような状況は変わるのではないか。
対話と議論を通じた合意形成の土壌があるか
科学技術の進歩にはリスクがつきものだ。科学技術を「正しく」使うためには、市民や専門家、国や行政がテクノロジーの活用法やリスクについてフラットに対話する関係性や場が必要である。どうしても技術者は技術者の間だけ、政治家は政治家の間だけ、行政職員は行政のなかだけで話をしがちで、一方で市民は「特に興味がない」といった状況になりやすい。しかし、それだとそれぞれに最適化された情報しか入ってこず、あるべき姿をともに実現していくようなレベルの合意形成には至らない。リスクを管理するルールや仕組みづくりという点からも、これからは各々が主体性を持ちながら、相手との意見の違いを把握し、対話や議論のなかで落としどころを見つけていく能力が大切になってくる。
シビックテックのような活動をしていると「私にはテクノロジーのことはわからないから」と線を引かれてしまうことも多々ある。こうした壁を超えるためには、その分野に詳しくない人たちだけに努力を求めるのではなく、知識を持つ側やガバナンス側がわかりやすく(「正しい」専門用語にこだわるのではなく)説明して、誰もが広く参加できる機会をつくる努力をする必要がある。両サイドから歩み寄ることが大切だ。
仕組みを正しく機能させるのは市民の関心
どんなに科学技術にリスクがあっても「AIは危ないから、開発を全部止めましょう」というわけにはいかない。
そうなれば、日本だけが世界から取り残されてしまうだろう。もはや科学技術の進歩自体は避けられない。だからこそ、規制や企業の監視など、一定程度のコントロールが必要になる。そのときには、決してリスクはゼロにはならないし、100%のコントロールもあり得ないことを前提にしたうえで、どういうリスクがあり、どう対処するのかというルールや規範といったものを冷静に決めていくことが重要だ。また、技術の悪用を防ぎ、よりよい社会のために使いたいと考えている専門家が、きちんと制度設計に関わっていくことも大切で、それこそが国の果たすべき大きな役割の1つだと思う。
ただし、結局のところ、そうした仕組みが正しく機能するためには、やはり多くの市民が関心を持ち、主体的に参加して意見を言っていくことが前提となる。そうでなければ、科学技術が間違った方向へ使われてしまう可能性は常にあるということを、私たちはしっかりと認識しておくべきだろう。
【構成】中村未絵


