※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 01 ソーシャルイノベーションの始め方』より転載したものです。
西渕あきこ Akiko Nishibuchi
『「わかりあえない」を越える
目の前のつながりから、共に未来をつくるコミュニケーション・NVC』
マーシャル・B・ローゼンバーグ
今井麻希子|鈴木重子|安納献 訳
海士の風(2021)
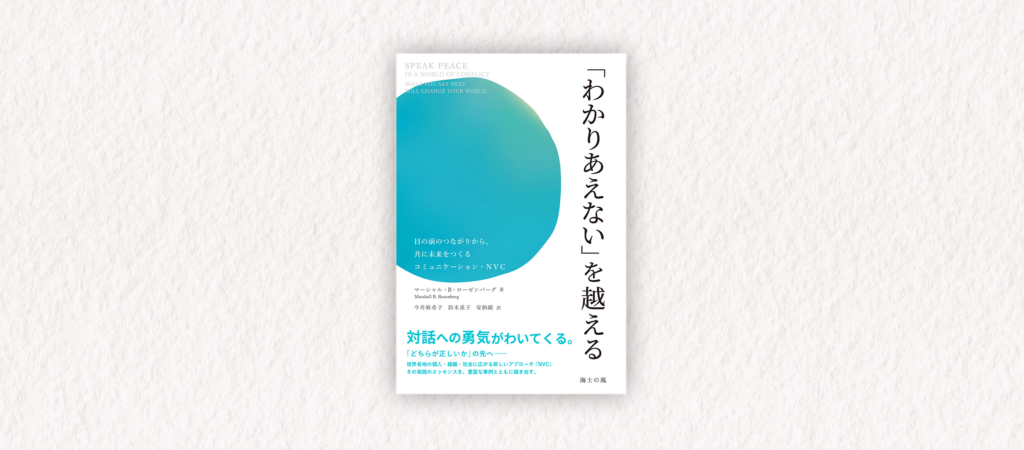
「わかりあえない」とのつき合いは長い。対処方法も心得ている。わがままな要求や期待通りにならないことにも、若い頃のようにイライラしたり声を荒らげたりもせず、落ち着いて対応できる。どうしても受け入れ難い相手なら、距離をとって自分の心を守ることもできる。それがいままでのわたしのやり方だった。
わたしが暮らすイラクのクルド自治区ドホークの人々も、そんなやり方に長けている。大きな紛争から復興しつつあるいま、人々は自分をあまり出さず対立を回避する。民族や宗教が異なる人とのつき合いについてたずねると、「うまくやっていますよ」という答えが返ってくる。ただよく聞いてみると、他者と深く関わらないようにして表面上の平和を維持しているように感じられる。
ドホークは、数年前まで過激派組織ISISの拠点となったモスルから、北に70キロほど離れたところにある町だ。当時、たくさんの人が殺戮や戦闘を逃れて身を寄せた。戦闘が収まったいまでも、約40万人のシリア難民・イラク国内避難民が暮らしている。わたしはここで2018年から3年間、国際NGOで緊急人道支援に携わったあと、現在はフリーランスとして絵本づくりや小学校での活動に取り組んでいる。
わたしがNVC(非暴力コミュニケーション)に初めて興味を持ったのは、紛争地での人道支援に関わる前、日本の企業で中間管理職をしていたときだった。社内の部署間の風通しが悪い。不満や批判ばかりふくらむ。そんななか、自ら手を挙げて部署間をつなぐ役についた。本やトレーニングを通じて学ぶ努力はしてみたが、ほとんど何も実践できないまま組織を離れる決断をした。
NVCの提唱者マーシャル・B・ローゼンバーグによる『「わかりあえない」を越える』には、具体的な実践事例があふれている。まず、NVCの原理として、2つの問いが示される。
• わたしたちの内面で何が息づいている・生き生きしているか?
• 人生をよりすばらしいものにするために何ができるのか?
そして、この2つの問いがいろいろな場面で投げかけられる。親子・兄弟の不和、犯罪者と被害者、若手社員とベテラン社員など、実際に社会で生じる対立のなかで、2つの問いから具体的にどんなコミュニケーションをとって「わかりあえないを越えて」いくのかが描かれる。
著者のマーシャルは、対立する人々の真ん中に立ち、彼らに問いを投げかけていく。その会話の運び方に魅了されつつも、正直にいえば「神業のよう。わたしには無理」と思った。なぜそう考えてしまうのかについての洞察も、本書は与えてくれた。
”わたしたちは、他者を道徳的な判断・決めつけで捉えるように教育を受けています。意識のなかに、「正しい」「間違っている」「よい」「悪い」……といった言葉が染みついているのです。しかも、そうした決めつけは、自分が何に「値するか」という正義の概念とつながっています。悪いことをした人は罰を受けるのに値する、よいことをした人は報酬を得るのに値する、という具合に。”
「あの人は優れている」「わたしには無理」という決めつけや判断も、ひとつの暴力だったのだ。その思考から脱出するには、まず自分の内側で「息づいて」いるものを探り、自分の「感情」と「ニーズ」を聞き取ることから始めようと、この本は説く。
”もし自分自身に暴力をふるってしまうならば、どうやって平和な世界づくりに貢献するというのでしょうか?”
自分自身のこと、そしてイラクの人々のことを振り返ってみる。「わかりあえない」に対して、苦しみを経て身につけた「諦める」「離れる」という処世術。そこには、「感情」や「ニーズ」を我慢する、押し殺すという感覚がある。それでは「わかりあえない」を越えられない。
もしイラクの人々がNVCを学んだら、どうなるだろう?
長い紛争を苦しみ、十分すぎるほど我慢して犠牲を払ってきた人々。自分の感情やニーズを表明しても、誰かを攻撃することにはならないし、誰から攻撃されることもない。そんなコミュニケーションのあり方が存在しうると、初めは信じられないだろう。
民族や宗教が異なる人々が、ともに平和な社会を築いていくためには、みんな少しずつ我慢するしかないの?そうではないやり方もあるんだよ。あなた自身の感情やニーズに耳を傾けるのが第一歩なんだよ。
それをマーシャルのような心の奥に響くやり方で伝えることができたら、人々はようやく心の緊張を緩め、未来への希望を抱けるようになるのではないか。
そして、かつての自分にはこう伝えたい。
あなたは、一生懸命に自分を押し殺しつつ、相手や状況を変えようともがいていた。深呼吸して、自分の内側の声に耳を傾けて。その声をそっと手のひらに乗せて、相手に差し出してみて。それができたら、相手にもそのやり方を伝えられるかもしれないね、と。


