社会的な活動において、その「アウトカム」が非常に重視されている一方でそれを起こす「プロセス」はあまり注目されてこなかった。ケーススタディから見えてきた、変化を起こすプロセスの原則と実践とは?
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 02 社会を元気にする循環』より転載したものです。
アレックス・カウンツ Alex Counts
「The Systems Work of Social Change」
How to Harness Connection, Context,and Power to Cultivate Deep and Enduring Change
シンシア・レイナー|フランソワ・ボニッチ
Oxford University Press|2021
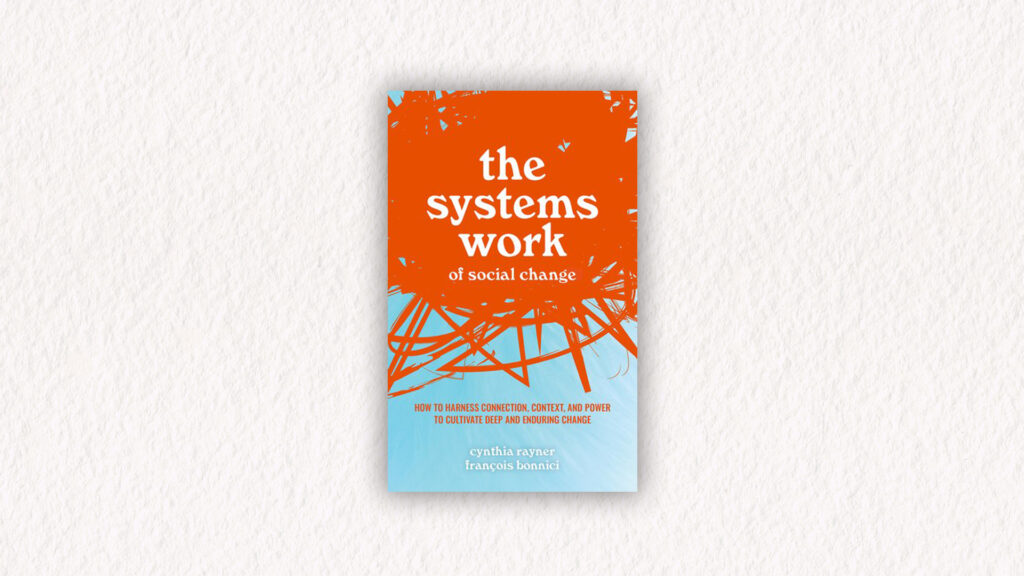
社会の進歩をめぐる議論で、今日の最も重大な社会課題に対して漸進的に改善する方法は有効なのか、という問題がある。
世界の第一人者のなかには、心理学者スティーブン・ピンカーや社会起業家ピーター・ディアマンディスなど、既存システムを徐々に変えていけば持続的な社会の進歩を実現できると主張する人もいる。その一方で、アクティビストのエドガー・ヴィラヌエヴァやジャーナリストのアナンド・ギリダラダスらのように、貧富の格差の拡大から気候変動にいたるまでますます社会の危機が深刻化しており、既存システムは明らかに破綻しているため漸進的な方法ではうまくいかないと主張する人もいる。彼らは、段階的なシステム変化では、山積みの危機を打開するどころか減速すらできないと確信している。
『社会変化のシステムワーク――つながり、コンテクスト、パワーを活かして深く持続的な変化を育む』(The Systems Work of Social Change: How to Harness Connection, Context, and Power to Cultivate Deep and Enduring Change)の中で、著者のシンシア・レイナーとフランソワ・ボニッチは、システム変化を簡単に生み出す方法はないと論じている。そして、8 つのケーススタディを通して、草の根で社会的事業を行う組織を掘り下げ、システム変化のための実践的な道筋を提案している。これらの組織はどれもが人間中心のアプローチを掲げ、支援対象のコミュニティのことを見過ごしてしまいやすい従来型のトップダウンのアプローチを否定している。
「社会変化を目指す長い道のりにおける日々の仕事は、雑然としていて、一直線に進められるものではない。問題の根っこが1つであることはほとんどなく、インプットに比例したアウトプットを得られる
ことも稀なのだ」と著者らは述べている。
著者らによる「システム変化」の定義は、非営利組織による漸進的で気づかれにくい活動を重視するものだ。「これらの組織は、活動のアウトカムをただ喧伝するようなことはしない。むしろ、変化のプロセスに焦点を当てて、急速に変化していく世界により即した、そして、世界中のより多くの、より多
様な人々の声がもっと反映されるような、新たなシステムをつくりだそうとしている」と著者らは説く。「本書で取り上げた組織は新しい価値観やアプローチを用いているわけではないが、目に見えない水面下で変化を起こしてきた。
……私たちは、このような変化を起こす原則や実践のことを『システムワーク』と名付けた」。著者らの定義は、たとえば社会課題を技術的課題に分解してそれぞれを個別に分析し、成果が出るまでせっせとパフォーマンス指標を測定しながら、「うまくいくものをスケール(拡大)する」ことで解決を目指すようなシステム変化の考え方とは異なるものだ。
『社会変化のシステムワーク』は、プロセスと実践に重点を置いて体系的に整理された本だ。最初のセクションでは、200 年にわたる社会変化を目指す活動の研究から導き出された、システムワークの3 原則を紹介している。
①つながりを育む――
学びと成長と変化をもたらす集合的なアイデンティティを構築する。
②文脈を受け入れる――
主役(現場の当事者)に、日々の課題に対応できる力をつけてもらう。
③権限のヒエラルキーを再構築する――
意思決定の権限とリソースを現場の当事者の手に渡すことで、社会システム全体がその中にいる人々の声を確実に反映できるようにする。
2 つ目のセクションは、これらの原則を実践に移すパートだ。4 つの章で事例組織が現場でどのように原則を実践したかを説明している。4 つの実践に共通しているのは、人間中心のアプローチをとっていること、そして活動を行う側の人々と非営利団体の支援対象である人々の両方を重視していることだ。以下が、著者らが見出した4 つの実践である。
①共同体や人と人とのつながりを育む。特にソーシャルメディアを活用する。
②問題解決に携わる人たちに、必要な時間、能力、サポートなどのリソースを提供する。
③問題解決に携わる人同士が学び合い、膠着した組織の壁を乗り越えるコラボレーションが生まれるようなプラットフォームを提供する。
④差別と不平等を生み出し続ける政策やパターンを根絶する。
最後のセクションでは、組織をサポートするネットワークについて分析している。そのネットワークは組織の社会的な目的を実現するために必要なもので、マネジャーやアドバイザーといった内部の関係者から、資金提供者のような外部の関係者まで含まれている。そして最終章では、社会変化を目指す活動におけるリソースの調達と測定の方法を見直すことを提案している。そこで求められるのは、測定の前提となる価値を問い直すことだ。つまり、「どのような価値を測定するのか?」ということだ。著者らはまた、人間関係の強みや人々の相互交流など、見落とされていたり定量化しづらかったりする「目に見えない価値」についても問いかける。
プロセスは、定量的な結果と同等かそれよりも「はるかに」重要である、という本書の挑発的な考え方は、経営者目線のトップダウンのアプローチで社会変化の活動に投資するような人たちを困惑させることになるだろう。
著者らの主張は、それぞれの現場で、適応力と持続力を兼ね備えた分散型の組織づくりをしながら、自分たちと似た組織とネットワークでつながることで「統一感」ではなく「一体感」を持つことは可能だ、というものだ。
レイナーとボニッチは、解決策の規模を拡大すれば複雑な問題を解決できるという単純な考え方は、根拠のない世俗の宗教を信じるようなもので、相互に関連して絶えず変化する、社会課題の本質を見抜けない浮世離れした慈善家がつくりだした「幻想」にすぎないという。そして、複雑な社会課題を解決する活動の「主役」は、「社会課題の中心にいて、その課題自体を体験したことのある人」がなるべきで、資金提供者や専門家は脇役に引いてもらうほうがはるかによいと主張している。
また、人よりも数字を重視して短期的なアウトカム測定に拘る現状を批判して、次のように述べている。「現在の社会変化の指標は、変化を目指す活動に取り組む人や、自分の生活を向上させたいと願う人々にとっての価値よりも、数値化しやすいかどうかのほうが重視されがちだ」。また、こうしたアウトカム指標の利用の前提にあるのは、何を測定すべきかを自分たちは知っており、アウトカム指標を使ったほうがそうしない場合よりも有益だという根拠の乏しい考え方があるという。そしてアウトカム指標とは実質的には価値判断であると指摘する。
著者らはさらに、どうすれば組織のパフォーマンスを上げられるかを追求するよりも、短い時間軸で(しかもたいていはプロジェクトの予算期限を考慮しながら)特定の手法がうまくいったかどうかの証明に重点を置いた評価がされがちであると論じている。その結果、「必要不可欠な学び」が、自分たちの正しさを信仰するエリートたちによって「説明責任という名のもとに」犠牲になっていると批判する。著者らが提案するのは、学びの評価に重点を置いた新しいパラダイムだ。これによって「組織は質の違う問いを投げかけるようになるはずだ。
つまり、『何がうまくいったか』ではなく『何が起こっているのか』を見きわめることこそが、評価の重要な目的であると認識できるようになるはずだ」。
著者らはこれらのポイントを、社会変化の活動における直線的思考への大きな挑戦の一部であると位置づけている。「社会変化を明確な始まりと終わりがあるものとして扱ってしまうと、私たちは必ずストレスをため込むことになる。なぜなら何を変えるべきかは、常に変化していくからだ」。そのような状況に陥らないように著者らが提案するのは、「誰のためのものか? 誰がデザインするのか? 誰が決めるのか? という核心的な問いを投げかける変化のプロセスに焦点を当てることで、未来に向かって柔軟に進んでいけるようになること」だ。そして、社会変化のプロセスをアウトカムの上位に位置づけられるようになれば、厄介な社会課題や環境問題の迅速な解決につながるはずだという。
統合的な分析と適応課題への学習ができる組織づくりがもたらす可能性を示すと同時に
いまでは明らかに役立たない常識は問い直すべきであることを私たちに訴えかけている
ここで、本書の指摘しておくべき限界を述べておこう。まず、著者らは専門家や専門知識を脇に追いやることの弊害を考慮できていない。これは、アメリカをはじめ世界中で、専門知識を軽視する排他的・反科学的・反知性的なポピュリズムが、新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミック対策を妨げてしまった状況と重なる。また著者らは、分析対象の組織を批判的に見ることができていない部分がある。その結果、社会変化に向けた活動の複雑に入り組んだ現実やパラドックス、曖昧さ、妥協といった側面に向き合えていない。
その1 つの例が、国際NGOチャイルド・アンド・ユース・ファイナンス・インターナショナル(Child and Youth Finance International)についての記述である。9 年という短期間ではあるが、彼らは活動をたたむまでの間に、子どもたちの金融リテラシーを高めるという素晴らしい成果を上げた。しかし、目的を達成したのだからもう自分たちは必要ないという団体の驚くべき主張を、著者らは何ら検証す
ることなく受け入れている。
もう1 つは、政府主導の地方分権化が、コロンビアの教育非営利団体フォンダシオン・エスクエラ・ヌエバ(Fundación Escuela Nueva)の達成した驚異的な進歩の多くを覆してしまった事例だ。本書の他の部分では地方分権のアプローチを称賛する一方で、この団体が変化を予測できたかどうか、もっとうまく変化に適応できたかどうかを検証することなく、学生中心のアプローチの大部分は何とか機能し続けている、という根拠のない主張を展開している。
さらに別の例もある。親から子へのHIV感染撲滅を目指す国際的な非営利団体マザー・トゥ・マザー(mothers2mothers)の事例では、感染率の低減効果が若干誇張され(52 分の1 から60 分の1 へ切り上げ)、一方で、比較対象として役立つ情報(基準感染率)は付録に追いやられている。本書では分析対象の組織の業績に関する情報は曖昧だったり不正確だったりすることが多い。こうした情報省略などから生まれる分析の緻密さの不足によって、ケーススタディの説得力が損なわれてしまう。そればかりか、「定量化できるアウトカムよりも見えづらいプロセスを重視する」ことが、そもそも賢明な挑戦なのだろうかという疑念を読者に抱かせてしまうかもしれないのだ。
さらに、実務的な面でもとりこぼしが見られる。たとえば、共通言語を持たない主要な関係者をどうやって招集するのかという問題や、社会で最も周縁化された人々が、彼らよりわずかに裕福な人々が自分たちだけのグループをつくった場合に排除されてしまうという厄介だがよくある問題に、本書は答えていない。もし、本書で取り上げられているすばらしい組織が、このような問題を解決する方法、あるいは少なくとも何とか対処する方法を見出しているのであれば、それらを掘り下げることで、本書はより内容の濃いものとして、社会変化を目指すリーダーたちに多くの指針を与えるものとなっただろう。もしかすると、システム変化の実践者向けにもっとフォーカスした続編がつくられれば、その空白を埋めてくれるかもしれない。
さらに著者らは、本書で主張する原則に多くの成功事例が合致していないことを認識していないようだ。複雑な社会変化の現実において、そして「草の根の市民組織」(流行遅れの言葉だが、私は彼らが復活させたことを嬉しく思っている)の構築において、非常に頻繁に生まれるトレードオフについても、彼らはもっとうまく説明することができたはずだ。
とはいえ、レイナーとボニッチの著作は、最新のフィランソロピーの流行に乗っかるような一過性のものではないことは確かだ。彼らは、統合的な分析と適応課題への学習ができる組織づくりがもたらす可能性を示すと同時に、いまでは明らかに役立たない常識は問い直すべきであることを私たちに訴えかけているのである。
【翻訳】五明志保子
【原題】Embrace the Process(Stanford Social Innovation Review, Winter 2022)


