生と死、健康と病気、若さと老い
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 03 科学技術とインクルージョン』のシリーズ「科学テクノロジーと社会をめぐる『問い』」より転載したものです。
占部まり Mari Urabe
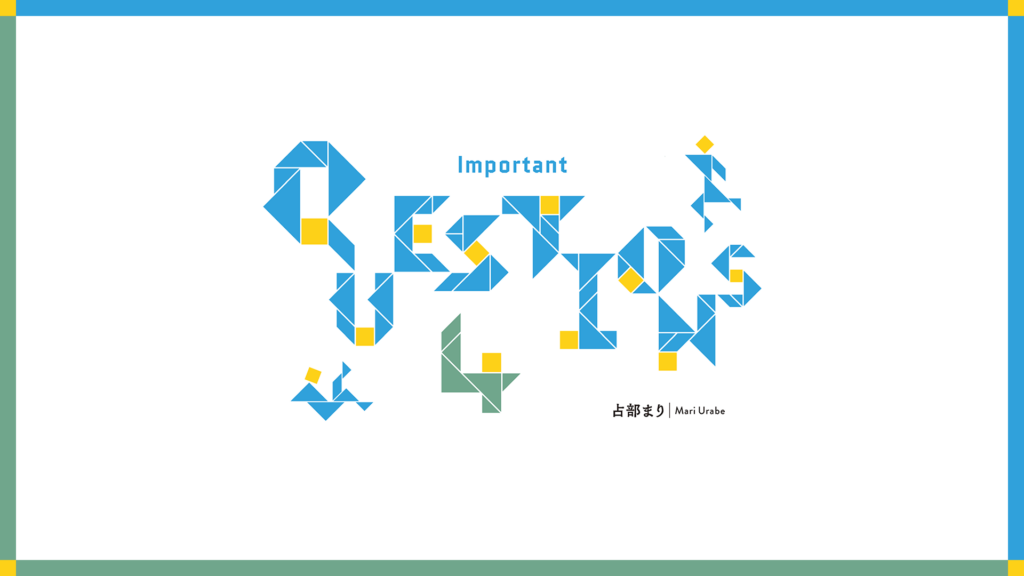
命と向き合う
テクノロジーがいくら発展しても、万人に老いや死は訪れる。だからこそ生命に対して向き合う必要がある。医師として臨床の場で常に感じていることは、「人が生きるとは何か」という根源的な問いだ。裏を返せば「死をどのように考えるか」ということでもある。かつては自宅で近しい人々に看取られていた命が、いまは病院で亡くなることがほとんどで、時に、病院や施設を転々としてその途中で亡くなることもままある。医療の現場を含めて、この社会において、命の最後の瞬間を手元に持っていたくないという風潮があるように思う。語弊を恐れずに言えば、命というボールを自分以外の誰かが落とすまでパスし続けているような感じだ。誰かが落としたら「ここまで一生懸命パスを回してきたのだから仕方ないね」とそこで試合終了。ボールを受けとめ、いったん目の前に置いて、じっくり見て考える機会がなくなっていると感じる。
その背景にあるのは生と死の分断ではないだろうか。どこからが死かを定義してしまうと、そこから先は生命が存在したこと自体が否定されるようなイメージがある。そもそも人はいつ死ぬのか。死は生活機能の停止を意味し、多くの場合、死の三徴といわれる瞳孔散大、呼吸停止、心臓拍動停止を確認した段階で医師は死んでいると判断するのだが、このような状況で救命活動が始まることもある。現場では、その判定は医師の医学的経験に基づいて行われており、実は厳密な定義があるわけではない。科学が発展した現在でも、死とは曖昧なものなのだ。物理的に存在しなくなった後でもその人が存在した気配がいたるところに染みついているような感覚は誰しもが持ったことがあるだろう。イザナギとイザナミの神話にもあるように、昔の日本人は、生と死の世界を自由に行き来するような生命観を持っていて、いまでもお盆などの風習にそれが残っているが、医療の現場において死を正式に宣言してしまうことで「その先」を語る場がなくなってきているように思う。
いまはVR 技術やチャットボットを通じて故人と再会したり対話したりするような体験も可能になった。こうしたテクノロジーは死別による喪失からの立ち直りをサポートするグリーフケアという点で救いになるかもしれない。しかしテクノロジーがいくら発展しても、それによって生命とは何か、生きるとは何か、死とは何かという問いに答えが出ることはないだろう。こうした根源的な問いについて、結論や評価を求めることなく問い続けることを容認するような“死” に向き合う文化の醸成が必要だと思っている。死について、いろいろな角度から話す場所をつくりたいという思いで始めたのが日本メメント・モリ(ラテン語で「死を想え」の意味)協会だ。現在はCOVID-19 のため思うように活動できていないが、宗教者、医療介護関係者、哲学者など、さまざまな分野の人とともに死を考える場を提供してきた。活動を通して感じるのは、現代社会においては死が身近ではなくなったと言われるが、それだけに個々の死にまつわる経験が深く、それを他の人と話してみたかったという人が想像していた以上に多いことだ。
健康を「能力」と捉えたときに見えてくるもの
生と死の分断が生命の本質を見えにくくする一方で、健康と病気の分断がよく生きることの妨げになることもある。現代社会においては病気と診断されるまでは社会通念上は健康で、診断を受けて病名がつけば患者になる。具合が悪くなって病院に行くまでが「健康」で、治療を受けながら社会復帰を目指している状態が「病気」というのは考えてみれば妙な話である。この矛盾に目を向けた「ポジティヴヘルス」という考え方がある。そこでは健康を「社会的・身体的・感情的問題に直面したときに、適応し、本人主導で管理する能力」と定義している1。困難な状況に立ち向かう「能力」という点にフォーカスすれば、病院に行って診断されるまでが「病気」で、治療をしながら普段の生活を取り戻そうとしている人は「健康」ということになる。「病気や障害があっても、不幸とは限らない」。医療関係者に限らず多くの人がこういった感覚を持っていくことも必要だ。
「ポジティヴヘルス」の延長上には「老い」に対する概念の転換も起こりうるだろう。『ナショナル ジオグラフィック』が世界の長寿研究者と行った「ブルーゾーン(長寿地域)」の研究によれば、100 歳以上の高齢者が健康で暮らしている割合の高い地域は大方の予想に反し、いずれもバリアフリー環境や大きな病院のようなお年寄りにやさしい生活のためのリソースがない場所だった。その特集のなかで、地中海の島に暮らすお年寄りのライフスタイルが紹介されていた。
彼の一番の楽しみは、毎日夕方カフェで友人と海に沈む夕陽を見ることだった。健康のためにリハビリをしましょう、歩きましょう、と言われても人はなかなか動かないが、「お気に入りのカフェで親しい友人と美しい夕陽が見たい」というモチベーションがあれば人は歩いていく。このような話を聞くにつけ、人を1 日でも長く「生」の側につなぎとめることよりも、人がより孤独でない状態をつくることに重点を置いた科学とテクノロジーのあり方が求められているように思う。
テクノロジーの進歩は止められない
変化や成長を求めるのは人間の根源的な欲望であり、そこから資本主義が発展し、科学技術が進化してきた。経済学者だった父2 は利潤追求優先の経済活動が引き起こす社会矛盾に着目し、人々が互いを尊重しながら安心して暮らすための経済学を追究していた。そのなかで「企業が利益を求めるのは自然なことである」としながらも、「企業の活動が社会にどのような影響を及ぼすのかを常に考えるべきだ」と言っていた。科学技術の発展についても同様に、それが社会にどのような影響を及ぼすのかを科学者や技術者は常に自らに問うべきだ。たとえば医療の分野では眼鏡やペースメーカーは、社会に大きな恩恵をもたらした。物が見えない不便さや心臓が止まる不安から解放されることで一人ひとりの生活の質がどれだけ上がったことだろう。最近でいえばCOVID-19 のワクチンは多くの人の命を救った。しかし、科学技術の発展のもたらす影響はこうしたポジティブなものばかりとは限らない。また、短期的に見ればポジティブでも長期的に見ればそうでないものもある。
父はまた、リベラリズムという価値を大切にしていた。「政治的権力、経済的富、宗教的権威に屈することなく、一人ひとりが、人間的尊厳を失うことなく、それぞれが持っている先天的、後天的な資質を充分に生かし、夢とアスピレーションとが実現できるような社会」を理想とする考え方である。そこには「他者の自由を侵害しない」という条件がつく。この「他者」のなかには未来世代も入ると私は考えている。未来世代に対する責任も感じながら科学技術発展のかじ取りをしていくことが必要だと思う。私たちの世代が「自分たちは最善を尽くしたから、次の世代はもっとよくなる」と胸を張って言えるように。
1 『オランダ発ポジティヴヘルス』シャボットあかね著、日本評論社、2018年
2 宇沢弘文(1928-2014)


