鍵を握るのは地味で地道なプロダクト改善能力
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 03 科学技術とインクルージョン』のシリーズ「科学テクノロジーと社会をめぐる『問い』」より転載したものです。
及川涼介 Ryosuke Oikawa
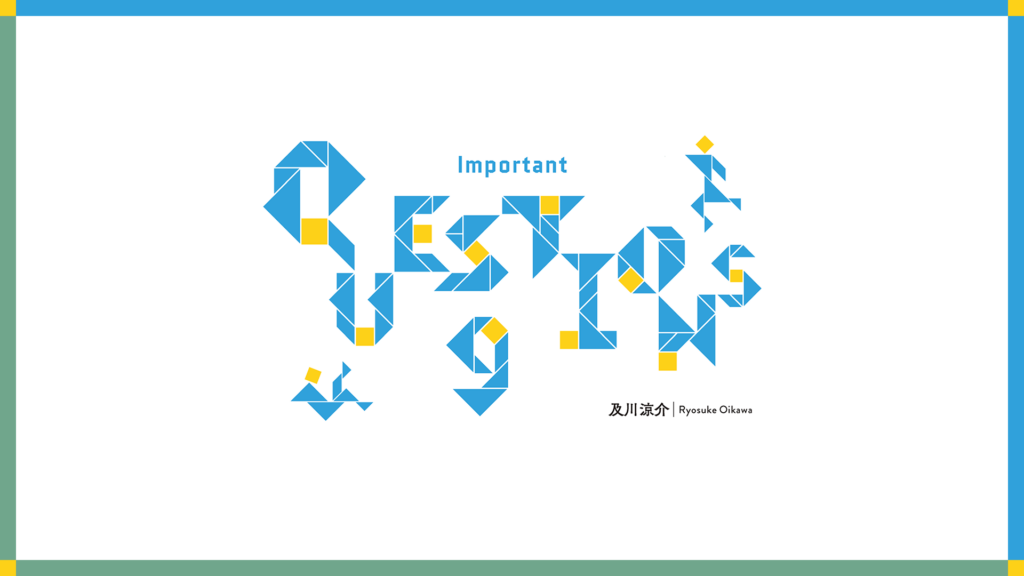
人の生活を変えるイノベーションとは
10年前、高校生だった私は、テクノロジーの拓く未来に心を躍らせていた。ソーシャルメディアやシェアリングエコノミーの台頭が経済や社会システムを根底から変えるのだとワクワクしていた。
それから10年が経ち、当時のイノベーションは既に生活になじみ、当たり前になった。もはやUberは新しい経済の旗手ではなく、出前やタクシーを頼むアプリの1つに過ぎない。
考えてみれば、これまでもそうだったはずだ。電気や自動車も出現した当時は画期的だっただろうが、今や日常の一部だ。各戸に電線が引かれ、スイッチ1つで明るくなることに心躍らせる人は少ない。コモディティになれなかったイノベーションは、歴史の波に埋もれ、忘れられていった。
新しいテクノロジーが生活に根付くために必要なのは、華々しい変革ではなく、気が遠くなるほど地味なプロダクト改善の積み重ねだ。そのプロセスを経て、初めてイノベーションは人々の生活に役立つものとなる。
自治体として市民のために何ができるかと考えると、この一見地味で地道な改善プロセスが持つ大きな意味に気づく。本当の意味で人の生活を変えるということは、地道な課題解決を繰り返した先にしか実現しないのではないか。過去にイノベーションと呼ばれたテクノロジーを振り返ってみて、そのように感じている。自治体がこの改善プロセスを繰り返すためには、まず市民のニーズをすくい上げる必要がある。
自治体こそプロダクト改善が必要な理由
総務省と民間企業で「行政のデジタル化」に取り組んできた私は、2022年4月、静岡県裾野市の副市長に就任した。裾野市役所では「日本一市民目線の市役所を目指す」というミッションを新たに策定したが、これはUX(顧客体験)デザインにおける「人間中心設計」の考え方を意識している。財政の健全性を維持しながらも、低コストで良質な行政サービスを提供できなければ、小さな地方自治体は生き残れないという危機感があった。市役所組織も、制度中心・法令中心の考え方から、市民のニーズを起点にした考え方に転換しなければならない。
裾野市だけではない。全国の自治体が高齢化・人口減少問題に直面している。「2040 年までに全国の市町村の半数が消滅する可能性がある」と警鐘を鳴らす調査もある。消滅までしないにせよ、人口や歳入が減少すれば、地域の持続可能性が危ぶまれる。
効率だけを考えるのであれば、医療や教育、交通インフラを都市部に集中させるほうが早いかもしれない。だが、大切なのは効率だけではない。自分たちの住む地域や地縁を守り、幸せに暮らしたいという住民の意思があるから、地方自治体が存在するのだと思う。では、どうすれば「住み続けたい」と思えるまちになれるのだろう。私は、行政組織のプロダクト改善能力が鍵を握るのではないかと思う。
民間企業であれば、ユーザーのニーズを把握するために市場調査を行う。経営指標をリアルタイムに確認し、打ち手を講じる。民間では当たり前になされているこうした手法を取り入れている行政はまだ少ない。「選ばれる自治体」になるためには、このような地道なプロダクト改善の手法を活用することが必要ではないか。
そして、ユーザーである市民の声に合わせたサービス設計や改善を低価格で行うのに、デジタルツールは効果的に機能するはずだ。
行政サービスのデジタル化を考えるときには、市民サービスの向上と行政職員の負担軽減を両輪で考える必要がある。私が副市長になって半年間で注力したのは、実は庁内のデジタルインフラの整備だった。地味に聞こえるかもしれないが、インフラ改善というのはうまく作用すれば大きなインパクトにつながる。新しいインフラを使いやすく設計し、実際に職員に使ってもらう。改善すべきところがあれば、意見を聞いて改善する。そんな小さなサイクルを庁内で回す必要がある。
デジタル化の導入に際して、職員のモチベーションがボトルネックになることは多い。慣れたやり方を手放すことにためらいを感じるのも当然のことだろう。それでも、インフラがしっかり整備され、デジタルで仕事をするほうが楽で早いことがわかれば、職員も新しいやり方に前向きになり作業時間が減る。そこで空いた時間を、市民が本当に必要としていることのために使うことができる。
テクノロジーは社会発展を牽引してきたが、課題解決のツールに過ぎないことを見誤ってはならない。私たちが一番大事にすべきは、市民が必要としていることのためにサービス改善を繰り返すことであって、それ自体はテクノロジーがあってもなくても実現しうる。デジタル化の起点は「何ができるか」ではなく「何が必要とされているか」である。そして、どんなサービスや商品も、つくって終わりではない。市民のニーズや要望を把握しながら地道に改善を繰り返し、しっかりと成果を出していく必要がある。
デジタルデバイドは高齢化のせいなのか
テクノロジーが生み出す問題の1つに、デジタルデバイドが挙げられる。それは、行政のデジタル化を進めるうえでも避けては通れないものだ。では、たとえば「スマホ弱者」といわれる高齢者層が完全にスマートフォンを使いこなすようになったら、社会はどのように変わるだろうか。
市民向けスマートフォン講習会に参加したとき、印象的だったのは、スマートフォンは苦手という高齢者の多くがLINEを使いこなしていたことだった。電話と同じように連絡帳から相手を選び、テキストメッセージを送る。シンプルでわかりやすいという。
年齢によるデジタルデバイド問題が指摘される。しかし敬遠されているのはスマートフォン操作そのものではなく、アプリのわかりにくい UI(ユーザーインターフェース)ではないか。そう考えさせられた。
電子機器が苦手という高齢者でも、テレビや電話は難なく操作でき、自動車も運転できる。スマートフォンやPCばかりを特別視することもない。講習会では「わからないから恥ずかしい」「何を聞いていいかわからない」という声もあった。そうだとすればサポート次第で問題は改善するだろう。
高齢になると変化に対応できなくなるといわれるが、本当にそうだろうか。変化に対する許容性の低下を招いている真の要因が、高齢化ではなくアクセシビリティの問題であれば、商品やサービスの使い勝手を改善し、その使い方をしっかりサポートしていくことで解決できる可能性がある。
デジタルデバイドを高齢化のせいにするのではなく、実際の要因を突き止めることが重要だと思う。これはICT技術に限った話ではない。新しいテクノロジーや考え方を受け入れられるかどうかは、社会の柔軟性や成長力に直結する。仮に地道なプロダクト改善や丁寧な伴走によって解決できる余地があれば、打ち手は変わってくる。日本は課題先進国ともいわれるが、今後どれほど高齢化が進んでも、変化に対する許容性を失うことさえなければ、この国の成長可能性は増していくのではないだろうか。
「何が必要とされているか」を起点に始まる行政のデジタル化は、さらなるデジタルデバイドを生むことなく、人の生活を変え、豊かにするための一助となれるだろうか。私も市民のニーズの把握とサービス改善という地味で地道なプロセスを繰り返しながら、挑戦し続けていきたい。
【構成】渡辺裕子


