MOOCsやAI教師など新しい技術が広がり、誰にでも平等な教育機会が実現するという期待が高まっているが、いまだ本質的な教育改革に至っていない。テクノロジーの導入だけではなぜ不十分なのか?
また、「教師」は本当に不要になるのだろうか?
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 01 ソーシャルイノベーションの始め方』より転載したものです。
フラワー・ダービー Flower Darby
「FAILURE TO DISRUPT : Why Technology Alone Can’t Transform Education」
ジャスティン・ライヒ Justin Reich
Harvard University Press|2020
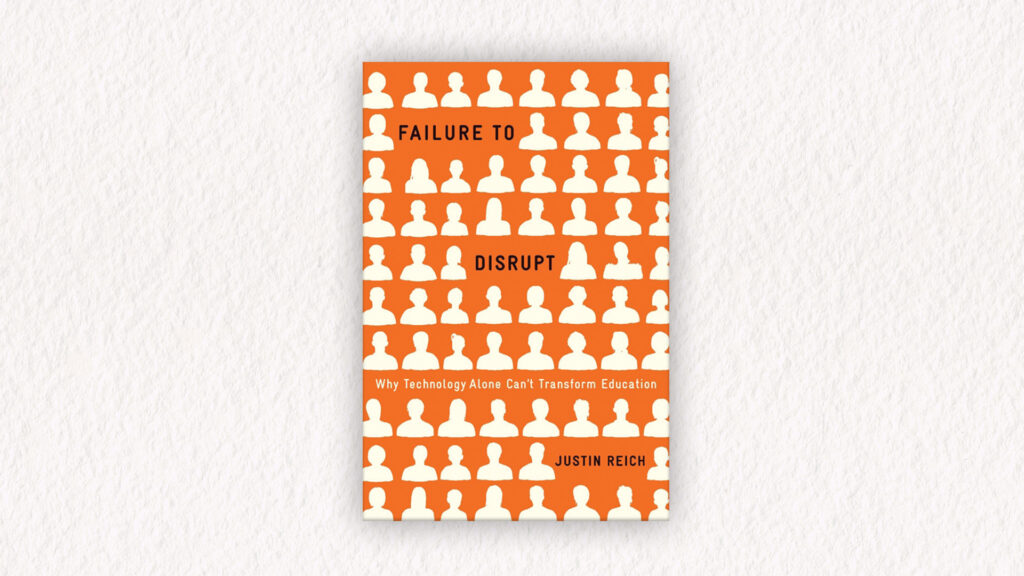
最もアナログ思考の教師でさえテクノロジーを使うことが求められる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延下において、教育に変革をもたらすテクノロジーの可能性についての本を書くというのはいささか奇妙であると、ジャスティン・ライヒは承知している。ライヒは著書『ディスラプションの失敗―なぜテクノロジーだけでは教育を変革できないのか』(FAILURE TO DISRUPT: Why Technology A lone Can’t Transform Education)のプロローグでこう述べている。「最高の未来とは、社会における公教育システムの重要性を認識し、そこに適切な資金や支援や敬意を集められる未来である。そして学習テクノロジーとは、それを使いこなす教育者のコミュニティがあって初めてその威力を発揮することができるものだ」。この著者の洞察は、どれほど革新的なテクノロジーであっても、それだけでは世界を変えることはできないという本書の主張を端的に言い表している。
世の潮流に逆らうようなタイミングで出版された本書において、マサチューセッツ工科大学(MIT)の比較メディア研究の教授であるライヒは、大規模学習向けの教育テクノロジーが、その推進者たちの大げさな主張に見合うほどのものではないと論じている。MOOCs(ムークス。世界中の大学の公開オンライン授業を受けられる大規模プラットフォーム)や適応型学習システム(学習者一人ひとりに最適化された学習教材)のようなイノベーションが教育改革や学力格差の解消につながるというのは、裏付けのない予測にすぎない。それよりも必要とされているのは、教育がより公平なものになるよう、慎重に注意を払いながらゆっくりと着実に変革を進めていくことであると、著者は述べている。
教育システムは、保守的であるからこそシステムレベルの変化が必要だと著者は説く。1 人の教師が教室いっぱいの生徒を教えるという教育の基本的なかたちは、何世紀も変わっていない。自分が教わったように人に教えているだけなのである。つまり、MOOCsや適応型学習システムといった大規模学習テクノロジーも、教育を根本から変えたわけではないというのが著者の見解だ。教育はテクノロジーに追いついていない。むしろ、革新的だったはずの新しい技術は、どこまでも伝統的な教育システムに取り入れられようとする過程で、これまでの教育方法や学習方法をデジタルに置き換えただけのものとなってしまった。
たとえば、かつてMOOCsは、教育の機会を世界中の誰にでも低コストで提供できるとしてもてはやされた。しかし実際は「主に専門性の高い修士課程や社会人教育プログラムといった、既存のインフラを補完するものとなっている」。オンライン学習アプリのQuizletも同様の例として挙げられている。Quizletは人気もあって効率的ではあるが、単語帳を使った昔ながらの学習方法をデジタル化しただけであり、教育に変革をもたらすものではないと著者は断言している。
ライヒは、少数の教育者でも多くの学生に学習機会を提供できる大規模学習テクノロジーやオンライン学習環境について、教師主導型、アルゴリズム主導型、ピア・ラーニング型という3 つの既存カテゴリに分類し、それらを 2 つの代表的な教育哲学と結び付けて説明している。ひとつは教授主義的アプローチで、生徒は空っぽの入れ物でそこに教師が知識や情報を注ぎこむという考え方だ。もうひとつは構成主義的アプローチで、学生が自ら試行錯誤しながら学ぶ環境をつくることで、学生の興味や好奇心を引き出すことを目指している。
MOOCsは、教師が主導する教授主義的な学習テクノロジーの好例だ。学習者は、事前に教師や専門家が学習促進に最適だと考えた教材を順番に学んでいく。コースは直線的で、あらかじめ用意されており、すべての学習者に共通だ。
同じ教授主義的なテクノロジーでも、学習者一人ひとりのインプットに対応するアルゴリズム主導型の学習環境もある。それぞれの学習スタイルや学習進度などの情報がシステムに蓄積され、その情報に基づいた教材を用いるので、全員のカリキュラムがカスタマイズされることになり、教科ごとの強みや弱みもはっきりわかる。追加のサポートが必要な学生には復習と練習問題で弱点を克服させる一方、内容を理解した学生には新しい課題か難易度の高い課題を与えることで、個別の学習ニーズを満たすことができるようになっている。
ピア・ラーニング型の学習環境は、学生の興味や好奇心に基づいた型にはまらない学習に最適だ。一例として著者は、2013 年に大流行したレインボールーム(Rainbow Loom)を挙げている。レインボールームという制作キットを使ってカラフルな輪ゴムでブレスレットなど複雑なデザインの作品をつくる方法を、世界中のネットユーザーたちが YouTubeに投稿していったのだが、これは、公的な教育システムが存在しない場で学習者同士が学びあった例である。ピア・ラーニング型の学習環境は、社会的な交流の場ではうまく機能するが、他者との共同作業ではなく個人の学習進度を評価するように設計されている学校という伝統的な環境においては、効果的ではない。プログラミング・クラブのような課外活動の場を除いては、ピア・ラーニング型の学習環境は学校になじまないだろうと著者は述べている。
著者はまた、近年開発された 4 つ目の新しいカテゴリである、ゲーミフィケーション(ゲームを使った学習)にも触れている。ゲーミフィケーションは、教授主義的な学習環境でも構成主義的な学習環境でも広まっている。楽しい冒険に見せかけて計算の練習問題をさせる教師主導型のゲーミフィケーションもあれば、オンライン上の投稿者たちからゲームを進めるヒントやコツを教えてもらうマインクラフトのようなピア・ラーニング型のものもある。しかし、MOOCsや適応型学習システムと同様に、ゲーミフィケーションも教育を根本から変えるには至っていない。学習者はゲームの遊び方を教わるが、そのスキルが日常生活を含む他のパラダイムで「柔軟に展開できる」ものかどうかは疑わしいと指摘されている。
本書の後半では、どんな大規模な学習環境も教育機会の不平等をなくすには限界があるという複雑な問題が論じられる。まず、「慣れの呪縛」の章では、革新的な技術が既存の教育システムに適合するようにねじ曲げられ、その効果を希釈されてしまいがちだと述べている。また、社会学者ロバート・マートンが提唱した「成功がさらなる成功を生む(マタイ効果)」という効果が教育テクノロジー(EdTech)にどのように表れているかを検証している。著者は、テクノロジーへのアクセスと特権を持つ人々が、恵まれない環境にいる人々よりも、大規模学習テクノロジーからより多くの利益を享受して「成功がさらなる成功を生む」効果を生み出していると説明する。さらに、「ルーティン評価の罠」の章では、自動化された評価はコンピュータが得意とする分野でしか効果がないこと、その一方で、未来の仕事では自動化できない複雑なことができる人材が求められるようになることを説明している。さらに決定的なジレンマは、「データと実験の有害性」の章だ。ここでは、明示的な許可なしに学生のデータを収集することについての複雑で倫理的な懸念について触れている。
著者の提案は、こういった批判的な評価を考慮しながら、学生、親、教師、研究者などさまざまな人々が協力してテクノロジーの設計と開発に長期的にコミットしていくことだ。「大規模テクノロジーには教育を変える力がある」という大げさな主張をするよりも、テクノロジーの実装方法を研究し、小さな改良を着実に積み重ねていくことでより良い結果を生みだすことができるだろう。そして何よりも必要なのは、システムレベルの変化にコミットすることであり、専門性の育成に特化した教育者コミュニティや、地域インフラの改良、学生がテクノロジーをより効果的に使えるようにするための保護者向け教育プログラムなどへ投資することだ。つまり、大規模学習テクノロジーを学校や大学に導入するだけでは、システムを変える決定打にはならないのである。これらの技術的な手段が大きな力を発揮するためには、人とシステムの両方を包括的にサポートしていくことが必要だ。
著者の分析と提言は、豊富な経験とゆるぎない研究、そして事実と史実に基づいた情報を根拠にしたものである。しかし、著者の分析においてのみならず、大規模学習テクノロジー全体には何かが欠けている。
それは、教師である。大規模学習テクノロジーが失敗するのは、そもそも学習促進に必要な教育学の専門スキルを欠いたコンピュータ・プログラムを教師に置き換えようとするからである。教師は、教科についての専門知識と教育スキルの両方を兼ね備えており、目の前にいる学習者たちのニーズに応じてその知識と専門性を最適化する。なぜなら、個々の学習者の振る舞いも教室全体の学習経験も、教師がそのクラスでどのように教えるかに影響を与えるからだ。教室にテクノロジーを実装する際の課題にアプローチするためのTPACKというフレームワークを検証すれば、なぜ大規模学習テクノロジーによる学習環境が効果的でないのかがわかる。教師にはTPACK(Technological, Pedagogical, and Content Knowledge)を構成する「テクノロジー」「教育学」「コンテンツ(教える中身)」という3 種類すべての知識が必要だが、どの知識がどれだけ必要となるかは教育の現場や場面ごとに異なる。そして、その場で何が必要とされるかを判断できるのは人間だけだ。それをあらかじめプログラムしておくことはできないし、学生はロボットではない。テクノロジーは人間と同じように教えることはできない。人間だけが教育学的な訓練や経験を通して得た知恵と専門知識を持って、必要に応じたスキルを駆使して教えることができるのだ。
著者の分析からは、学生の学習を手助けする教師の価値が見過ごされている。歴史的に社会から取り残されてきたグループや低所得層の学生たちは、非人間的なテクノロジーなど必要としていない。直面している課題を乗り越え、学ぶために彼らが必要としているのは、人との結びつき、助言をもらえる関係、そして他者からの気づきである。
なぜこうしたものが必要とされているのかを理解するためには、著者の「ルーティン評価の罠」の議論に立ち戻って、コンピュータには何ができないのかを考えてみることだ。著者は評価の自動化には限界があると述べている。コンピュータには非構造的な問題は解決できないし、一定のレベルを超えた複雑なコミュニケーションもできない。その一例として、航空会社のチェックインカウンターでは、これからもスタッフによるチェックインの手助けが必要となることを挙げている。型どおりのチェックインなら専用の機械が担うことができるが、チェックインの過程で基本的なコミュニケーションやサービス以上のものが必要となった場合には、人間が対応する必要がある。
教育についても同じだ。コンテンツの提供や評価の一部はプログラム可能だが、特にクリティカル・シンキングや複雑なコミュニケーション、非構造的な問題解決についてテクノロジーで対応するには限界がある。
そして、このような自動化できないスキルこそが、まさに教師が生徒に与えられるものなのだが、これについても著者は触れていない。教師は、人間同士のやりとりや関わりや励ましを通して、生徒が学ぶべき自分の軸の持ち方や交渉術やクリティカル・シンキングを教えることができる。しかし、このレベルの複雑な指導となると、どんなテクノロジーにも不可能なのである。
公正を期すために言うと、著者は「大部分の学習者が必要としているのは、サポートや他者とのやりとりである」と述べており、大規模学習テクノロジーを意義あるものとして実装するためには、教育者の育成をもっと充実すべきだと呼びかけている。そして、特に低所得層の通う学校向けに、十分な教育者の育成を行うことと、学習についての持続的な教育者コミュニティをつくることを提案している。しかしながら、コンピュータには教えられないことがある、つまり、複雑なコミュニケーションや込み入った人間的な問題の解決は不可能だということについては、指摘し忘れているのである。
著者は、教育に根強く残る文化を大きく変えるほどの、システムレベルの変化を提案しているが、教育関係者一人ひとりに対しての実践的な手段は提供していない。実践的手段の欠落と、教師の重要性の見過ごしが相まって、理論と実践の間にギャップを残してしまっている。プロローグにはこの視点が盛り込まれているのに、本文ではそれを補完していない。コンピュータは教えることができない。教えることができるのは人間だけだ。結果、いつ終わるか知れないCOVID-19 パンデミックにおいてリモート学習テクノロジーの重要性は増しているが、それだけでは不十分なテクノロジーをいったいどう補えばいいのかという読者の疑問は解消されないままである。
【翻訳】五明志保子
【原題】Learning Isn’t an Algorithm(Stanford Social Innovation Review, Winter2021)


