コロナ禍であらゆる分野のデジタル化が加速したが、特に明確に分かれたのが行政分野だ。コストばかりが膨らんで使い勝手が悪いシステムは、誰もが体験したことがあるはずだ。
より公正なサービスを届け、本当に社会の利益になる「公益テクノロジー」をどう実現すればいいだろうか。
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 01 ソーシャルイノベーションの始め方』より転載したものです。
ジム・フルヒターマン Jim Fruchterman
POWER TO THE PUBLIC
The Promise of Public Interest Technology
タラ・ドーソン・マクギネス|ハナ・シャンク
Tara Dawson McGuinness and Hana Schank
Princeton University Press|2021
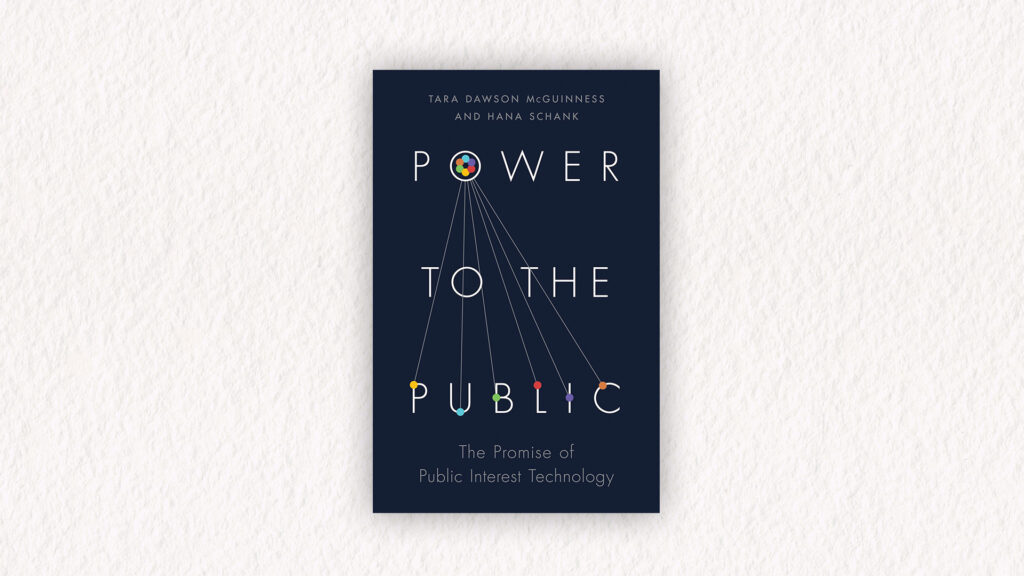
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的大流行は、持てる者と持たざる者の違いを鮮明に浮かび上がらせた。特にテクノロジーに関しては、その差が明らかだ。
通信デバイスを持たずインターネットに接続できない低所得層は、教育や医療へのアクセスが制限された。テクノロジーを使いこなせない多くの非営利団体は、ロックダウンによって対面活動が滞ってしまうと、オンライン事業の開発に移行できなかった。アメリカの州や国の政府は対応に苦慮し、COVID-19 が援助を必要とする人々に及ぼす健康面、経済面、社会面の影響についての詳細な情報を得られないため身動きがとれなくなった。富裕者が豊かになる一方で、低所得者はさらに貧しくなり、より多くの人がCOVID-19 によって死亡し、障害を負った。
この破綻は、1 つの問いを投げかけている。「こうしたトレンドを加速させるのではなく、逆戻しするためにテクノロジーはどう活かせるのか?」米シンクタンク、ニュー・アメリカ(New America)の タラ・ ドーソン・マクギネスとハナ・シャンクは、共著書『社会に力を――公益テクノロジーの可能性』(POWER TO THE PUBLIC : The Promise of Public Interest Technology)のなかで、現代のデジタル技術を活用した行政事業と政策立案の展望を示している。その目的は、「公益テクノロジー」という新たな分野をつくり出すことだ。本書で公益テクノロジーとは、「デジタル時代において、公共の利益を生み出して社会をよくするために、デザイン(設計)やデータやデリバリー(提供)を活用すること」と定義されている。
著者らは、政府のテクノロジー利用における自身の豊富な経験を活かしながら、このテーマの探究に取り組んでいる。マクギネスはニュー・アメリカが設立したニュー・プラクティス・ラボ(New Practice Lab)のディレクターであり、ガブテック[「ガバメント」と「テクノロジー」の造語]にまつわる悲劇と救済の物語に深く関わっていた。それは、オバマ政権下でのオンライン医療保険加入サイトHealthCare.govの悲惨な立ち上げと、シリコンバレーの技術者チームによる有名な救出劇である[開設と同時に大規模システム障害が起こり、その後民間のITエンジニア採用を進め改善していった]。
一方、ニュー・アメリカの公益テクノロジー戦略部門ディレクターであるシャンクは、コンサルティングとテクノロジー分野で長いキャリアを持つ。米国デジタルサービスは、HealthCare.govの失敗をきっかけに、国家の最重要課題を解決するため、技術者を募集する目的で設立されたが、シャンクはその初期の段階から携わっていた。
テクノロジーの良い点と悪い点の両方に向き合った経験から、マクギネスとシャンクは本書において、行政が市民により良いサービスを提供するためにはソフトウェアとデータの利用方法を見直すべきだ、と主張する。
本書は大きく2 つのパートに分けられる。
前半パートでは、従来のアプローチと、新世代の問題解決者たちが技術を駆使して展開するアジャイルなソリューションとの違いが説明される。
新世代の人たちは、「3 つのツール(デザイン、データ、デリバリー)を駆使して、ホームレス状態、里親制度、自殺防止といった課題に取り組んでいる」という。
そして後半パートでは、どうすれば公益テクノロジーを仕組み化できるのか、またどうすれば行政のあらゆるレベルで効果的に実践できるのかに焦点が当てられている。著者らは、テクノロジーを利用した解決策を、ステークホルダー「のためにではなく、共に」取り組むという哲学に基づいてアップグレードし、行政の内部でテクノロジー革命を起こすべきだと的確に論じている。なぜなら「行政の力なしでは、世界で最も困難な問題を解決することはできない」からだ。
本書の中心的なテーマは、行政プロセスに技術的イノベーションをもたらす取り組みは、必要不可欠であると同時に非常に難しいという点だ。過去の意思決定の遺産として、複雑なプロセスが残されているのは珍しくない。
本書で取り上げられる事例には、一見極端なものもある。たとえばミシガン州の支援申請書DHS-1171は、医療、食料、保育などの緊急支援を求める市民が 42ページにもわたる 1204 の質問項目に記入しなければならないのだが、このような非効率な事態を引き起こす原因として、アメリカの州や国の政府が法律で定めた旧態依然な調達方法、方向性のぶれたインセンティブ(動機づけ)、不十分な情報に基づく政策などが挙げられている。また、このようなシステムは非常に複雑で、同じ政府機関内でも異なる部門が、相互に目的が食い違う取り組みをしていることもよくある。
著者らは、プロジェクトの失敗や数百万ドルの浪費をもたらしやすい調達方法に早くから着目していた。空母やオフィスビルの購入なら、詳細な成果を前もって完全に特定できることが前提となるが、そうした調達プロセスは、柔軟なソフトウェア開発にはほとんど役に立たないことがわかっている。
本書では、米国市民権・移民局で使われている申請書をデジタル化した電子移民システム(ELIS)の例が紹介されている。設計の最初のバージョンは、受注したIBMによってコントロールされ、「まず、ソフトウェアライセンスを生成してそれを永続的に維持する機能が優先された。そして次に、当局のニーズに応えるシステムが開発された」という。数億ドルもの大規模なコスト超過をしながらELIS1 が立ち上げられたとき、申請フォームの処理速度がシステム導入前の 5 分の 1 にまで落ちてしまった。それは当局がシステム全体を廃止し、完全なやり直しを決定するほどの失敗だった。
政府が契約しているITベンダーは、プロジェクトの規模を小さくまとめるよりは大きくしたほうがもっと利益が出ることを知っているため、プロジェクトのコストが膨らみがちだ。これに昔ながらの開発手法、つまりシステムや製品を実際に使う人を設計プロセスにも改善プロセスにも参加させないアプローチが加わると、ELISのような大失敗を引き起こす。プロジェクトの予算は大幅に超過し、システムは立ち上げても機能しない。テクノロジーは業務の妨げになるどころか、最悪の場合は現状から後退すらしかねないのだ。
著者は、ソフトウェア設計に人間中心デザインをもっと取り入れる必要があると繰り返し述べている。著者の「誰かのためにではなく、共に」という簡潔な言葉が伝えているのは、テクノロジーは一般市民や行政機関のスタッフのためにではなく、彼らと共に築くパートナーシップによって開発されるべきだということだ。このモットー(行動指針)は、サービスの提供先である個人やコミュニティとの協働を望む、ソーシャルイノベーション分野で活動する多くの人が共感するはずだ。それは受益者のニーズなど顧みられずに設計されがちな従来型の慈善事業や行政プログラムとは対照的なものである。
従来のソフトウェア開発モデルでは、組織のリーダーがソフトウェアの機能や、するべきことをすでに知っていて、それらの要件を満たすようにソフトウェアを設計して構築すればよいと考えられていた。これは「ウォーターフォール方式」として広く知られたアプローチで、行政機関のスタッフや一般市民からのフィードバックを取り入れない直線的なプロセスである。推測だけでつくられた製品は失敗することが多いため、ソフトウェア業界では 10 年以上前からこのアプローチはほとんど使われていない。あらゆる段階でユーザーを巻き込んでいく方法がはるかに望ましいが、行政にはそれがまだ浸透していない。
人間中心デザインの有用性は、ソフトウェアに限らない。著者は、コミュニティからのフィードバックや情報は、政策立案や社会課題の解決策にも反映されるべきだと主張する。
この点について、COVID-19 のパンデミック対策として米国政府が策定したCARES法(Coronavirus Aid, Relief, and Economic Securities Act)の欠点を論じている。
CARES法は、ほかの多くの政策と同様に、実際のデータではなく知識による推測に基づいていたという。著者の見解によれば、「このプロセスに欠けていたのは、COVID-19に苦しむ平均的な家族を助けるためには何が必要か、迅速に検討することだった」。法案が対象としていたのは、正式な銀行口座を有することと、ここ数年に確定申告をしていることの両方の条件を満たす人だ。しかし米国では、超低所得者は確定申告をする必要がなく、銀行口座を持っていない人も多いため、この方法では最も脆弱な立場にある国民のニーズに応えることができなかった。
同様に重要なのは、テクノロジーが解決策にならないケースを知っておくことだ。本書で最も先見性のある事例の 1 つは、ホームレス状態の撲滅を目指すキャンペーンであるビルト・フォー・ゼロ(Built for Zero)が実践した、テクノロジーと非テクノロジーの両方を駆使した介入策だ。
ビルト・フォー・ゼロを立ち上げた非営利団体コミュニティ・ソリューションズ(Community Solutions)の代表兼CEOであるロザンヌ・ハガティの画期的なアイデアは、測定指標を転換したことだった。
これまでは活動内容やリソース(都市で利用できるベッドの数や提供される食事の数など)を測定していたが、それを個人の行動(30 日前に都市で路上生活をしていたすべての人が住居を見つけたかどうか)を確認するようにしたのだ。現代のテクノロジーを活用して、都市部であればどんな機関と接触してもすべての路上生活者の名前をデータベース化することが可能になった。
イリノイ州ロックフォードの地域リーダーのチームは、ビルト・フォー・ゼロの手法を学ぶトレーニングに参加し、それを試してみることにした。このロックフォードのチームが、リストに載っている退役軍人の路上生活者の話を聞くと、最大の問題はバス運賃であることがわかった。著者は「退役軍人が精神的な問題を抱えていて医療機関までの交通費が出せないと、受診予約を逃して必要な薬の服用を継続できなくなってしまい、すぐに依存症が再発して路頭に迷うことになる」と説明する。
退役軍人の路上生活者に無料のバス乗車券を提供する取り組みは、少ないコストで効果を出せる介入策であり、特注のモバイルアプリよりもはるかに優れていることがわかった。
本書は、技術者でない人にもわかりやすくすぐに読めるように書かれており、テクノロジーは万能薬ではないという明確な見解を提供している。本書の文献的な意義は、政府が問題解決のために従来のアプローチを改革する必要があると指摘していることだ。
一方で、本書が代替案を十分に提唱するに至らなかった、という点については不満が残る。たとえば、全50州が同じ連邦プログラムを採用し、それぞれが独自のITシステムを構築するというアイデアは、実際の災害対策としてではなく、単に実現可能なものとして提示されている。
また、行政だけでなく非営利団体も、マクギネスとシャンクが推奨するようなデザインアプローチを採用する必要があるという点にも言及してほしかった。
さらに、技術系の人材をどう確保するかという、もっと注目すべき課題を掘り下げることもできただろう。米国デジタルサービスは、国全体の課題解決に取り掛かるための熟練技術者の採用に成功したが、ソーシャルセクターにおける技術者不足を解決するまでの道のりは、まだまだ遠い。
マクギネスとシャンクは、行動を起こすことを読者に呼びかけて本書を締めくくっている。著者らは、1960 年代に「公共に資する法律利用(public interest law)」のムーブメントが生まれたことを手本にして、公益テクノロジーの分野を築くことを提案する。そして、技術者たちのほうから、自分たちの技術力を社会や地球のニーズに活かそうという機運が盛り上がることに期待している。こうした人材たちが集結し、どうすれば最も必要としている人々にテクノロジーを活かせるかという著者のビジョンを統合できれば、今日の世界の課題に立ち向かうことができるかもしれない。
【翻訳】布施亜希子
【原題】Tech for the Public Good(Stanford Social Innovation Review, Fall 2011)


