企業のダイバーシティ&インクルージョンの取り組みは「自分たちの領域へマイノリティを呼び込む」ことが多い。しかし、逆に「マイノリティの領域に歩み寄る」ことで社会の格差や不平等は大きく改善される可能性がある。特に将来性の高いテクノロジー分野で実践された画期的な「テックインクルージョン・モデル」を紹介する。
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 03 科学技術とインクルージョン』より転載したものです。
リンダ・ヤコブ・サデー|スマダール・ネハブ
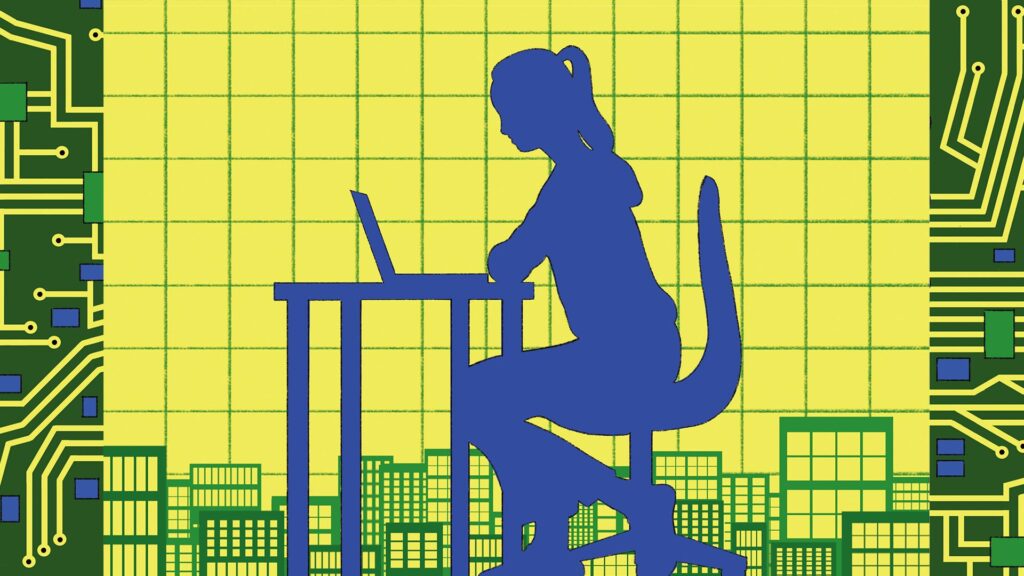
アリは、イスラエルに住むコンピュータサイエンスのエンジニアだ1。彼は、イスラム教を信仰するアラブ系のパレスチナ人家庭に育ち、地理的にも経済的にも国の中心地からは遠く離れた地域に暮らしていた。イスラエルの名門大学を出て、商都テルアビブで大手のソフトウェア企業に入社した彼は、アラブ人がほとんどいないIT 業界では例外的な存在だ。
この会社には、アリが来るまではイスラム教徒もパレスチナ人もいなかった。職場の人たちは彼の文化やアイデンティティに馴染みがないし、理解を示すこともない。イスラム教の祝祭日には孤独感に襲われる。イスラエルの戦没者追悼記念日や独立記念日といった政治色の濃い祝祭日ともなれば、なおのことだ。おまけに都心で働くためには、通勤に往復4時間もかかる。テルアビブ市内でアパートを借りるなど、とても現実的ではないからだ。結局、1年もしないうちに会社を辞めてしまった。
実は、こんな話はアリに限ったことではない。これは世界の成長産業、とりわけテック業界には疎外されたコミュニティ出身者がほとんど参画できていない、という実態を物語っている。ただ、人口比からみてもテック業界で職を得ている人の数が極端に少ないという状況は、彼らが経験している分断や疎外の一部にすぎない。地理的に隔離されている地域が「エキゾチックな観光名所」と扱われるのはまだいいほうだ。ひどい場合には、「犯罪などの危険に満ちた禁断の地区」だと見られることさえある。2つの社会の間に接点が発生するのは、飲食店やオフィス、建築現場などのマイノリティの人たちが低賃金で肉体労働に従事している場くらいだろう。
両社会の交流が乏しいだけでなく、疎外されたコミュニティに住む人たちは、構造的な暴力や過剰な警察活動による抑圧も経験している。そのため、ハイテク業界への就職を志望しながらも、面接に対して心理的抵抗感を持つこともある。つまり、社会のなかに分断を永続させる仕組みがあり、たとえ企業側にあからさまな差別意識がなくても、疎外されたコミュニティを受容していることにはならないのだ。
このように、ただでさえ高いテック業界への就職のハードルをはるかに上回る障壁が志望者の前に立ちはだかっている。その結果、疎外されたコミュニティの出身者で、テック業界を研究や仕事の場に選ぶのは、非凡な才能を持つごくわずかな人だけである。そういう人でも、社会的、文化的に孤立していると感じやすい立場に置かれている。このような分断があまりにも大きいと、テック業界でのキャリアが自分のために存在するとは思えなくなってしまう。成功者の前例がほとんどない業界で、自分がすんなり溶け込んでいる姿などそう簡単に想像できないだろう。
職場のダイバーシティ、公正性(エクイティ)、インクルージョンを推進する取り組みがまったくなかったわけではない。しかし一般的には、企業がすでに持っているオフィスに、疎外されたコミュニティの出身者を採用するケースがほとんどだ。
こうした受け入れ策が適切に実現するためには雇用者側の努力が必要だとの理解から、企業側は職場の「ダイバーシティ」や「インクルージョン」の推進に向けてさまざまな施策を打っている。具体的には、「最高ダイバーシティ責任者」の任命、平等な雇用機会に向けた採用制度の刷新、無意識バイアスを回避するためのダイバーシティ研修の実施、メンター制度の導入やダイバーシティ推進委員会の設置などがある。
だが、こうした取り組みは、たびたび頓挫している。企業側は真摯に取り組んでいるとはいっても、個々の志望者にしてみれば、採用時だけでなく、就職後も長期にわたって幾多の壁を乗り越えていく必要がある。企業側の純粋な善意から生まれたマイノリティ採用の取り組みにも、不都合な現実がある。それは、そもそも応募者が少なく、その限られた応募者が必ずしも満足のいく資質を備えた人材とは限らない、というものだ。
企業側が、疎外されたコミュニティの人たちが不利な立場にいることに理解を示し、専門知識やスキルの面で平等に戦える土俵を整えようとの配慮から、実践的なトレーニングを提供することもある。ところが、このような活動を通じても、テック業界で働くマイノリティの人たちが大幅に増えるまでには至っていない。トレーニングを通じて専門知識や経験が得られても、もっと根深い社会的、民族的、経済的な障壁は手つかずのままになっているからだ。
その結果、矛盾した状況が生まれる。テック業界で技術面での社会的流動性(社会階層間の移動)が実現されても、特定のコミュニティは締め出されたままになっていることだ。さらに、善意の企業がマイノリティの人たちを採用して、ダイバーシティやインクルージョンの施策を導入して彼らを受け入れようとしても、能力も関心もある人材が集まっていない。こうして疎外されたコミュニティの人たちは、専門技術を学んで経済成長を支える分野、特にテック業界で仕事をしようという意欲を削がれたままとなっている。
この矛盾を解消するために本記事で提唱したいのが、「テックインクルージョン・モデル」だ。これは、疎外されたコミュニティ出身者の参画を阻んでいる社会的、経済的な障壁について真正面から向き合うアプローチだ。このモデルが提案しているのは、これまでの発想を転換して、テック業界自体をインクルージョン加速の原動力にすることだ。具体的には、業界のほうに疎外されたコミュニティの人たちを引き込もうとしてきた従来の考え方を転換し、業界のほうからコミュニティ側に歩み寄り、就職志望者と企業の双方にとって有益な環境を整備する、という考え方である。
テックインクルージョン・モデルがハイテク分野に焦点を当てている理由は、排他的な風潮が根強いこともあるが、この業界には大きな将来性があるからだ。その将来性とは、「経歴や生い立ちに関係なく社会的、経済的な流動性が見込めること」「疎外されたコミュニティの近隣地域も含めて、拠点を分散させても雇用が可能なこと」「テクノロジーを重視する国で、労働力の新たな供給源を生み出せること」などが挙げられる。疎外されたコミュニティにテック企業の拠点が開設されれば、地元住民だけでなく、地域外からも専門人材が来て働くようになる。すると、組織内の力関係がリセットされ、ステレオタイプが打破されて、社会変化を後押しする可能性が高まるのだ。
イスラエルのテックインクルージョン事情
テックインクルージョン・モデルが生まれたのは、世界でも特に社会の二極化が顕著で、ハイテク業界に排他的な空気が漂う国、イスラエルだ。2008年時点で、イスラエル総人口のうち、パレスチナ系住民は21%を占めていたにもかかわらず、国家経済の最大の成長エンジンであるハイテク業界で働く専門職は0.5%にも満たなかった2。むろん、イスラエルで多数派のユダヤ系社会にパレスチナ系住民が参画しようとするときに生じる軋轢は、こうした雇用統計データだけでは語り尽くせない。イスラエルでは、通常、パレスチナ系住民とユダヤ系住民は、別々の都市や地区に分かれて暮らしていて、公教育も民族ごとに分かれており、生活の随所に言語の壁や差別が根強く残っている。
2007年、本稿の共著者であるスマダール・ネハブは、特異な立場にあった。コンピュータエンジニアやマネジャーとして豊富な経験を積んだユダヤ系イスラエル人であり、国内のパレスチナ人コミュニティとも深いつながりのあるアクティビスト(活動家)という立場だ。彼女が抱いていた問題意識は、イスラエルの大学でSTEM(科学・技術・工学・数学)分野を専攻したパレスチナ系の学生は、業界全体で深刻な雇用機会の不均等に直面しており、労働市場が機能不全に陥っているというものだ。当時のイスラエルでもすでに技術系人材が枯渇しており、2019年にはテック業界全体の6%にあたる1万8500 人以上の労働力が不足する事態となった3。2007年当時、ネハブはスタートアップ企業でエンジニアリング担当バイスプレジデントを務めており、優秀なエンジニア人材の獲得に苦労していた。彼女はある日、取締役会から求人範囲を海外にも広げるよう求められたが、ある疑問を抱いた。イスラエルには、スキルも能力もありながら職に就けないパレスチナ系の大卒者が多数存在するのに、なぜわざわざ海外に探す必要があるのか? そこで、国内外のテックセンター(産業集積地区)でロジスティクスを専門に手がけていた友人のヨシ・コテンを説得して、自社に来てもらった。
その頃、イスラエルのパレスチナ系住民のサミー・サーディは、自身が暮らすイスラエル北部でテクノロジービレッジを運営し、特にアラブ人が多く住むガリラヤ地方における持続可能な経済の確立に貢献したいと考えていた。ネハブとコテンは、サーディをパートナーに迎え、2008年初めには、イスラエルのパレスチナ系住民とテック業界の橋渡しをミッションに掲げるツォーフェン(Tsofen)というNGOを創設した。
ツォーフェンは、2つの柱で構成される。第一の柱は、パレスチナ系とユダヤ系の共同運営組織とすること。第二の柱は、イスラエルのパレスチナ系住民が暮らす地域へのテック企業の進出を後押しすることだ。
創業者である3人にとって、第一の柱は不可欠だった。パレスチナ系住民が直接、対等な立場で関与しない限り、根本的な変化をもたらせないと考えたからだ。ユダヤ系とパレスチナ系の間には偏ったパワーバランスがあるが、だからこそユダヤ系の人たちには、その恵まれた立場をうまく活かしてこの活動に参加してもらう必要があった。いまでもツォーフェンの基盤として引き継がれているのが、このパレスチナ系とユダヤ系のパートナーシップだ。

もっと大きな課題だったのが、第二の柱だ。何しろ、パレスチナ系住民が集中する地域に事業拠点を開設するよう企業を説得しなければならなかったからだ。業界の専門家らは、「そもそもこの分野にアラブ人はいない」として、進出に後ろ向きだった。その主張もあながち間違いではない。当時、何千人ものパレスチナ系住民が大学で理工系の学位を手にしていながら、ハイテク業界に就職した卒業生はわずか数百人どまり。それ以外の卒業生は、教員になるか、小売業や建設業など資質や適性に合っていない職に就いていたからだ。このように卒業後の進路の選択肢が限られているために、はなからテクノロジー関連分野を専攻しようとするパレスチナ系学生がほとんどいなかったのである。
2007年後半、ちょうどツォーフェンが創業準備を進めていた頃、パレスチナ系住民の居住区としてイスラエル最大の都市ナザレに、ガリル・ソフトウェアという企業が誕生した。この企業を立ち上げたのは、ツォーフェンの「イスラエルに住むアラブ人のハイテク業界進出を促進し、エンジニアの深刻な人材不足を解決する」というビジョンに共鳴した同国のベンチャーキャピタルやハイテク業界の有力者たちだった。ガリルは、アラブ系住民が集まる地域でテック企業の運営が成功できることを証明する事例となった。
ガリルの後に続く企業を集め、事業として成り立つと評価してもらうために、ツォーフェンはイスラエル政府からの助成金獲得に動いた。また、企業の採用を支援するために、トレーニングや職業斡旋のサービスも提供した。こうした戦略が功を奏し、企業の間では、ガリラヤでの事業所開設が前向きに受け止められるようになった。
やがて、イスラエルのパレスチナ人社会に変化が起こり始めた。なによりも、ガリル・ソフトウェアは、若者の進路選択に大きなインパクトをもたらした。ガリルは、地元の企業としてパレスチナ系の若者たちを雇用し、彼らがマイノリティとして扱われることのない職場環境を整え、後進のロールモデルとなる第1世代を生み出していった。この結果、テック業界での活躍も夢ではないと若者たちは理解していった。
この変化の背景には、ツォーフェンによる学生たちの保護者やオピニオンリーダー、財界の有力者といったキーパーソンたちへの働きかけがあった。活動の意義を訴え、地域社会を巻き込むため、アラブ系住民を対象とした交流会やハッカソン(技術者が課題解決のアイデアを競うコンテスト)、技術系、ビジネス系のカンファレンスなど、テック業界と地域社会をつなぐイベントを開催した。さらに、技術職に求められる実践的なノウハウを伝えるトレーニングコース(最近では「ブートキャンプ」とも呼ばれるような短期集中講座)を開講して、大学教育では足りない領域をカバーした。
第1回のトレーニングコースに参加したのは、20代後半から30代後半の優秀な志望者たちだ。彼らはテック業界で働く夢を長年抱き続けていながら、溶接工や商店主、PC管理者などで生計を立てていた。初年度は志望者集めに苦労したため、1回しか開講できなかった。しかしその修了者から就職の成功事例が出たことで、状況は一変した。2年目には2回実施して翌年以降も回数を重ね、2021年半ばにはトレーニングコースの開催数が記念すべき累計50 回に到達し、受講者数が1000 人を突破した。
この14年間で、イスラエルのテック業界に就職したパレスチナ系住民の数は、ツォーフェンの創業者たちの当初の夢をはるかに超える水準にまで拡大している。イスラエルのテック業界で働くアラブ人エンジニアの数は、2008年にはわずか350人にすぎなかった。それが2020 年には8500 人に膨れ上がった。また、イスラエルのパレスチナ系住民が暮らす都市に事業所を開設した企業は、2008年時点ではガリル1社だけだった。それが2020年には、ブロードコムやアムドックス、マイクロソフトなどのグローバル企業を始め、40社以上が進出するまでになった。
単なる数字以上の変化も起こっている。アラブ人が多く住む都市にテック企業が進出し、従業員の大半をアラブ人が占めているという現実は、「テック業界にパレスチナ系住民の居場所はない」という通説を覆すものだ。また、「パレスチナ系住民がユダヤ系住民中心の地域に通勤するのが常識で、その逆はありえない」という固定観念も打ち破った。
トレーニングコース修了生のオルサンは、「コンピュータの勉強をしていたときは、どうせどこも雇ってくれないだろうと思い込んでいました」と振り返る。「まして、地元のナザレで働けるなんて思いもしませんでした。ナザレにある職場を息子に見せることができて本当にうれしいですね。息子も同じ道に進むことができるし、もっと上を目指す夢だって持てますから」
テックインクルージョン・モデルの可能性
本稿ではツォーフェンの事例を掘り下げながらテックインクルージョン・モデルの具体例を紹介してきたが、このモデルはもっと広い範囲に応用できる。このモデルが目指しているのは、次のようなミスマッチを解消することだ。多くの企業は、職場のダイバーシティ推進を謳いながらもマイノリティ人材にうまくアクセスできていない。一方、才能あるマイノリティの若者たちは、大きな社会的、経済的要因によって意欲を失い、自らの能力を活かす業種に就職しようとしていない。
本来ならこの業界は、社会的、経済的な流動性を高める起爆剤としての可能性を秘めているにもかかわらず、いま挙げたような矛盾した状況のために、疎外されたコミュニティへの門は閉ざされたままなのだ。
テックインクルージョン・モデルは、3つの基本原則によってこの矛盾した状況を打破しようとするものだ。第一の原則は、疎外されたコミュニティの出身者をテック業界のほうに連れていくだけでよしとせず、そのコミュニティのほうに業界を引き寄せようとすることだ。言い換えれば、ダイバーシティ、公正性、インクルージョンの従来の手法に疑問を呈しているのだ。
第二の原則は、主流派とマイノリティのそれぞれのコミュニティの間で、真の全面的なパートナーシップを築くことだ。マイノリティの人たちが参画せずに、根本的な変化は実現できない。この基本があまりに見過ごされている。
第三の原則は、モデルの実現に全力で取り組む市民社会の中間支援組織(今回の事例ではNGO)を通じて、根本的な変化を目指すことだ。具体的には、業界への志望者や地域社会のステークホルダーを含む地域社会、テック企業、政府などに対して幅広く働きかけていく。こうした団体は、優秀な志望者の発掘・選抜・トレーニング、コミュニティ内での信頼醸成、現地への企業誘致、政府への支援要請などさまざまな役割を果たすことができる。
テックインクルージョン・モデルは、この3つの基本原則から4つの施策に落とし込んでいる。
1. 疎外されたコミュニティの中心部にテック企業の事業所を開設する
2. 実践的トレーニングで能力開発を行う
3. 地域社会の理解を得る
4. 政府を巻き込む
ここに挙げた施策は、それぞれで最大のインパクトを出せるように、ほぼ同時に進めていく必要がある。以下、4つの施策を個別に見ていこう。
施策❶ 疎外されたコミュニティの中心部にテック企業の事業所を開設する
地元からの雇用を前提に、そのコミュニティの中心部に事業所を開設すれば、テック業界への就職に現実味があることを地域住民と業界の双方に行動で示すことになる。さらに、政府や他の潜在的なステークホルダーに対しても、実現性の裏付けとなるだろう。これこそが、問題を俯瞰的に捉えた解決策であり、このモデルの最も革新的なポイントだ。ここが、疎外されたコミュニティが業界全体に参画していくための出発点となる。
疎外されたコミュニティにテック企業を誘致する場合、「事業価値」「社会的価値」「技術的な専門性」という3つの基盤が必要になる。これらは同等に重要だが両立がむずかしいものもある。どの領域に技術的専門性をフォーカスするかは、十分な市場ニーズがある分野を見極めたうえで、雇用ニーズと志望者の市場性をうまくマッピングする必要がある。最終的な選定は、事業所を設立するテック企業か中間支援組織が判断する。普通に考えると、一番ニーズがあるのは、品質保証(QA)や顧客サポートなど、必ずしも専門教育が必要ないサービス業務である。
一方で、この技術的な専門性は、テック業界が疎外されたコミュニティに門戸を開き、雇用や経済的流動性を改善しようとしていることをアピールできるものにすべきだ。従って、ソフトウェア開発の技能が必要な業務にフォーカスするのが望ましいといえるだろう。ビジネス面の課題と社会的な課題は、長い目で見れば最終的に相反するものではない。まずはそこまで高度な技能を必要としないソフトウェアサービスを採用し、疎外されたコミュニティの出身者がハイテク分野に参画するようになれば、ゆくゆくは収入の高い専門職に就職する人たちも増える可能性があるからだ。とはいえ、始めから両方を視野に入れておくことは重要だ。
ここで強調しておきたいのは、このモデルは、人件費の安い場を求めて海外などに出ていくオフショア開発モデルとは、明確に異なるということだ。テックインクルージョン・モデルの場合、従業員は同じ経済システムのなかで生活しており、主流派と同じ給与体系の対象となる。疎外されたコミュニティの近くに職場を置くのは、低賃金を当てにしてではなく、そのコミュニティ内でテック産業を活性化するためだ。
このモデルをいち早く導入するような企業の経営者は、マイノリティの雇用機会を拡大することの社会的、経済的な価値を重視する人物である可能性が高い。事業拠点の新規設立は常に困難を伴うものだが、疎外されたコミュニティで新しく立ち上げるとなれば、さらにハードルが高い。このため、このモデルを推進する起業家にはテック業界における豊富な経験が求められる。
このモデルの好例が、イスラエル人のカダー・アルシェイクとジオラ・ヤロンが創業したシラージ・テクノロジーズ(Siraj Technologies)だ。アラブ系遊牧民のベドウィン出身のアルシェイクは、2016年半ばにハイテクビジネスの起業家であるヤロンと出会う。イスラエルで急成長を遂げるテック業界と、ベドウィンのコミュニティの橋渡しとなることをしたいという思いで2人は意気投合した。
当時のイスラエルでは、パレスチナ人コミュニティとの共生がある程度進んでいたものの、南部に多く住むベドウィンはまだこの流れの恩恵にあずかってはいなかった。ベドウィンの社会・経済状況は悪化し、高校や大学で理工系に進む学生はどんどん減っていた。そこでアルシェイクとヤロンは、イスラエル南部でベドウィン出身のエンジニアたちを中心に採用するテック企業を立ち上げることにした。技術系の人材不足の問題と、ベドウィン出身の技術者が少ない問題の双方の解消をめざしたのだ。
最初に着手したのは、少数精鋭の取締役会をつくることだった。ユダヤ系とベドウィンの双方からハイテク業界の経験が豊富で顔の広い幹部クラスの人材を集め、ベドウィン出身者からは学歴の点でもロールモデルとなるような人物を探した。
2017年、たった4人のエンジニアをそろえ、IoT(モノのインターネット)に特化したスタートアップ、シラージ・テクノロジーズを立ち上げた。彼らは次のような意図をもって事業分野を選択した。
第一に、優秀なメンバーの顔ぶれが、ベドウィンのコミュニティから誕生した企業であることを物語っていた。この規模だと、品質保証のような単純業務のアウトソーシングを考えている企業には魅力的ではない。だが、技術開発にはうってつけで、少数精鋭の技術陣でも始められる。
第二に、高度な技術開発職であれば収入もよいはずなので、志願者の目には魅力的な仕事に映るし、就職できればコミュニティでも一目置かれるようになる。
第三に、IoTのような先進領域の事業を手がける企業であれば、市場でも注目されるし広報を通じて一般市民や政府の目に触れる機会が多くなる。そして、IoTは急成長分野とあってサポートなどの補完的なサービスが必要になるため、多くの補助業務を行う人たちの雇用や参画にもつながる。
シラージが創業地に選んだのは、ネゲブ砂漠にある最大の都市ベエルシェバだ。ここは「ネゲブの首都」とも呼ばれ、政府主導のハイテク産業集積地区が新設されていた。この都市出身のベドウィンは多く、ベドウィンコミュニティにとってはおなじみの街だ。
創業当初に直面した大きな課題の1 つが、顧客集めだった。この問題はどのスタートアップでも起こるが、これまで業界には見られなかった技術者を集めるシラージの場合、ハードルは余計に高かった。しかし創業者たちは、シラージの社会的な問題意識をうまく活用することで、共感してくれる経営者に働きかけられるだろうと見込んでいた。ここで彼らの知恵と経験が見事に功を奏した。普通なら人脈もなしに、最初の顧客を見つけることは不可能だったはずだ。
その後シラージ・テクノロジーズの事業は拡大していったが、ベドウィン出身の志望者が足りず成長の足かせになるという問題も生じた。そこで創業から1年後に、非営利団体のシラージNGOを設立した。シラージ・テクノロジーズ特有のニーズや技術に合わせて、人材の選抜、トレーニング、職業斡旋などの重要な支援を担う組織だ。志望者たちはシラージで使われている技術のトレーニングを受ける。また、大学生向けのテック業界への就職活動支援、高校生向けのテック業界の啓発活動、さらにベドウィンの一般成人向けに技術を普及する活動などにも取り組んでいる。
今やシラージは非常に重要な存在になっている。創業から5年近くが経過し、同社で働くエンジニアの数は24人にのぼる。これは、ベドウィン出身のテック企業への就職者の約半数だ。シラージは、ベドウィンのコミュニティに対して、以前までは存在しなかった雇用機会があることをはっきりと示し、就職者からはベドウィンのロールモデルになる人も出てきている。シラージの成果をさらに広げるため、シラージNGOでは交流会やハッカソンや学校訪問といった、コミュニティ向けのイベントも開催するようになった。イベントには、シラージで働くエンジニアの同年代の親戚が参加することも珍しくない。だからこそ、こうしたイベントで直接コミュニティの人たちと関わることは、ふつうの広報活動では得られないインパクトがあるのだ。
たとえば2020年に開催されたベドウィンの学生向けの大学交流イベントでは、マイノリティの利益向上に取り組むテック企業の拠点がそのコミュニティの近くにあるのが、いかに魅力的なことなのかがはっきりと示された。これは、少なくともマイノリティの人たちが業界に参画する初期段階では、特に重要な意味を持つ。
このイベントには2つのテック企業幹部が主賓として招かれていた。1つはシラージで、もう1つはアップルのイスラエル本社だ。イベントの終わりには、シラージのメンバーが学生らに囲まれて、同社での採用について質問攻めにあっていた。世界的に見ればアップルのほうが憧れの企業であるはずだが、ベドウィンの若者たちはそこまで惹かれなかったらしい。一方シラージは、現実的な就職先であり、温かく迎え入れてくれそうな雰囲気を醸し出していた。テックインクルージョン・モデルにおいてこうした要素は過小評価されるべきではない。
施策❷ 実践的トレーニングで能力開発を行う
業界が成長するためには、適切な資格を備えた人材が必要だ。資格とは学歴だけでなく、業界の流儀や作法の知識があることも指している。たとえば、プログラムを書くコーディング業務について考えてみよう。そこではとことんつくり込むよりも、開発のスピードのほうが重視されることが多い。また、チームで協力する能力も求められる。さらに日々の問題解決の場面では、プログラマーたちは最終的な答えを出すことよりも、課題となるイシューは何かを議論することを大切にする。
コミュニケーション能力やリーダーシップなどの重要なソフトスキルは、クラブ活動、若者支援プログラム、優秀な人たちが集う交流会など、課外活動や学校・会社以外の人間関係を通じて得られるものも多い。だが、こういった場の多くは、疎外されたコミュニティの人たちはアクセスできないようになっている。
この問題に対処するのが、テックインクルージョン・モデルの第二の施策である能力開発だ。大学などの正規教育では足りない部分を補完するもので、業界の実務や人間関係で必要なノウハウを伝えている。その実践の場となるのが、企業主導のトレーニングコースだ。協力企業は、現場で求められる専門知識や仕事の進め方、組織が重視している資質などを定義することでコース開発に関わっている。
トレーニングコースでは、協力企業の製品や技術の開発手法を習いながら、チームでの共同作業を模擬的に体験する。うまくいけば、参加者から何人か採用されるかもしれない。たとえ採用されなくても、参加者はトレーニングコースを通じて貴重な実践的な経験を積むことができ、将来の採用面接でも、技術的なことやプログラミングのリアルな現場について的確に語れるようになるだろう。実際に採用されたあとも、こうした経験があれば、新しい職場にいち早くなじめるだろう。
このトレーニングコースは、現場で教育するOJTと比較されることがある。OJTは、新技術への移行を目指す企業で、スタッフが素早く身につける必要があるときに利用されるものだ。一方のテックインクルージョン・モデルでは、コースの参加者は新たな技術の経験を積むだけでなく、業界での働き方を身につけることを重視している。たとえば評価に関していえば、試験を通じて従業員の能力を測るのではなく、仕事のパフォーマンスや成果について毎日あるいは定期的なタイミングで常にフィードバックされる。実際の現場では、1人のミスがプロジェクト全体の失敗につながることもある。ハイテク業界で働く人たちは、こうしたプレッシャーとの付き合い方をOJTやトレーニングコースで身につける。
実践的な能力開発を行う支援団体は、採用候補者の評価、選抜、育成面のサービスも実施できる。さらに、企業の技術責任者を呼んでコースの講師役になってもらったり、企業側のニーズを聞きながら研修内容を調整したりすることで、テック企業を巻き込んでいくこともできるだろう。
実践的なトレーニングを提供している団体の好例が、アメリカのパー・スコラス(Per Scholas)だ。1995年にニューヨーク州サウスブロンクスで設立して以来、これまでに全米14都市で活動を展開している。パー・スコラスは、ITのプロフェッショナルを目指す失業者や、希望や能力と合わない仕事に就いている潜在的失業者を対象に、無料の技術トレーニングを提供している。また、テック業界における適格人材が不足している問題(2020年にアメリカで100万人と推定)の対策、テック業界のダイバーシティ推進、疎外されたコミュニティ出身の優秀な人材の育成も目的としている。
パー・スコラスの主要事業は、パートナー企業と共同開発した独自のトレーニングコースだ。現場実践型の、業界での業務定義が明確な職種に対応するコースで、採用に関心ある企業との連携を重視し、企業での事例を活用し、企業の要件に合う教育を提供している。パー・スコラスは数十年で述べ1万4000 人以上のテック系人材を輩出している。
施策❸ 地域社会の理解を得る
テック業界で収入の高い就職機会が増えるとなれば、地元コミュニティが真っ先に飛びついて応援してくれるはずと思うかもしれないが、そう簡単にはいかない。疎外されたコミュニティでは、テック業界は「向こうのもので、こっちには縁がない」という声がよく聞かれる。こうした発言は、社会からの疎外感や、自分たちの仲間にそんなキャリアを目指す人などいないという思い込みを反映している。
また彼らは、テック業界にどんな企業があって、どんな職種があって、どんな人が活躍しているのかもよく知らない。筆者らは、世界的な大手ソフトウェア企業で働く、若手エンジニアの女性に話を聞いたことがある。彼女には教師と銀行員の姉妹がおり、両親はソフトウェアエンジニアになった彼女の経済的な先行きを最も案じているという。
テックインクルージョン・モデルでは、テック業界に進む人を大量に増やすためには、コミュニティからの理解や後押しがきわめて重要だと考えている。テック業界に就職したいと思う若者を増やすためには、この仕事は収入が高く、世間の評判も良くて、安定した職であるという認識をその両親や親族、そして経営者などコミュニティの有力者にも広げるよう働きかける必要がある。
そのために支援団体にできるのは、コミュニティの各方面向けに多種多様なイベントを企画して、技術面でも人間関係の面でも業界関係者と直接交流できる機会を設けることだ。高校生に対しては、テック業界に興味を持ってもらえるようなロールモデルの存在が不可欠だ。施策2 では地域に進出した企業が提供する教育トレーニングについて述べたが、こうした企業がハッカソンを企画したり、業界で活躍している人物が登壇するワークショップを主催したりすれば、より若者の関心を引くような機会となるだろう。他にも高校生による企業訪問や、高校生と企業で働く地元出身者との交流イベントなどを通じて、若者たちはこの業界に就職した場合の姿を想像しやすくなるだろう。
学生やトレーニングの修了者に役立つ取り組みとしては、交流会やハッカソン、合同企業説明会など、技術教育や就職をテーマにした交流イベントがある。こうした場を通じて、どんな企業や技術があるかの知識を得られるし、彼らが同じコミュニティ出身のロールモデルや業界リーダーと出会う機会となる。若者たちはそこで業界への理解を深めたり、地元の出身者から刺激を受けたりするだけでなく、業界の有力者と交流するなかで「発見」の喜びや安心感を覚える。一方企業にとっては、それまではアクセスできなかった、優秀なマイノリティ人材を知る機会になるのだ。
このような場で重要なのは、地元住民に影響力のある有力者を巻き込むことだ。彼らの協力を取りつけるために、たとえばこうした人たちをシンクタンクに招待してテック業界の著名人を紹介したり、イベントに登壇してもらったり、政府の委員会の委員として迎え入れたりすることで、1対1の関係性を築く。あるいは、既存のビジネス系の講演やセミナーに、テック業界のテーマを組み込んでもらうように働きかけることもできるだろう。
技術職への志望者を増やすためには、若者たちの親の世代に受け入れられることも大切な一歩である。疎外されたコミュニティの親世代には、経済や技術面での変化を直接体験していない人も多くいる。また、文化的に自分の子どもの職業選択については親世代が大きな発言権を持っている。このため、親世代の理解を得る活動はきわめて重要だが、これは簡単なことではない。だからこそ彼らの関心を引く証拠を集め、他のステークホルダーによる支持を足掛かりにするべきだ。もっとも、親世代に働きかけるのは先進企業がすでに地元で事業を展開していて、有力者たちの後ろ盾を得たあとのステップになるだろう。
モレンギーク(MolenGeek)は、ベルギーのブリュッセル近郊のモレンベークで活動する非営利団体で、「万人に門戸が開かれたテック業界」を目指し、疎外されたコミュニティを結んでテクノロジーのエコシステムを築こうとしている。モレンベークは、首都圏でも特に貧困層が多い地区で、住民の大半はモロッコ系を中心とする北アフリカ移民の2 世や3 世であり、失業率は40%にもなる。
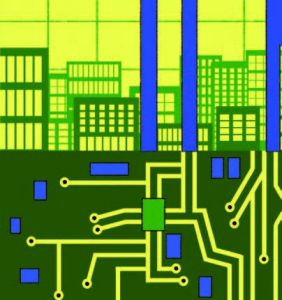
モレンギークは、複数の機能を一本化する活動に取り組んでいる。たとえば、通常利用できないようなハイテク企業レベルのオフィスサービスを備えたコワーキングスペースの利用を、地元出身の社会起業家に呼びかけている。そのコワーキングスペース内では、さまざまな期間のトレーニングプログラムを実施している。モレンギークの参加者以外、特にモレンベークの住民を対象にしたハッカソンや技術セミナーなどのイベントも精力的に開催している。
これらの取り組みを通じて、テック業界には仕事をする機会があるという認識がコミュニティに醸成されてきている。地元にコワーキングスペースという物理的なシンボルができれば、地域住民の目に触れるようになる。そして地元出身の若者や起業家が出入りしているという噂が広まる。やがて地元の若者やビジネスリーダーなど、興味を持つ人たちが交流会を通じてテック業界について知るようになる。さらに、テクノロジー関連のイベントには多くの参加者が集まるため、テック業界の関係者が地域の人材について理解を深める機会にもなる。
施策❹ 政府を巻き込む
テックインクルージョン・モデルで求められる4つめの施策は、政府の支援を取りつけ、テック業界におけるインクルージョンを社会的にも経済的にも持続させていくことを目指すものだ。疎外されたコミュニティ出身で経験の浅い人材のインクルージョンを推進するうえで、特に初期の取り組みに対して政府から積極的な協力を得ることは、その後に必要な追加対策を他のテック企業に働きかけるためにきわめて重要だ。未経験のエンジニアを採用するには、コストとリスクが伴う。見習い期間のコストと、志望者の一部が定着せずに終わるリスクである。しかも、疎外されたコミュニティ出身者が、よそ者意識を感じていたり、場合によっては敵対心まであったりすると、そのコストはさらに高くなる可能性がある。通常、フィランソロピーの助成事業において、民間企業が抱える追加のコストやリスクまで配慮することはない。そこまで面倒を見てくれるのは政府しかない。
疎外されたコミュニティ出身者の社会参画によって、政府が得られる利益は非常に大きい。それは社会的大義の達成となるだけでなく、テック業界の人材不足が深刻化する一方で、大量の失業者が存在しているという状況の解決にもなるからだ。その不足を補うために海外の人材を当てにしていたら国内の人材蓄積が一向に進まない。
一般に政府は、トレーニングや雇用斡旋事業には助成するが、雇用そのものを支援することはほとんどない。ハーバード大学国際開発センターが積極的な労働政策について幅広く調査した報告書によれば、賃金助成制度を盛り込んでいる政策は全体のわずか10%にとどまっていた4。同報告書では、賃金助成制度は、新規雇用や賃金アップの実現を促進する最も効果的な政府介入策だと述べられている。企業への支援にとどまらず、疎外されたコミュニティから新たに採用した従業員の所得も約11%増加する。これと対照的に、職業の斡旋や相談事業による所得の伸びは2%、職業訓練による所得の伸びは6.7%にとどまっていた5。
政府の支援を引き出すためには、プログラムの実現性への信頼度を高める必要がある。施策1で述べたような先進事例に学ぶのはその近道だろう。また、施策3で述べたコミュニティの啓発活動についても政府に情報を提供し、支援を要請すべきだ。そうすることで、インクルージョンの取り組みがもたらす大きな可能性について、政府関係者の理解を深められるだろう。
これらの活動は、施策2で述べたトレーニングや斡旋事業、あるいは企業の雇用コストをカバーするための財政的な支援を政府から引き出すのに役立つだろう。
疎外されたコミュニティのテック業界への参画を本格化するためには、上記4つの施策すべてを実行することが必要だ。単一の施策だけ、あるいは一部の施策だけを実行に移しても、その成果は限定的であり、このモデルが想定している大規模な変化にはつながらないからだ。
ビジネスセクターかソーシャルセクターかを問わず、起業家がテックインクルージョン・モデルに取り組むとき、すべての施策をゼロから取り掛かろうとすることもあるだろう。しかし必ずしも常にそうする必要はなく、すでに地域にある類似の活動を分析したうえで、4つの施策のうちどれが実行されていないのかを特定し、足りない部分を補うことで既存のプロセスを最適化していく、という手もあるだろう。
成功の前提条件
テックインクルージョン・モデルが実のある社会変化をもたらすためには、いくつかの条件が前提となる。第一に、業界で技術系の人材が大幅に不足していること。このモデルはまさにこの問題の解決に焦点を当てているからだ。ここから出発して、実際のビジネス上のニーズや価値を明らかにし、対処することになる。
第二に、疎外されたコミュニティで、STEM(科学、技術、工学、数学)分野専攻の高校以上の卒業者の割合が大きくなければならない。プロジェクト開始の時点で、高度なSTEM教育を受けていながら、それに見合った仕事に就いていない人材が、集団として存在している必要があるだろう。この人たちが先進企業への志望者候補となる。
ツォーフェンは、大学でSTEM教育を受けていながら不相応な職に甘んじている人材と、業界の極端な人材不足のマッチングを実現している好例だ。もっとも、地域に進出したテック企業の雇用条件として学歴が重視されなければ、この条件はそこまで重要ではなくなる。
幸い、テック業界が人材に求める要件は一様ではなく、テクノロジーの進化やオートメーションの普及によって、ますます多様になっている。実際に専門的技術が必要とされない職種での雇用も拡大している。疎外されたコミュニティ出身者にとっては、この種の仕事でもコミュニティ内の平均よりも高い賃金がもらえる。たとえば品質保証や技術サポート、ウェブコンテンツ開発やモニタリングなどの職種だ。金融機関や行政機関では、自動化システム用に大量の保守要員を必要としている。伝統的な業界でも自動化が進むなかで、生産業務は学位こそ不要だが、熟練を要する仕事になっている。このため、一定の条件がそろえば、地元に進出したテック企業に高学歴というハードルがない場合、テックインクルージョン・モデルは、非常にうまく機能するだろう。
第三に、テックインクルージョン・モデルは、疎外されたコミュニティが地理的に1 つのエリアに集中している場合に効果的だ。コミュニティ内の人々の距離が近いほど、若者に対しても、親世代や一般市民に対しても、働きかけの効果は高まるはずだ。
さらに、こうした役割を担う支援団体には、テック業界の有力者にも参画してもらう必要がある。善意の支援団体が企業に働きかけようとしても、ビジネス面や技術面の課題に対応できなかったり、専門的、社会的な信頼関係を築けずに終わったりすることも少なくない。団体の創設者や理事にビジネス面や技術面で実績のある人がいれば、個人のネットワークを駆使して、確かな信頼関係を足掛かりに企業を巻き込んでいくことも可能になる。また、団体側に技術やビジネスに精通したメンバーがいれば、トレーニングや斡旋事業を企業ニーズに合わせて調整することもできる。
こうした条件がそろえば、テックインクルージョン・モデルはうまく機能するだろう。ひとたびインクルージョンが広がっていけば、4つの施策のそれぞれの重要度は異なってくる。たとえば、コミュニティ外の企業への就職のハードルも低くなるはずだ。その次の段階に円滑に移行するには、まずはコミュニティ出身でテック業界に就職した人たちの人数が一定の規模に達していなければならない。同時に、コミュニティ内で事業展開するテック企業が誕生している必要がある。この2つの条件がそろえば、テック業界に対するコミュニティの信頼は深まっていくし、学歴についての考え方や選択の仕方も変わっていくだろう。
もちろん、テックインクルージョン・モデルだけで、社会を変えることはできない。不平等と分断の問題には、根本的な解決策が求められる。しかし、テック業界が活性化している地域では、テックインクルージョン・モデルを活用することで、産業から生まれる利益をより多くの人々が分かち合えるようになるはずだ。疎外されたコミュニティがどうしようもないほどの貧困にあえぐ一方で、テック業界には桁外れの富があふれている。しかもその格差はますます広がっている。テックインクルージョン・モデルは、これを食い止める1つの手段である。
【翻訳】斎藤栄一郎
【原題】Tech Inclusion for Excluded Communities(Stanford Social Innovation Review, Summer 2022)
【画像】Illustration by Claire Merchlinsky
1.本記事に登場するすべての関係者の氏名は、個人が特定されるのを防ぐため仮名を使用している。
2.Israel Central Bureau of Statistics, “ICT Sector Estimate for 2015,” September 7, 2016.
3.Israel Innovation Authority and Start-Up Nation Central, High-Tech Human Capital Report 2019.
4.Eduardo Levy Yeyati, Martín Montané, and Luca Sartorio, “What Works for Active Labor Market Policies?” Center for International Development at Harvard University, Faculty Working Paper No. 358, 2019.
5.賃金助成制度の効果について評価が高まっている。たとえば、OECD Socialは2021年9月21日、OECD加盟国のうち、企業による若者の雇用を後押しするために雇用助成金を導入または拡充した国は3分の1 に上るとツイートしている。
Copyright ©2022 by Leland Stanford Jr. University All Rights Reserved.


