社会的インパクトを生むためには、多様なステークホルダーをつなぐネットワークが欠かせない。しかしネットワークだからこそ直面する危機があり、それを乗り越えるためには日常からの備えが必要だ。
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 04 コレクティブ・インパクトの新潮流と社会実装』より転載したものです。
ミシェル・シューメート|キャサリン・R・クーパー
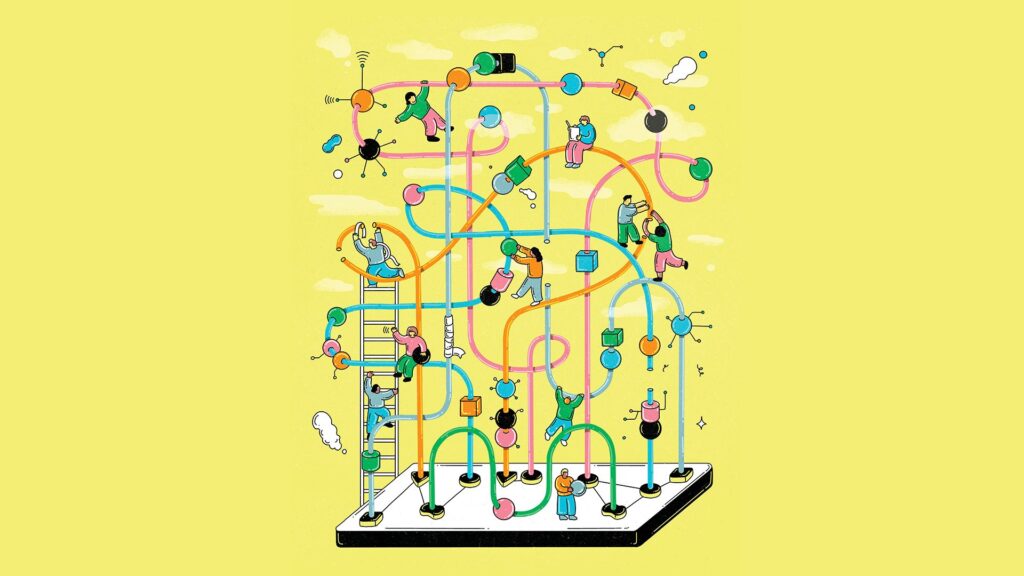
本稿の共著者であるミシェル・シューメートが訪問したシェアオフィスは、広くてモダンな装いだった。そこには、ザ・リテラシー・オーガニゼーション(仮名)に加盟する多くの団体が拠点を置いていた。
ザ・リテラシー・オーガニゼーションは、100を超える教育関係の非営利団体からなるネットワーク組織である。
ミシェルはオフィスを見学した後、同ネットワーク事務局長のジェリー(仮名)とともに役員会議室に向かい、ある相談をもちかけられた1。2人は運営費やインパクト測定の方法など、ネットワーク組織にありがちな課題について話し合った。実はジェリーは、自分たちのネットワークが生み出している社会的インパクトの評価・測定をミシェルに手伝ってもらいたいと考えていた。
しかし残念ながら、ミシェルはこう言った。「このネットワークの掲げるミッションにも共感しますし、オフィスも素晴らしい環境です。ただ、ひいき目に見ても、このネットワークの実際の活動は、みなさんが自分たちで言っているほどの社会的インパクトを生んではいないと思います。ネットワークの加盟団体は個別ではインパクトを生み出せているのかもしれませんが、全体としては生み出せていないでしょう」。
ミシェルは代案として、ザ・リテラシー・オーガニゼーションが参加団体向けに実施しているキャパシティビルディング(組織能力の開発)がこのネットワークの真の価値だと思うので、それを評価・測定することなら協力できると申し出た。ただし、「市全体の教育面のアウトカム(成果)向上」という社会的インパクトをザ・リテラシー・オーガニゼーションの功績とうたうことは不誠実に思える、と釘を刺した。
ジェリーたちが資金提供者やネットワークへの参加を検討中の団体を得意気に案内していた素晴らしいシェアオフィスは、このミーティングからほどなくして、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)拡大の影響で閉鎖された。そして、2020年5月25日にジョージ・フロイドが殺害されたことを受けて黒人差別への抗議運動が広まると、このネットワークの加盟団体の人種構成が白人に偏っていることが露呈し、多様な人種や経済状況の人が住む市において、白人ばかりのメンバーで格差の是正に取り組んで果たして社会的インパクトをもたらせているのかを問い直す必要に迫られた。さらに、ある大口資金提供者が経営危機のため寄付を減額してネットワークの運営費が逼迫した。こうした事態が重なった結果、経営再生の目処が立たなくなり、ジェリーなど立ち上げに携わったリーダーたちの願いもむなしくネットワークは解散した。
このような話は珍しくない。私たちは数十年にわたって、社会的インパクトを目指して結成されたネットワークや共同プロジェクトなど数百の事例を調査してきた。その一部が複数年にわたる50以上のコミュニティ密着型ネットワークの変遷調査2 であり、『社会的インパクトを目指すネットワーク』(Networks for Social Impact)という本にまとめられている3。近年の研究から明らかになったのは、多くのネットワークが、重要な決断を迫られる「存亡の岐路」とも言える局面を経験していたことだった。その局面とは、単に「メンバーの退職」や「新しい活動の立ち上げ」にまつわるありがちな課題でもなく、必ずしもパンデミックのような社会レベルの混乱に影響を受けたものでもない。しかし、いずれの状況もネットワークの存続が危ぶまれるような局面だった。
社会的インパクトを目指すネットワークは、どうすれば存亡の岐路を切り抜け、成功までたどり着けるのか。私たちの研究からわかったのは、ほぼすべてのネットワークは存亡の岐路を免れられないが、以前にどんな意思決定を行ってきたかが、そのときの選択やその後のアウトカムに影響するということだ。レジリエンスの高いネットワークは、日々の活動のなかで、危機的な状況に直面してもあらゆる問題に対処できるように準備を進めている。たとえば、「特定の人間にリーダーシップが集中するのを避けて分散する」「セオリー・オブ・チェンジ(変化の方法論)を明確にする」「自分たちのリソースに合わせてトラブルに効果的に対処するための戦略をつくる」といったことを行っている。そして、いざこうした状況に直面しても生き残ったネットワークのリーダーたちは、現実と正面から向き合い、どんな問題に対しても解決策を導き出しながら組織を前進させていた。
社会的インパクトを目指すネットワークとは何か
「社会的インパクトを目指すネットワーク」とは、共通の目的にフォーカスした、3つ以上の組織からなるグループを指す。ネットワークという形態は、各参加組織の自治と相互依存の板挟みになりやすい。そのため、存亡の岐路への対応は、各組織レベルでの対応よりもはるかに難しいものとなる。というのも、ネットワークのリーダーたちは、個別の組織のリーダーと同様の責任をすべて負っているにもかかわらず、同様の権限を持っていることはほとんどないからだ。
ネットワークのデザインの方法論は、従来型の組織デザインほど一般化されていないため、ネットワークごとにさまざまな違いがある。数百という加盟団体数を誇るネットワークもあれば、数団体のネットワークもある。事業者だけで構成されるものもあれば、企業や政府機関を含むものもある。全体のマネジメントを統括するバックボーン組織を設置するネットワークもあれば、小規模なネットワークや地元住民が参加するネットワークで見られるように、共同で意思決定するものもある。さらに、地元のリーダーが地域の重要課題を解決すべく立ち上げたネットワークや、特定の課題解決を掲げて全国の地域リーダーと協働する大規模なネットワークもある。後者はアメリカサーブ(AmericaServes)、ストライブ・トゥギャザー(StriveTogether)、「初等教育レベルの読解力キャンペーン(The Campaign for Grade-Level Reading)」などだ。
こうしたネットワークを比較すると、最も重要なデザイン上の違いは、どのように社会課題に取り組むかを表すセオリー・オブ・チェンジである。セオリー・オブ・チェンジは単一の場合もあれば複数の場合もある。
複数ある場合は、同時進行型と段階型のアプローチがある。規模が大きい、あるいは資金が潤沢なネットワークであれば、十分なリソースを活かして複数の戦略を同時に進めることができる。あるいは、課題への理解を深めながらセオリー・オブ・チェンジを変えていくネットワークもあるだろう。私たちの書籍で整理した、多くのネットワークが採用している5つのセオリー・オブ・チェンジのモデルについて見ていこう。
●プロジェクトモデル
ネットワークの協働によって新たなプログラムや製品を生み出し、提供するモデル。たとえば、レディ・セット・ペアレント!(Ready, Set, Parent!)は、新米の親を支援するプログラムを展開するネットワークで、エブリー・パーソン・インフルエンス・チルドレン(Every Person Infl uences Children, EPIC)、ベイカー・ビクトリー・サービス(Baker Victory Services)、カトリック・ヘルス(Catholic Health)などによって共同結成された。プロジェクトモデルは、5つの変化の方法論のなかでは最もシンプルだ。目的が明確な新プロジェクトを立ち上げるためにネットワークを結成し、そのプロジェクトが完了すれば解散するか縮小する。
ネットワークが生み出す社会的インパクトは、プログラムの質またはサービス次第である。
●カタリスト(触媒)モデル
高い効果が見込まれる解決策の規模拡大を目指すモデル。個別の組織単位でも解決策の規模拡大には取り組むが、カタリストモデルのネットワークは組織横断型の解決策に取り組むことができる。このモデルの好例が「卒業!ネットワーク(The Graduate! Network)」だ。このネットワークは、過去に大学を中退したが再挑戦する「カムバッカー」の学位取得を支援するためのコミュニティをつくることを目指して設立された。参加メンバーは、カレッジリーダー(大学で学生たちのキャンパスライフや進路などをサポートするために選出された在校生)、地元の資金提供者や経済団体、労働力投資委員会(Workforce Investment Boards,WIBs)、人材獲得に関心のある企業、関連自治体のリーダーたち、消費者金融相談機関、また、図書館などの公共施設、さらには地元の非営利団体などである。もともとフィラデルフィアで始まったこのネットワークは、いまでは41の地域で展開され、のべ8 万人のカムバッカーを支援している。
●政策モデル
カタリストモデルとは対照的に、政策モデルは直接または草の根レベルのロビイングによって法律や規制を変えることを目指す。このモデルは、法律や規制の改革を訴えるアドボカシー活動が成功した場合に社会的インパクトを生み出すことができる。その一例が、2004年に設立され、米国中西部全域に130 を超える参加団体を擁するリ・アンプ(RE-AMP)だ。このネットワークの目標は、地域にとって不公正をもたらすことなくアメリカ中西部の温室効果ガスの排出量を減らすことだ。州レベルのアドボカシー活動によって、この地方で産出される再生可能エネルギーの量を増やし、石炭火力発電所の新規建設を阻止し、既存の石炭火力発電所を廃止するという政策を後押しした。
リ・アンプのように政策モデルをとるネットワークは、かなり大規模になる場合が多く、個人や組織の協力を促すために共同キャンペーンを展開している。リ・アンプでは、特定の州規制の改革に集中的に取り組んだだけでなく、各州での取り組みを連携させた。こうしたネットワークを通じた集合的なアクションは、組織単独での取り組みよりも大きな成果をもたらす。
●学習モデル
さまざまな組織による既存サービスの質の向上を目指すモデル。全米規模の「子どもを見守るコミュニティセンター(The Center for Communities That Care)」が一例だ。このネットワークは、エビデンスに基づいた取り組みについて学ぶことで、薬物乱用など若者の危険な行動を減らす解決策を考える活動を行っている。そこで重視しているのが学校、医療保健、非営利団体、司法制度、あるいは地方自治体などの地域コミュニティにおけるリーダーだ。このモデルの社会的インパクトは、参加団体がどれだけ学び、またそれを実践に活かせるかにかかっている。ネットワークという形態が個別の組織よりも優れているのは、多くの類似する組織からパフォーマンスや活動に関するデータを集めて比較できる点だ(個別の組織がデータを収集する場合、多くは自組織の過去のデータが基準になりがちだ)。
他の事例としてシカゴ・ベンチマーキング・コラボレーティブ(Chicago Benchmarking Collaborative) も、参加団体ごとに目標や事業対象が異なるにもかかわらず、比較学習型の手法を用いている。
参加団体の支援対象は、成人から幼児までと幅広い。また、それぞれ異なる地区で活動しているため、ターゲットの人種や民族性や母語なども違ってくる。ところがこのネットワークでは、参加団体同士の活動理解にとどまらず、お互いの活動を組み合わせることでシカゴ全体により大きな変化を起こせるのではないかと考え、その方法を模索した。
そこで、組織横断的に測定できそうなプログラム面や教育面のアウトカムを洗い出した。彼らはさらに、活動実績を共有してそのアウトカムを分析し、共通の目標を設定した。そして、それぞれの参加団体が、他の組織から学んだ実践手法を自分たちの組織に取り入れた。こうしたネットワークレベルの取り組みを通じて、参加団体はしっかりとデータを比較できるようになり、より的確に自分たちのアウトカムへの理解を深め、他組織の戦略を学んで活用できるようになった。その結果、各団体の支援対象者の教育面におけるアウトカムが向上した。
●システム連携モデル
既存のサービスが届かない空白地帯に対して、参加団体による共同事業をコーディネートするモデル。特徴は、他の4モデルよりも大きなシステムレベルの観点に立って、組織間の比較や調整を行う点だ。そのため、より包括的で、個々の組織の受益者よりも広い対象を支援するアプローチとなり、組織レベルの活動が削減、統合または変更される場合がある。システム連携モデルが社会的インパクトを生むのは、プログラム間の連携を通じてターゲット集団全体におけるアウトカムが向上した場合に限られる。
近年、アメリカの連邦政府は、福祉システムにおける連携の取り組みに資金を投じているが、これは、より多くのネットワークがシステム連携を図っていることを示唆している4。たとえば、アメリカの住宅都市開発省による「ケアの連続体(Continuum of Care)」プログラムは、ホームレス状態の個人や世帯に対して新たな住居をすばやく提供することを目的とする、住宅供給者のネットワークである。保健福祉省のメディケア・メディケイド・サービスセンター(Centers for Medicare & Medicaid Services)が発表した「合衆国のためのロードマップ(Roadmap for States)」では、社会保障法の1115条に定められた免除規定〔州政府が連邦政府の承認を得れば、通常のメディケイドより踏み込んだ革新的なプログラムを実施することが可能となる〕の活用方法を解説している。これを利用すれば、それぞれのネットワークが給付内容、プログラム、サービスを調整しながら、健康の社会的決定要因に働きかける独自の取り組みを進めることが可能となる。
たとえばアメリカサーブは、退役軍人、軍の仕事をしているが民間に転職しようとしている人、さらには軍関係者の家族などへの支援を行う11のネットワークをサポートしている。その一環として、これらのネットワークの参加団体に寄せられる問い合わせに確実に対応できるようなシステムを構築した。非公開型のデジタルテクノロジーを使ったこのシステムで、ネットワーク内のリソースを共有し、すべての状況が追跡できるようになった5。各ネットワークの連絡センターで問い合わせ案件の追跡をしているため、どの団体からでもより迅速かつ的確に回答することができる。このネットワークに参加している、ある退役軍人支援団体が問い合わせに対応するまでの平均所要時間は48時間未満だ。ネットワークに参加していない同様の組織ではどこも順番待ちになってしまうことを思えば、飛躍的な改善である。
アメリカサーブに参加する組織は個別に新しいプログラムやサービスを立ち上げるのではなく、既存サービスへのアクセスやサービス間の連携を改善している。これがシステム連携モデルである。
ネットワークとは、同じ社会課題への関心を持つ組織が集まり、自分たちが協働することでインパクトを生み出せると確信したときにつくられるものだ。初期の頃はしっかりしたセオリー・オブ・チェンジさえあれば参加団体と資金は集まるだろう。しかしながら、ひとたび活動が軌道に乗ると、ネットワークは変化を経験する。
その変化にどう対応するか。ネットワーク設立時に資金提供者や支援対象者に表明したことを前提としたセオリー・オブ・チェンジを維持する場合もある。
あるいは、1つか2つのセオリー・オブ・チェンジに落ち着くまで、いくつかのアプローチを試しながら、自分たちの活動現場で何がうまくいくのかへの理解を深めようとするネットワークもある。また、学習を通じてモデルを更新しながら成熟していくネットワークもある。
ネットワークが内的・外的変化に対応していく際には、このような動きが起きるものだ。ところが存亡の岐路の局面は、これらの変化とはまったく異なるものだ。
そのときネットワークは、「これまで行ってきた運営方針に関するあらゆる判断がまちがっていたのではないか」「現状のやり方ではインパクトを生めるまで存続できないのではないか」と疑問を抱くことになる。
5つの岐路
ネットワークは常に変化している。
新規参入もあれば離脱もあり、リソースや外部環境も変わっていく。世論、政局、司法判断などが問題や解決策に関する私たちの考え方に影響を及ぼしながら、社会課題自体も変化していく。ネットワークの運営者はこうした変化や今後生じうる課題を見越してそれを乗り越えるための戦略的なプランを立てる。
存亡の岐路とは、こうした想定範囲内の課題と違って、根本的で破壊的な、ネットワークの存在意義を問うような状況のことである。これについて、デボラ・アゴスティノ、ミシェラ・アルナボルディ、マルチナ・ダル・モリンは公的なネットワークの研究成果を発表した共同論文において、「存亡の岐路を乗り越えることができれば、新しいコラボレーションの段階へと進めるだろう。乗り越えられない場合、コラボレーションそのものが消え去ってしまうことになる」と述べた6。私たちは、過去5 年間の研究から、ネットワークが直面する5種類の存亡の岐路を見出した。すべてを経験することはあまりないものの、ほぼすべてのネットワークが少なくとも1 つは経験する。
❶資金提供者が支援を大幅にカットする
社会的インパクトを目指すネットワークの多くが、初期の数年間は助成金に依存している。助成金があることで、少数の組織が無償で行っていた活動の規模を拡大し、ネットワークの運営専任者を雇用できるようになる。ただし、助成金に依存したままだと、不安定な財務状態から抜け出せない可能性がある。
ネットワークがさらに成長しても、単一の資金提供者に依存した活動を続けていると、いずれ存亡の岐
路に立たされることになる。こうした資金提供者は、ネットワーク立ち上げに直接関わっていたり、設立当初からの支援者であったりすることが多い。その関係が終われば、ネットワークは危機的状況に陥ってしまうのだ。
ミシガン州で教育面のアウトカム向上に取り組むフリント・アンド・ジェネシー・リテラシー・ネットワーク(Flint and Genesee Literacy Network)は、リーダー交代と同じタイミングで連邦政府からの助成が打ち切られた。そこでどうすれば大口の資金提供なしで活動を続けられるかを大至急考えなければならなくなり、地元のコミュニティカレッジで働きながら学んでいる学生や市民とボランティア活動との橋渡しをするアメリコー(AmeriCorps)プログラムの参加者などを巻き込んだ、プロジェクトベースのセオリー・オブ・チェンジへと方向転換した。
❷社会の大きな変化によって活動が根底から覆される
アメリカのネットワークは、過去2年間で2つの重大な出来事に直面した。1 つはCOVID-19の感染拡大、そしてもう1つが、ジョージ・フロイド殺害をきっかけに全米に波及した、人種差別撲滅を目指すブラック・ライブズ・マター(BLM)のムーブメントだ。前者によって、現場のプログラムやサービスの多くが、対面で実施できない期間は中断するかオンラインで実施するしかなかった。また、食料不足や、子どもたちの学習用インターネット環境の整備などの新たなニーズの高まりに対応すべく、一部のネットワークとその参加団体は新しい活動を考えなければならなかった。一方BLMによって、ネットワークには誰が関わっているのか、そしてこれらのネットワークが支援対象としているのは誰なのかについて、厳しく問い直されることになった。
私たちが協働したネットワーク(とりわけ義務教育課程の児童・生徒を対象とする教育関連団体)の多くが、過去2年のうちに岐路に立たされた。たとえば、多くの「地域カレッジ進学ネットワーク(Local College Access Networks, LCANs)」が外出自粛期間中は一切の活動を停止した。このような、高等教育への進学を支援するコミュニティ密着型のネットワークは、企業、自治体、地域住民、そして教育分野のリーダーたちと密に連携しながら活動している。LCANsが提携していた学区や学校の多くがCOVID-19関連の危機に直面していたため、高等教育への進学支援に時間とエネルギーを割くことがもはやできなくなっていた。
❸ビジョンを掲げたリーダーが去る
リーダーの交代によって、ネットワークが存亡の岐路に立たされることもある。特にカリスマ的存在、すなわち、創設者やビジョナリーリーダーを失ったときの状況はより深刻だ。もちろんネットワークは、協調的、集合的に運営されるものだが、社会変化を目指す取り組みには周囲の人たちを巻き込めるようなリーダーがいるものだ。
ネットワークの参加団体や資金提供者は、カリスマ的存在が去れば、ネットワーク全体のビジョンも失われてしまうと考えるかもしれない。リーダーが去れば必然的に、資金や人脈も失ってしまうのではないかと危惧することもあるだろう。また、残されたメンバーは自分たちにはリーダーほどの情熱や経験がないのでネットワークの当初の目標を達成できないのではないか、と弱気になりやすい。教育ベースのネットワークであるピッツフィールド・プロミス(Pittsfield Promise)では、中心となっていたリーダーが数人去ったことで、他にも離脱者が出るのではないかという懸念が生じた。もともと参加している団体の多くが、このとき去ったリーダーたちから口説き落とされてネットワークに加わっていたからだ。そのためネットワークにとどまる意欲や必要性を疑問視する団体も出てきた。
❹ 1 つの強力な組織に
ネットワーク全体の活動が吸収されるネットワークのリーダーは、参加団体のうち力のあるところとそうでないところの板挟みになりやすい。ネットワークは組織間の任意の合意に基づいているため、全体のマネジメントを行う存在がいたとしても、たいていは個別の参加団体に対する権限は限定的である。
ときには、ネットワーク内でより強い組織がネットワーク全体の活動を吸収することもある。その背景には、大まかにいって次の2つの考えがある。ネットワークの活動が自分たちの組織のコア・コンピタンスと重なっている、もしくは自分たちの組織単独でその事業を運営するほうが効率的である、というものだ。私たちが調査した2つの教育ネットワークは、いずれも学区によって吸収された。コネチカット州のハートフォード・パートナーシップ・フォー・スチューデント・サクセス(Hartford Partnership for Student Success)の場合、学区の新任教育長がこのネットワークのコミュニティスクールのプロジェクトに非常に感銘を受け、学区がこの活動を吸収して資金も提供するという決定をした。この教育長は他の学校にもプロジェクトを拡大し、サービスを受ける生徒数も大幅に増加した。これによってプロジェクト自体は各学校で続いていくことにはなったが、ネットワークの役割は減った。同様に、ニューヨーク州マウントバーノンのマイ・ブラザーズ・キーパー(My Brother’s Keeper)は、州の助成先である学区がその活動を一手に引き受けた。学区は、支援を受け続けるために結果を出すことを迫られていたので、ネットワークの多様な組織や共同プログラムと連携するよりも、自分たちでプログラムを回すほうが効率がいいと考えたのだ。
❺過剰なミーティングで燃え尽き症候群になる
私たちが調査したネットワークの多くは、自分たちは矛盾する要求に応えようとしている、という認識
を持っている。最もよくあるジレンマとして挙げられるのが、ネットワークを専門とする研究者が「ネットワークの効率化とインクルージョンの対立」と呼ぶものだ7。目に見える社会の変化を求めているコ
ミュニティに対してネットワークの活動が前進していることを示す小さな成功例を示したくても、多く
のステークホルダーが関与しているとネットワークのなかで何かをすばやく立ち上げるのは難しい、ということである。
このジレンマを克服するために多くのネットワークがとった判断は、希望するステークホルダーが参加可能な定例ミーティングを開催することだった。短期的に見ると、こうした集まりは人々の意欲を高めるし、全員に開かれていることで透明性やインクルージョンが確保されているという感覚を与えてくれる。一方で、こうしたミーティングは時間がかかる。しかも、ネットワーク側が、できるだけ誰もが参加しやすい時間と場所でミーティングを設定しようと最善を尽くしても、すべてに出席できる人はいない。このことが長期的にはメンバーの燃え尽き症候群につながることがある。
ここで、幼少期から大学、そしてキャリア形成準備まで、教育面のアウトカム向上を目指すコミュニティ密着型ネットワークのエデュケーション・フォー・オール(仮名)の事例を見てみたい8。このネットワークは、参加団体も地域住民も参加しやすいネットワークを目指して、3種類の集まりを設けた。「参加団体のリーダーたちがそれぞれの活動に関する意思決定を行うためのミーティング」「ネットワークの活動にあまり関わっていなくても最新情報を得たい人が参加できる、大規模な情報共有ミーティン
グ」「ネットワークに積極的に関わる意欲のある組織や地域住民がアクションチームをつくって話し合
うミーティング」である。
さらに、ミーティングを欠席した人の不安に配慮して、情報共有ミーティングの前に非公式のキャッチアップの場を設けることまで行った。つまり、前回のミーティングの内容を把握するためのミーティングだ。このような取り組みを通じて多様な人々のインクルージョンを目指していたものの、最終的には「ミーティング疲れ」が参加者たちに悪影響を及ぼしていることを、ネットワークの運営者は認めざるを得なかった。
そもそもネットワークはメンバーの入れ替わりが激しいことが私たちの研究でも既に明らかになっている9。参加方法がたくさんあるにもかかわらず、どんなミーティング形態をとってもネットワークの全ステークホルダーの参加やインクルージョンを実現するのは無理である。エデュケーション・フォー・オールの運営者は、一部の参加者から「このネットワークは活動が前進しなくても、多様な人を受け入れるミーティングができていれば満足なようだ」と見られていると知って落胆した。運営者はネットワークの活動について議論する場を設け、地域住民の参加を呼びかけたが、そこで明らかになったのが、「誰でも参加自由」というミーティングのあり方が出席者の意欲を削ぐという点だけだった。すなわち、地域住民の多くが、このネットワークは社会変化を生むのではなく、「ただ話すだけ」と感じていたのである。
日常から危機に備える
メンバーの疲弊や資金源の喪失といった存亡の岐路に直面したとき、ネットワークの将来は危うくなる。
対応策は、運営方法を大幅に変えるか解散するしかないように思える。ところが、私たちが調査したネットワークのなかには、存亡の岐路に直面する前からレジリエンスを高めるための活動を行っていたところもあった。具体的には、「ネットワークの中央集権化」「曖昧なセオリー・オブ・チェンジ」「コンフリクトマネジメント(対立への対処法)の軽視」がもたらすリスクを回避することに重点的に取り組んでいたのだ。レジリエンスの高いネットワークは、存亡の岐路が及ぼすダメージから身を守るための投資をしている。私たちは、効果のあった方法を整理して導き出した3つの戦略を提唱したい。
❶リーダーシップの分散を検討する
変革を主導してきたリーダーや創設者のような重要メンバーの入れ替わりがあっても、レジリエンスの高いネットワークであれば耐えられる。研究対象のなかには、中央集権的なリーダーシップに依存していたネットワークがあった。たいていは「バックボーン」とも称される中心組織への依存度が大きいネットワークで、中心組織のリーダーが他のメンバーと協議して最終的な意思決定を行う。こうしたネットワークは、リーダーの交代によって混乱に陥りがちだ10。
一方で、リーダーシップが分散された体制によって分権的なガバナンスを行っているネットワークもあった。私たちの研究からは、後者のようなネットワークのほうが、存亡の岐路によるダメージに強いことがわかった。ノースカロライナ州オレンジ郡で貧困の連鎖を止めることを目指して活動するファミリー・サクセス・アライアンス(Family Success A lliance, FSA)と、アイオワ州マーシャルタウンで活動する「初等教育レベルの読解力キャンペーン(Campaign for Grade-Level Reading, CGLR)」を見てみよう。両ネットワークとも、権力を分散させた体制をとっているので、中心的リーダーたちが抜けてもネットワーク活動を続けることが可能だ。また、リーダーシップの分散の一環として、異なるタイプのステークホルダーのエンパワメントも実施していた。たとえばFSAは、プログラムの策定や運営を参加団体に担ってもらったり、保護者会など地域住民側のステークホルダーに関わってもらったりすることで、さまざまな関係者にリーダーとしての役割を分散させ、1 人の人間にネットワークの顔としての役割を与えることはしなかった。CGLR は、地域住民との連携を強化する取り組みや人間関係の構築を実施していたため、立ち上げに関わったリーダー(地元団体を40年経営した有力者)が引退した後もネットワークを存続できた。
❷変化の方法論を明確化し、リソース状況との整合性をとる
自分たちの活動が実現したい社会的インパクトにどのようにつながるのかを、一度も明確化したことのないネットワークもある。ネットワークはセオリー・オブ・チェンジを明確にすることで、資金調達、リーダーシップ、組織運営などにおける変化を乗り切りやすくなる。また、当初の計画を変更すべき状況になっても、どうすれば自分たちのセオリー・オブ・チェンジから外れずに活動を続けられるかを問うことができる。
まずは、5つのセオリー・オブ・チェンジからどれを採用するかの検討から始めるべきだが、そこで終わりではない。強固なネットワークは、先に目標を定めてからその目標に対してどんな活動のアウトプットを出せば目標に近づけるかを逆算することで、セオリー・オブ・チェンジの全体像を描いている11。特に強固なネットワークの場合、自分たちのセオリー・オブ・チェンジの妥当性を試すため、成功の先行指標と遅行指標を定義している。
このようなプロセスを通じてネットワークのリーダーたちは、手元にあるリソースと今後得られるであろうリソースがセオリー・オブ・チェンジに見合ったものであるかを見極めていく。一般的に存亡の岐路の背後には、リソースの変動や、ネットワーク参加団体あるいは地域コミュニティとの対立があることが多い。それを踏まえてネットワークを維持するために必要なリソースがあるかを日頃から考えておいたほうがよいだろう。現代社会において、非営利団体や社会的インパクトを目指す活動では、より多くの仕事をより少ないリソースで実施することがますます求められるようになっている。こうした状況において、セオリー・オブ・チェンジを1つに絞り込むことでジレンマから解放される場合もある。うまくいっていない活動を手放して、うまくいく活動に集中できるようになるからだ。明確なセオリー・オブ・チェンジは、ネットワークへの支援や評価に関わる資金提供者や支援対象コミュニティに対するアカウンタビリティにもつながる。
プロジェクトモデルのセオリー・オブ・チェンジの場合は必要なリソースが比較的少なくてすむので、プロジェクトはいずれ、ネットワークから独立して運営できるようになる。対照的に、システム連携モデルには長期的な視点が必要だ。ネットワークが短期的な助成を受けている場合や行政側の重要人物が参加していない場合に、システム連携モデルを採用しようとするとネットワークが不安定になるだろう。自分たちのセオリー・オブ・チェンジに見合ったリソースを持たないネットワークは、資本不足の企業のように解散する危険度が増す。
❸対立への対処法を確立する
私たちは長年にわたってネットワークを研究してきて、ときに参加者側に回ることもあったが、その経験から言えるのは、ネットワークでは参加者の善意を過大評価しがちであるということだ。たとえば、「教育や保健の質を向上させたいという共通の関心事項があれば、今後生じうるあらゆる対立や意見の相違を乗り越えられる強さがあるはずだ」と多くの人が思い込んでしまう。
ネットワークという性質上、対立はつきものだ。個人間、異なる目標や物事の進め方を持つ組織間で、意見の不一致が生じることは避けられない。地域住民がネットワークのやり方を受け入れない可能性もある。最も望ましい対立への備えは、たとえばコンセンサス(合意形成)のような公式の意思決定プロセスを定め、「このプロセスでは誰もが活発に意見を交わし、多様な意見を受け入れるインクルーシブなものになっている」と感じられるように設計することだ12。コンセンサスによる意思決定は通常よりも時間がかかるため、すぐに結果を出したい参加団体は乗り気でないかもしれない。一方で、どのメンバーの声も確実に届き、どのように意思決定がなされるのかを理解できるようになるので、そこに至った経緯が気に入らないからネットワークを去るという事態は防げる。このように公式な意思決定プロセスを定めておけば、ネットワーク内の強力な利害関係のバランス調整に役立つし、多くの対立に対して標準的な対処法を示すことができる。
ネットワークのリーダーは、コンフリクトマネジメントのスキルも学んでおく必要がある。特に、対立の性質とさまざまな介入策の判断に役立つコンフリクトアセスメントは必須だろう。自分たちのマネジメント方法を見直し、相手の立場で考える「視点取得(perspective taking)」や、対立する当事者の意見をそのまま伝達する「シャトル外交(shuttle diplomacy)」といった具体的な戦略も学ぶとよいだろう。
さらに研究から見えてきたのは、第三者の仲裁者の協力は、特に対立の状況が自分たちの手に負えない場合や、非常に長期間続いている場合に有効であるということだ。たとえば老後の人生を支援するエイジウェル・ピッツバーグ(AgeWell Pittsburgh)は、プログラムを終了するか、よりネットワークの目標に合うようにプログラムの方向性を変えるかについて対立が生じたときに、第三者の組織に仲裁を依頼して参加団体を引き止めることができた。
存亡の岐路で何が問われるか
リーダーたちは、自分たちが存亡の岐路に直面しているとなかなか認めることができない。たいていはこれまでのやり方が通用しなくなっていることにショックを受け、失望し、なぜこうなってしまったのかとあれこれ考える。しかし優れたリーダーたちは、ついにこのときが来たのだと捉えて、現実と正面から向き合おうとする。そして、この機会を活かして自分たちの本質を問い直す。
▪なぜ、私たちのネットワークは存在すべきなのか
▪生み出したい社会的インパクトは何か、そのためのセオリー・オブ・チェンジは何か
▪どのように意思決定すべきか
▪どのように資金調達するか
存亡に関わる緊急事態への備えができているネットワークであれば、これらの問いに対してすぐに答えられるかもしれない。たとえば、セオリー・オブ・チェンジや、意思決定の進め方、ネットワーク参加者や地域住民への提供価値を事前に明確化できていれば、危機をチャンスだと捉えて、ネットワークの目標を見つめ直し、改めてコミットすることができる。これらの問いに対する答えが曖昧であったり定まらなかったりするネットワークは、存亡の岐路に直面すると大打撃を受け、ネットワークを再建しようという声が上がっても、その議論に何カ月も要するだろう。
コネチカット州で、「ゆりかごから社会人まで」の人々を対象に大学進学や就職支援に取り組む教育ネットワーク、コアリション・フォー・ニュー・ブリテンズ・ユース(Coalition for New Britain’s Youth)を見てみよう。私たちが調査を始めた2017年の時点で、このネットワークは既に16年ほど活動しており、事務局長と数人のスタッフで構成されるバックボーン組織を置いていた。2020年にこのネットワークにインタビューをしたところ、この数年のあいだに存亡の岐路を経験していたことがわかった。バックボーン組織のスタッフが抜け、ネットワークとして新たなミッション、ビジョン、バリュー、そして組織構造を再定義していた。かつては教育面でのアウトカム向上にフォーカスしていたが、新たなミッションとバリューでは、「家族単位のサポート」と「若者の声を中心にする」にフォーカスを変えた。しかしながら最も大きな変化は、それまでネットワークのミーティングにいつも来ていた資金提供者たちに対して、今後は参加しないよう依頼したことだった。しかしその代わりとして、資金提供者からアドバイスや情報をもらうために別途設定したミーティングへの参加を呼びかけた。この変化のプロセスは、1年以上を要した。
存亡の岐路に立ったとき、すべてのネットワークがこうした選択肢をとれるわけではない。どんな危機に直面しているのか、そしてそれまでにどんな意思決定を行ってきたのかによって、選択肢は変わってくる。
これは「経路依存性(path dependency)」と呼ばれるものだ。運営形態やミッション、セオリー・オブ・チェンジをまったく新しいものに刷新しようとしても、単に時計の針を巻き戻したり、すべてをリセットしてゼロからやり直したりすることはできない。
ネットワークの再建は往々にして、立ち上げよりも困難なのだ。
たとえばセオリー・オブ・チェンジにおいても、それがプロジェクトモデル、政策モデル、カタリストモデルである場合と、学習モデルやシステム連携モデルである場合とでは、存亡の岐路の状況も異なってくる。私たちの研究によれば、参加団体に対して通常の業務や活動以上の取り組みを求めるネットワークのほうが危機に対して脆弱である。たとえば共同キャンペーンは、個別の組織にとって通常業務の範囲外の活動である。特にカタリストモデルのネットワークは、参加団体に対して、それぞれが通常行っている地域レベルでの活動の枠を広げてインパクトを拡大するように求めがちだ。
レディ・セット・ペアレント!のように単一のプログラムを運営するネットワークの場合、存亡の岐路に直面すると活動終了に至ることが多い。このネットワークは乳幼児の社会性獲得や情緒面の健康と発達を支援するプログラムを提供していたが、保険会社が出産後の入院支援期間を短縮すると、参加団体はネットワークの活動をするための財源も時間も確保できなくなった。最終的にこのネットワークは解散した。レディ・セット・ペアレント!は、ロードスター財団(Lodestar Foundation)の「コラボレーション賞」を受賞した実績があり、プログラムに対する需要や参加団体の努力が足りなくて終了したのではない。しかし、実績と多くの熱心なメンバーの存在だけでは、存亡の岐路を乗り切ることはできないのだ。
学習モデルやシステム連携モデルのセオリー・オブ・チェンジは、既存の活動を改善することに重点を置いている。たとえば他の組織からよりよい方法を学んで自組織に取り入れたり、異なるプログラムを連携させたりするといった取り組みがその一部である。このようなかたちで各組織の既存の活動を支援しているので、存亡の岐路に立ってもネットワークが受けるダメージは軽減される。
研究で調査したネットワークの多くが、COVID-19 のパンデミックによって存亡の岐路に直面し、レジリエンスと柔軟性を試されることになった。私たちは感染拡大が始まった年に、アメリカサーブの11 のネットワークで働くスタッフを対象としたインタビューを実施した。先述した通り、どのネットワークに問い合わせても、食料、住宅供給、心のケアなど21種類の異なる支援サービスから適切なものを選んでつないでくれる。つまり利用者はたらい回しにされることがない。感染拡大の初期は、ネットワーク参加団体の多くが対面での窓口を一時的にでも閉じてリモートワークに切り替えざるを得なかったが、すぐさま新しいニーズを捉えて戦略を変更し、以前と同じ目的を実現できるようにした。
たとえばアメリカサーブの連携ネットワークの1つであるPAサーブ(PAServes)は、支援が必要な退役軍人を見つけるための対面型のアウトリーチ活動を続けられなくなった。同様に、対面のプログラムしか提供していなかったPAサーブの協力団体の1つも活動停止に追い込まれた。そこでPAサーブは方向を転換し、以前実施した地域コミュニティでのイベント参加者リストを活用して、食料と基本的な生活支援サービスについてメールで情報発信を行った。また、プログラムを停止した協力団体に対して、食料や医薬品の配達という彼らにとって未経験のサービスを提供するよう依頼した。さらに、住宅供給、食料、就労支援など同時多発のニーズを扱えるように問い合わせを精査する仕組みを設けることで、新たな利用者の流入にも効率的に対応できるようになった。PAサーブは、自分たちのネットワークがどのようにして社会的インパクトを生んでいるかを理解していたので、多様なニーズを満たすサービスに退役軍人たちをつなぐことで、すばやい方向転換を実現した。そしてネットワークに参加する団体は、PAサーブが退役軍人を自分たちが提供するサービスにつないでくれていることを認識していたため、ネットワークへの協力を続けたのである。
レジリエンスの高いネットワークへ
ネットワークが存亡の岐路をうまく乗り切るための決め手は何か。この点について研究対象のなかでも頭一つ抜けているのが、ノースカロライナ州ウィルミントンのボヤージュ(Voyage)だ。ボヤージュのセオリー・オブ・チェンジは、青少年とその家族が成功するための道筋を整えることである。
その特徴は、2つのモデルのハイブリッド型である点だ。1つは複数の組織同士が協働するプロジェクトモデル、もう1つはボヤージュの代名詞である「コミュニティ・アウトリーチ・アドボケート(Community Outreach Advocates)」という、システム連携モデルのプログラムである。後者の活動は、まず問題を抱えるコミュニティに出向いて、個々の家族と一緒に考えながら彼らの強みや目標を明らかにする。そして、その目標を達成するためのアクションプランをともにつくり、ネットワークの参加団体が提供する各種サービスのなかから適切なものにつなげる。
存亡の岐路に直面する数年前から、ボヤージュは備えを進めていた。まず着手したのが「セオリー・オブ・チェンジの明確化」である。設立主旨のページにそれを明記することで、ネットワークの誰もが理解できるようにした。次に行ったのが「リーダーシップの分散」である。複数のアクションチームや地域住民が参加する委員会をつくり、1 人の中心的な人物に依存しないように、役割や責任をネットワーク全体に分散させた。さらにネットワーク初期段階で発生していた「対立への対処」も行っていた。地域で活動する非営利団体のなかには、ネットワークによって自組織の活動の影響力が弱まるのではないかと懸念するところもあった。そこでボヤージュは時間をかけて彼らの懸念と向き合い、信頼関係を築いた。
その後、ある変革型リーダーがネットワークを去ったとき、ボヤージュは存亡の岐路に立たされることになる。後任の事務局長はネットワークの方向性を変え、より包括的なあり方を模索した。つまり、ネットワークの日々の活動に影響を与える人間関係や家族、地域コミュニティ、社会制度に目を向けたのだ。そして、ネットワークのバリューの転換を示すべく、名称も変えた。当初のブルー・リボン・コミッション(Blue Ribbon Commission)からエンド・ユース・バイオレンス(End Youth Violence)に変え、現在のボヤージュに至る。その後もネットワークは成長を続けており、プログラムに参加する子どもの数は2倍を超え、サービスを利用する家族も大幅に増加した。また、2017年には30程度だった参加団体の数が、2019年には51まで増加した。十分な準備に支えられたボヤージュの対応は、ザ・リテラシー・オーガニゼーションの顛末とはきわめて対照的である。
自分たちのネットワークはいずれ必ず存亡の岐路に立たされると確信しているリーダーもいることが私たちの調査からもわかっているが、その瞬間を予測できる場合もあれば、突然やってくる場合もある。危機に直面して消滅するのは、そもそも消滅するはずだった場合か、危機を乗り越える準備ができていなかった場合のどちらかだ。一方、危機にうまく適応して発展を遂げるネットワークもある。短期的な戦略上の撤退は、方向転換になることもある。ネットワークが参加団体と地域コミュニティのニーズをよく理解していて、真の提供価値にフォーカスしていることを示せるからだ。
ネットワークを危機から完全に守る方法はない。また、「真摯に社会的インパクトを目指していれば、障壁を乗り越えなくても目標を達成できるはずだ」という甘い期待を抱いてはならない。レジリエンスを高めることができれば、危機的状況でもサービスを提供し続けられるはずだという自信を持って、進むべき道を見出せる。存亡の岐路において何らかの変化は避けられないが、以前よりも、自分たちのセオリー・オブ・チェンジとバリューにフォーカスした姿に生まれ変われるのだ。
【原題】How to Build More Resilient Networks(Stanford Social Innovation Review, Fall 2022)
【イラスト】Kathleen Fu
注
1 組織および個人が特定できないよう、いずれも仮名としている。
2 Network for Nonprofit and Social Impact, “The Networks for Social Impact in Education Series,” 2021, https://nnsi.northwestern.edu/educationseries.
3 Michelle Shumate and Katherine R. Cooper, Networks for Social Impact , Oxford: Oxford University Press, 2022.
4 Michelle Shumate, Mapping the Navigation Systems of Pennsylvania: Opportunities for the Future , Social Impact Network Consulting, 2021.
5 Yuri Cartier, Caroline Fitchenberg, and Laura Gottlieb, Community Resource Referral Platforms: A Guide for Health Care Organizations , Social Interventions Research & Evaluation Network, University of California San Francisco, 2019.
6 Deborah Agostino, Michela Arnaboldi , and Martina Dal Molin, “Critical Crossroads to Explain Network Change: Evidence from a Goal-Directed Network,” International Journal of Public Sector Management, vol.30, no.3, 2017.
7 H. Brinton Milward and Keith G. Provan, A Manager’s Guide to Choosing and Using Collaborative Networks , IBM Center for The Business of Government, 2006.
8 団体名は名誉尊重のために仮名とした。
9 Katherine R. Cooper and Michelle Shumate,”Interorganizational Collaboration Explored Through the Bona Fide Network Perspective,”Management Communication Quarterly , vol.26,no. 4, 2012.
10 Rong Wang, Katherine R. Cooper, and Michelle Shumate, “The Community System Solutions Framework,” Stanford Social Innovation Review, Winter 2020.
11 Maoz Brown, “Unpacking the Theory of Change,” Stanford Social Innovation Review, Fall 2020.
12 Seeds for Change, Consensus Decision Making: A Guide to Collaborative Decision-Making for Activist Groups , Co-ops, and Communities (2nd edition), 2020.
Copyright ©2022 by Leland Stanford Jr. University All Rights Reserved.


