企業のサステナビリティ事業は爆発的に成長しているが利益が優先されて実際のインパクトは見過ごされがちだ。その流れを変えるために重要な3つのステップを示す。
※本稿は、SSIR Japan 編『スタンフォード・ソーシャルイノベーション・レビュー 日本版 02 社会を元気にする循環』より転載したものです。
マイケル・L・バーネット Michael L. Barnett
ベンジャミン・カショア Benjamin Cashore
アイリーン・ヘンリクス Irene Henriques
ブライアン・W・ハステッド Bryan W. Husted
ラジャット・パンワール Rajat Panwar
ジョナタン・ピンクス Jonatan Pinkse
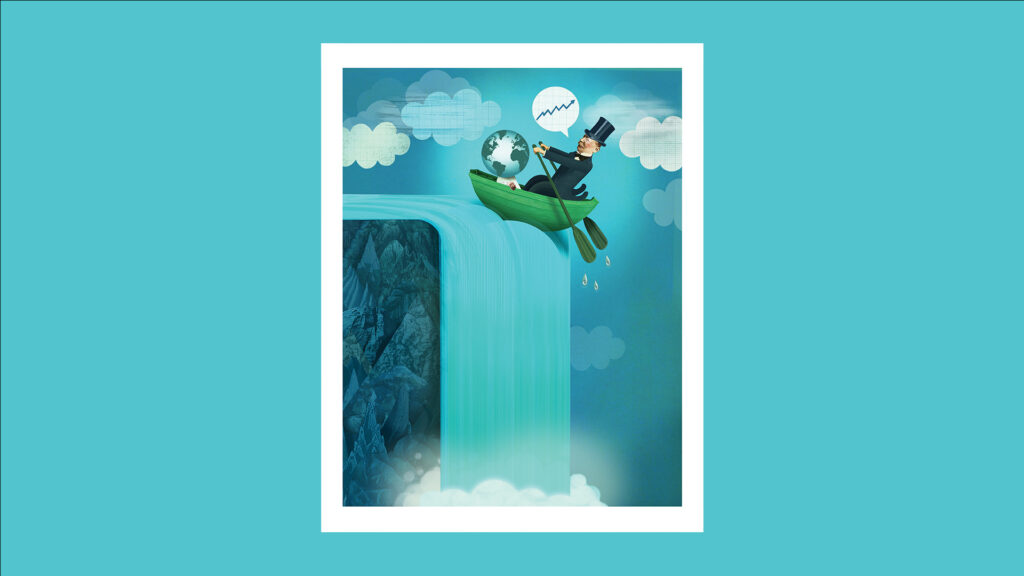
サステナビリティは、人類にとって最大の課題だ。地球の生態系は甚大なダメージを負っていて、存続の危機に直面している1。その責任の一端は企業活動にあるが、果たして企業はこの流れに歯止めをかけられるだろうか。
企業はこれまで、重要な環境問題に自主的に取り組み、膨大なリソース、グローバルな展開力、そして独自の能力をつぎ込んできた。今や、最大手のグローバル企業の90%超が、環境への責任を果たすと公言している2。サステナビリティ事業はどの企業でも見られるようになり、多くの企業では組織構造や文化にまで浸透し、専門性の高い幹部がマネジメントに当たっている。
では、なぜ私たちは未だに危機的な状況にあって、さらに悪い方向に向かっているのだろうか。当然ながら、企業だけが地球のサステナビリティに対する責任を負っているわけではない。政府にも果たすべき役割はある。一方で、環境問題に対してこれほど大きなコミットメントを企業が示しているにもかかわらず、その貢献の成果が不十分なことは証明されている。たとえば、多くの企業が温室効果ガスの過剰排出を止めようとしているにもかかわらず、こうした取り組みが激増した過去30年間の二酸化炭素排出量は、それ以前の250年間を上回った3。
長期にわたって取り組まれてきた、企業による膨大な数のサステナビリティ事業は、本来ならそろそろ環境悪化の進行を止めるか、せめてそのペースを抑制するなどの成果をあげていてもよいはずだ。しかし、多くの経営者自身が認めているように、企業は地球を救うために十分に取り組んでいない4。何かが変わらなければならない。その「何か」とは、サステナビリティに取り組む際の事業企画(ビジネスケース)主義のパラダイムだ。事業企画主義によって、企業のサステナビリティ事業の分野は大きく成長した。しかしながら、事業企画によってサステナビリティの取り組みがプログラムの効果を十分に発揮できないような方向に歪められている。私たちは、手遅れになる前にこの歪みを認識し、正さなければならない。
失敗の歴史
サステナビリティは世界最大の課題ではあるものの、大半の企業はこの課題を経営の中心に据えていない。むしろ企業は、自身の基幹事業を成長させるために環境を荒廃させてきた。企業だけが人類の危機的な状況の責任を負っているわけではないとはいえ、企業活動の影響は非常に大きい。たとえばクライメート・アカウンタビリティ・インスティテュート(Climate Accountability Institute)のデータによれば、1965年から2018年にかけて、全世界の化石燃料由来の排出の35%が、石油・ガス・石炭の最大手企業20社によるものだった。
「利益」は企業にとって強力な動機であり、それによって企業活動は人類や地球に悪影響を及ぼしうる。しかし同時に利益は、人類全体の幸福とサステナビリティを改善するような行動を企業に取らせる動機にもなりうるのだ。企業は、サステナビリティを他のあらゆる事業投資と同じように見なしている。そのため、利益が見込まれる「事業企画(ビジネスケース)」にはゴーサインを出す。利益を目指すこのアプローチによって、企業のサステナビリティ事業はみるみるうちに成長していった。世界の最大手の企業のほとんどが、いまでは幅広いサステナビリティ事業に多大なリソースをつぎ込んでいる。
現在、企業のサステナビリティへの取り組みにおいて、事業企画主義のパラダイムがはびこっている。たとえば各社が毎年発表しているサステナビリティ関連の無数の華やかなレポートは、こうした事業への莫大な投資は企業と地球にとって「ウィン・ウィン」であるとうたっている。政府側もその姿勢を支持し、企業によるサステナビリティ事業への投資を推奨してきた。企業が自発的に自社の活動を規制するほうが、法による規制よりもコストがかからず簡単で実効性も高いので、法整備の大きな負担を軽減したいと考える各国政府にとって魅力的だからだ。こうした企業による自主規制が政府の規制を部分的に補完しながら、企業のサステナビリティ事業が発展していった。
一方で地球環境の悪化には歯止めがかかっておらず、熱帯雨林は大幅に減少し、海洋はプラスチックごみであふれ、土壌はますます汚染され、数えきれないほどの生物種が絶滅している。こうした状況への企業の関与は減るどころか増えてしまっている。たとえば、「カーボンメジャー」と呼ばれる、世界最大級のカーボンフットプリント(企業活動全体における温室効果ガス排出換算量)を記録する企業の排出量は年々増加している。bpやシェルのように、2050年までに排出量を実質ゼロにするという野心的な目標を広く公表している企業でさえ、排出量が増えている。2016年にベイン・アンド・カンパニーが実施した調査によれば、企業の98%が自らのサステナビリティ関連の目標を達成できていないという衝撃的な結果が示された。つまり、企業のサステナビリティ事業は拡大し続けているにもかかわらず、全体としては環境悪化をほとんど相殺できていないのだ。
簡単なウィンを狙うテクノロジー主導の消費主義
いったい何が起きているのだろうか?なぜ、サステナビリティが実質的に後退しているにもかかわらず、企業のサステナビリティ事業は成長しているのだろう?
サステナビリティ事業への投資に企業を走らせる「利益への動機」は、サステナビリティを改善するという実際のアウトカム(成果)をむしろ抑制するような方向に投資判断を偏らせてしまう。その結果、企業のサステナビリティ関連の投資が増えても、環境へのプラスの影響がその投資額に見合うほど大きくなっていないのだ。事業企画というものは、技術革新に依存した限定的な範囲の「簡単なウィン」を追求するよう企業に促すので、見当違いのアウトカムと消費量の増加を引き起こしてしまっている。その典型的な特徴をこれから見ていこう。
●簡単なウィン
サステナビリティを義務やコストではなく投資として定義することで、事業企画は利益の最大化が企業の第一の目的であるという考え方を補強している。利益が見込めるとわかれば、企業は環境に配慮した事業のビジネスチャンスの探索に乗り出し、新たなイノベーションに取り組むようになる。しかしながら、そうして実現された事業における環境への配慮は、限定的なものになりやすい。事業企画をつくる際の「ウィン・ウィン」の考え方では、まず自社にとって適正な利益が見込めるかどうかが問われ、利益が出る場合にのみ環境改善効果に目が向けられる5。環境問題への取り組みや、革新的なソリューションの新規開発に十分な金銭的インセンティブがあれば、企業はそうした事業にわれ先に乗り出すだろう6。だが、それが実現するのは環境に配慮した製品やサービスを顧客が喜んで買う「美徳の市場」が存在する場合だけだ7。結果として企業は、主に所得の高い消費者への訴求力を高められるような、一部の比較的小規模な環境問題に取り組むようになる。そして、実質的な環境改善効果よりも、商品の機能性やデザインの改善が優先されるのだ。
しかし、重要な環境問題の多くが事業化自体が困難か、そもそも不可能な場合もある。ほとんどの消費者は、たとえば生物多様性保護への貢献度がより大きい製品があっても、それを買うことによる直接的な利益を認識できない。そのため、生物多様性を保護する製品の市場は、環境への意識が高い消費者という小さなグループだけを対象とした規模にとどまってしまう8。海洋汚染、生息域の喪失、種の絶滅といった重大な環境問題は、消費者の意識が高まっても、明確な利益を当て込むことはできないし、したがって事業企画もつくれない。つまり、重大な環境問題のほとんどに対して、事業が成立しても、企業がとるアクションはあまりに小さすぎるものになりやすいのだ。
●テクノロジー中心のソリューション
サステナビリティ事業の推進者が事業化を考えるとき、市場の需要が十分にあることだけでなく、どうすれば企業が高い費用対効果でその需要を満たせるかも示さなければならない。革新的な企業であれば、急速に進歩しているテクノロジーを利用してランニングコストを下げ、生じる廃棄物の量を最小限に抑え、必要なエネルギー投入量を減らしながら、環境に配慮した事業機会を生み出そうとするだろう。違法な森林伐採を防止するためにリモートセンシング技術を活用したり、流通システムの脱炭素化のために水素燃料電池を使った電気自動車に移行したりするなど、企業はサステナビリティに取り組む姿勢を世に示す手段として、技術革新に大きく頼っている9。
ところが残念なことに、技術革新はしばしば意図せぬ悪影響を数多くもたらし、新たな環境問題を引き起こしてしまうこともある。たとえば、電気自動車は流通のカーボンフットプリントを削減できる一方で、コバルトなど「汚れた」鉱物が素材となる電池の生産によって土壌を汚染し、これらの鉱物資源を掘削する環境コストを跳ね上げる。また、従来のエネルギー源から再生可能エネルギーへ移行する際には、電力系統にスイッチギヤと呼ばれる開閉装置を設置する必要がある。スイッチギヤに使われる絶縁物質の六フッ化硫黄は二酸化炭素よりもはるかに強力な温室効果ガスであり、エネルギー源の移行に伴う排出量増加が懸念されている。これ以外にも予測できなかった悪影響の例として、台風並みの風に耐えるよう設計された風力発電用風車のブレードがリサイクルしづらいため、埋立地に廃棄されているという問題がある。
実は、環境に悪影響を及ぼすことがあらかじめわかっていた新技術もある。ソーラーパネルや電気自動車など、有用な環境技術が続々と生まれている一方で、環境にさらなる悪影響を及ぼす技術も生まれているのだ。たとえば、パルプ生産及び製紙業の技術革新によって、従来は手つかずで守られていた北方林(亜寒帯林)の広範な土地でも伐採が可能になり、企業活動による資源の搾取を助長している。
また、技術革新は手っ取り早い解決策と捉えられがちだが、それが実現するまでには時間がかかる。技術のブレイクスルーと、その実用化・商用化との間には大きなタイムラグが生じることがある。これは業界や地域によって異なるが、2018年に『エネルギー・ポリシー』誌に掲載された論文は、エネルギー分野では一般的に20年から70年のタイムラグがあると指摘している。このような時間軸は、環境問題の緊急性に見合わない。
●根底にある消費主義
事業企画の前提にあるのは、サステナブルな製品を求める消費者の需要があるということだ。環境に配慮した製品にお金をかけてもかまわないという顧客が十分にいなければ、事業は成立しない。幸い、機能性やデザインが改善されている場合は特に、環境に配慮した製品にお金を出したいという消費者の意欲は高まっている。企業が先進技術を活用してこのようなニーズに応える製品を生産するようになった一方で、消費者側でも環境によいものを選ぼうとする志向が高まり、こうした製品開発を進めることで企業が利益を得るチャンスがさらに広がった。
環境に配慮した製品を選びたいという消費者ニーズの高まりがサステナビリティ事業の成長に貢献しているが、これは環境のサステナビリティにとっては望ましくないソリューションである。なぜなら、消費し続けることでサステナビリティを実現することはできないからだ。1992年にリオで開かれた地球サミットでは企業活動に焦点が当たり、持続可能でないレベルの消費はサステナビリティの根本的な脅威であることが指摘された。それにもかかわらず、環境に配慮した消費活動においても消費の拡大が前提になっている。環境にやさしい消費でも、消費する量が増え続ければ環境への悪影響が減ることはないだろう。技術革新による環境改善効果のうち、とりわけエネルギー効率は、消費の拡大によって相殺されやすい。たとえば、ジェット旅客機の燃費効率が改善されて航空券が安くなったことで、航空交通量は大幅に増加した。環境経済学では「ジェボンズのパラドックス」として知られるこのリバウンド効果が、サステナビリティ事業の文脈で説明されることは滅多にない。
世界の特に人口の多い地域では、中産階級の人口が年々増えている。2007年から2012年の5年間で中国における世帯当たりの環境フットプリントは19%増加し、そのうち4分の3は都市部の中産階級と富裕層の消費増加に伴うものであった10。世界全体で見ると、2020年に欧州委員会が発表した予測によると、2017年に約37兆ドルだった中産階級の支出は、主に新興国における消費増加に伴って、2030年には約64兆ドルまで伸びるとされている。豊かになればなるほど、過剰な消費は環境に悪影響を及ぼす。環境に配慮した消費の拡大が環境によい製品やサービスの収益性を上げるとしても、総消費量の増加による環境への悪影響を打ち消すことはできないのだ。
誇大広告を希望に変える
利益予測を盛り込み、革新的な技術を活用し、環境志向の消費者需要を前提としたサステナビリティ事業への投資は、環境を改善するという本来の成果を十分に出せていないばかりか場合によっては環境を悪化させてしまっている。企業は、より実質的なアウトカムを達成するために、事業企画の方向性を変えなければならない。企業に求められるのは、簡単に利益を出せるビジネスの環境改善効果を台無しにする要素についても説明責任を負うこと、限定的な範囲で技術的なソリューションを求めるのではなく他者とのコラボレーションに全力で取り組むこと、そして成長よりも充足を優先することだ。さらに、これらの重要なステップを企業が歩めるようになるためには、各国政府がより積極的な役割を果たすことが求められている。
STEP1
環境への影響を正確に説明する
企業がサステナビリティ事業の質を高めるためには、まずはその事業が環境にどんな影響を与えているかをきちんと把握しなければならない。企業は経済的なアウトカムの評価は得意だが、自社の活動が環境や社会に与える影響について説明することは苦手だ。市場も共犯者だ。善意に見える活動は称賛する一方で、企業が実際の環境的インパクトを明確に説明せずに利益を得る状況を許容している。したがって企業側は、事業企画のなかで環境へのインパクトを細かく説明するリスクを負うことはしてこなかった。そのようなことをすれば、簡単に利益を出せるはずのビジネスをかえってややこしくしてしまうだけだからだ。
具体的なインパクトを出すために、企業はサステナビリティ事業について明確な指標を設定してその達成状況を誠実に報告するという、困難でリスクの高い取り組みを行わなければならない。現在主流となっている指標は、事業による環境改善効果を自社の過去実績あるいは同業他社の実績と比較して評価するものである。いずれにしても基準となるのは、過去の実績だ。これだと過去に何もしてこなかった企業ほど成果を出しているように見えてしまう。なぜなら、低い基準値と比較すると、わずかな改善を素晴らしい進歩のように錯覚するからだ(これは「アンカリング効果」と呼ばれ、先に示された数字や情報に基づいてその後掲示される数字や情報を評価する認知バイアスの一種だ)。さらに、そのような改善は根本的な問題をほとんど解決していない。たとえば、排出量が減少してわずかに改善したように見えても、それを打ち消すほど大量の温室効果ガスを排出していれば、解決に貢献していると自ら標榜している問題を実は悪化させていることになる。
企業は過去の実績を基準値にするという怠慢に走ることなく、環境科学に基づいた適切なベンチマークを設定し、実践に組み込まなければならない。また、組織レベルの目標は、部分から全体を見出すリバースエンジニアリングの考え方を通じて、システムレベルの目標と結び付けられている必要がある。このような方向に企業を促すために、CDP(Carbon Disclosure Project)、国連グローバル・コンパクト、世界資源研究所(WRI)及び世界自然保護基金(WWF)が共同で立ち上げたのが、「サイエンス・ベース・ターゲット・イニシアチブ(SBTi)」である。SBTiは、地球の気候システムが壊滅に向かう「ティッピング・ポイント(臨界点)」に達するのを回避するために、世界の平均気温の上昇を1.5℃以下に抑える目標を掲げたパリ協定に従うことを、特に企業に対して強く求めている。SBTiはこれまでCO2排出量だけに焦点を当て、他の温室効果ガスや環境問題への対策は視野に入れてこなかった11。それでもSBTiは、組織レベルの目標として何が適切なのかを問いかけたという点で、サステナビリティ事業におけるアウトカムの基準値設定に関して、幅広い対話を促す起点になったといえるだろう。
環境面でのアウトカムを実際に企業が評価している場合も、その指標の大半は組織レベルのものだ。しかし、実際はサプライチェーンや消費活動からも温室効果ガスは排出される。企業のサプライチェーンは多くの場合、世界中に分散していて運営の実態が非常に不透明なため、ほとんどの業界ではサプライヤーの追跡という単純なことですら不可能に近い。そこで、温室効果ガス排出についてのグローバルな枠組みとして、WRIと「持続可能な開発のための世界経済人会議」が共同で開発したのが「温室効果ガスプロトコル(GHGプロトコル)」だ。これは、企業が自社事業に関連するすべての温室効果ガス排出の評価とマネジメントをするための指針を示すものだ。GHGプロトコルでは、「領域1:企業レベルの排出」「領域2:購入した電力由来の排出」「領域3:バリューチェーンレベルの排出」の3つの領域ごとに指針を設けている。なお、領域3の実質的な評価は難しい可能性がある。排出量ゼロへのコミットメントを掲げ、サステナビリティへの関心を標榜している企業の多くが、領域3については無視しているからだ。
政府は、事業のインパクトに対する説明責任を果たすよう企業に求めるという、非常に重要な役割を担っている。強制力のある法的枠組みがなければ、領域3の排出について評価や報告を実施する企業はほとんどないだろう。アメリカの環境保護庁(EPA)は領域3の排出の情報開示を義務付けていないが、カリフォルニアなどアメリカの一部の州やイギリスやドイツなどの国では、サプライチェーンに関する情報開示を義務付ける規制がある。これらの規制の第一の目標は、非人道的な労働者の待遇や人身売買といった、サプライチェーン内の人権侵害の根絶であり、環境保護とは異なるものだ。しかし、企業にサプライヤーの特定を求めることで、領域3の排出報告を義務付けるための道筋として活用できるだろう。
さらに政府は、企業のサステナビリティ事業とインパクト評価に関する報告の標準化に取り組むことができる。これに市場関係者が足並みを揃えることで、優れた事業にもっと資金が回るようになり、問題のある事業が排除されるようになるだろう。企業会計の分野には国際財務報告基準(IFRS)があるが、これは世界中どこでも財務諸表が統一化されて透明で比較可能であるという状況を担保し、市場取引の促進に役立った。これと同様のことは、科学的観点に基づいた国際的な環境報告基準を設けることでも可能なはずだ。
STEP2
コラボレーションを通じてソリューションを見出す
技術革新は、より環境に配慮した製品を無数に生み出した。だが、気候変動、生物多様性の破壊などの、重大な環境問題を解決できる革新的なソリューションをどこかの企業が発見してくれるはずだとただ祈り続けるのは愚かなことだ。事業企画主義のパラダイムでは、イノベーションは組織の内部で実現し、利益は内部留保するのが常識だ。だが、どれほど革新的な企業でも、『ポリシー・サイエンス』の2012年の掲載論文が「superwicked(飛びぬけてやっかいだ)」と表現したような重大な環境問題を、1つの組織だけで解決することはできない。単独ではなく、コラボレーションが必要なのだ。
ステークホルダーやセクターを越えた幅広いコラボレーションのほうが、複雑な問題に対して革新的なソリューションを生み出しやすくなるはずだ。また、これまでの取り組みで十分に意見が反映されてこなかった人々に、発言する機会が与えられるだろう。たとえば、気候学者は海洋の氷の状況変化を把握するために、イヌイットと協働して彼らの伝統知識であるカウイマヤトゥッカンギト(Qaujimajatuqangit)を活用しようとしている。また、オーストラリア北部にいるアラワ族などの先住民が生物学者に協力して、猛禽類が燃えている木の枝を意図的に運んで草地に火をつける行為は、獲物を捕りやすくするためであることが判明した。サステナビリティ課題を解決するためには、こういった幅広いコラボレーションから得られる知見が実践にうまく活かされなければならない。この点において、事業企画主義がもたらす歪みが特に問題となってくる。
なお、サステナビリティ事業でコラボレーションしたとしても、たいていの場合は企業が事業の実施権限を持っている。そして企業は、その取り組みが自社の評価基準を達成できないとわかると拒否権を発動する。こうした慣習が、簡単には利益を見込めないような、実質的で根本的な問題解決への取り組みを難しくしている。しかしもっと広範なコラボレーションが実現すれば、たとえそのサステナビリティ事業が企業側の基準を満たせなくても、「これは自社の小さい利益以上にプラスの効果を生むかもしれないから、やってみる価値はありそうだ」という認識を企業側が持つようになるかもしれない。実現可能なソリューションを共創するための重要な一歩は、簡単に利益を見込めるビジネスからさらに踏み込んで、多様な関係者の問題意識に応え、利益以外のさまざまな種類の価値を創造していくという挑戦を企業側が受け入れることだ。
企業は、サステナビリティ事業が自社にどれくらい利益をもたらすかだけでなく、環境的・社会的価値をどれくらい生み出せるかについても評価する能力を高める必要がある。そして、経済成長の追求と地球の環境悪化との間にあるジレンマについて、オープンで正直な議論に取り組んでいくべきだ。ますます世界が複雑化していく状況において、財務的な業績以外の事柄に関する説明責任を、非営利組織やハイブリッド組織だけに押し付けることはもはやできない。企業もまた、仮に従来のように利益を明確に見込めなかったとしても、重要な環境問題を十分に認識して、協力的で責任感のあるパートナーとして解決に取り組まなければならないのだ。さらに政府も、優先事項を設定したりすべての当事者に説明責任を求める規制を設けるなどして、人類の難問解決に不可欠となる強力なコラボレーションを築くための環境を整えていく必要がある。
STEP3
脱成長に向けたデザイン
環境に配慮した製品がもっと広がってほしいという消費者の声が大きくなるのはよいことだ。だが、限りある資源の総消費量が拡大するのは望ましくない。世界的なパンデミック、想定外の世界規模の山火事、熱波、ハリケーンなど、際限なく続きそうな巨大災害が経済・環境・社会に大きなダメージを与えており、人類の消費活動が持続可能でないレベルにあることを露呈している。私たちは、地球が耐えられるような消費・生産システムを再構築しなければならない。
これほど進行した段階になってから、持続可能な消費・生産システムをつくることは容易ではない。たとえ環境に配慮した製品であっても、ますます量産し続けるのではなく、私たちの最適なウェルビーイング(心身の健康と幸福)にとって十分な消費のレベルを判断し12、これに従って脱成長に向けたデザインをしていく必要があるだろう。過剰消費から脱却するための第一歩は、充実した幸福な生活のために消費者が実際に必要としているものが何なのか、そして環境へのインパクトを可能な限り小さくしたうえでこのニーズを満たすにはどうすればよいのかを理解することだ13。
収益性よりも充足性を優先するということは、事業企画主義のパラダイムや既存の慣習をがらりと変えるということだ。たとえば、これまでマーケティングの常識だった「Product(製品)」「Price(価格)」「Promotion(プロモーション)」「Place(流通)」という「4P」の捉え方は根底から変わるだろう。充足性の思考では、企業は売上の量に注力するのではなく、より耐久性があり修理もできて、中古市場での取引も可能な製品のデザインと生産に取り組むことになる。価格には、製造、流通に加えて廃棄やリサイクルに要するすべての費用が含まれる。プロモーションにおいては、製品の宣伝をしながらもその過剰消費は促さないという、難しいバランスが求められるようになる。流通においても、従来の販売チャネルだけでなく、たとえばオンラインストアやシェア利用の仕組みなど、新しい実験的なチャネルも検討することになる14。
脱成長に向けたデザインは、消費による成長を追求し続けることよりもはるかに複雑だ。「脱成長」自体が難しい概念であり、消費率の低下だけでなくGDP成長率や従業員の労働時間などの指標も議論されている。脱成長は、脱資本主義を支持する急進的なイデオロギーとも近い考え方だ15。環境政策の研究者であるトーマス・プリンセンが2005年の自著『充足性の論理』(The Logic of Sufficiency)で述べたように、消費システムそのものの転換が必要になるかもしれない。プリンセンいわく、「たった1つの惑星に明白に迫っている限界を、日常生活の限界に捉え直して行動に移すことが急務となっているいま、充足性こそが秩序をもたらす原則になるのではないだろうか。分業や大規模なオペレーションや顧客の需要が力を持っている消費経済のロジックでは、このような捉え直しは言うまでもなく不可能だ」。しかし脱成長の概念がどうであれ、脱成長を実現するためには、それを中心に据えたビジネスモデルをつくると同時に、政治的な変化も必要になってくる。
とはいえ、脱成長に向けたデザインには、政府を転覆させるほどの過激さは必要ない。むしろ、これまで述べてきたステップと同様に、政府の積極的な役割が求められる。たとえば、生産者に自社の廃棄物を責任をもって処理することを義務付ける「引き取り法」を適切にデザインできれば、企業はもっとリサイクル可能な製品開発に取り組むようになるだろう。修理サービスへの減税措置を導入すれば、消費者は製品の修理に積極的になるし、企業は修理可能な製品をもっとつくろうとするだろう。さまざまな当事者による充足性と脱成長に向けた取り組みを促すには、このような政策がさらに求められている。
泥沼を回避する
過剰な開発によって、地球は持続可能でない方向に向かっている。私たちは、危機的な段階に直面しており、抜本的な措置を講じなければならない。2015年には国連の後押しによって、2030年までに17の持続可能な開発目標(SDGs)を達成することを世界のリーダーたちが強く誓った。この約束は、1992年にリオデジャネイロで採択された「アジェンダ21」から2000年の「ミレニアム開発目標」、そして2012年のリオ+20での「グリーン経済」に続く、国連主導のイニシアチブだ。このイニシアチブにおいても、主要な公約をいずれも達成できないことが将来判明するだろう。
SDGsのほとんどの目標で達成状況は不十分であり、特に気候変動と生物多様性の保全に関する項目はほとんど達成できていない16。アントニオ・グテーレス国連事務総長は、2019年のSDGsの進捗レポートの中で「私たちの現状について正直で率直な考察が必要だ」と結論づけている。この問題について2019年のダボス会議に登壇したグレタ・トゥーンベリは、「私たちの家は燃えています。今や断固とした行動を取らなければなりません」という、より直接的かつ鮮やかな表現で訴えた。
企業は強力な当事者だ。サステナビリティに貢献するにせよ問題悪化に加担するにせよ、大きな違いをもたらす力がある。差し迫った状況を認識して、過去数十年間にわたって企業は壮大なコミットメントを掲げてきた。しかし、現在はびこっている事業企画主義のパラダイムによって、残念ながら実態としては空約束に終始しており、サステナビリティを実現できないどころか、ときには有害無益となってしまっている。
公平を期すために述べておくと、企業のサステナビリティ事業は完全な失敗に終わっているわけではない。目標を達成できていないとはいえ、重大な問題に対する社会の関心を高めることには成功している。そして、多くの企業の立場から言えば、サステナビリティ事業は彼らのためにもなるものだ。政府が規制するやり方では、企業にコスト負担を強制することが難しいため、実効性に欠けやすい。企業は規制を回避したがるものだ。規制は環境破壊をもたらす業界慣習を削減させてきたものの、企業は政府に対するロビー活動を展開し、公的な規制を自主規制に切り替えることに成功してきた。残念ながら、膨大な数の企業のサステナビリティ事業が、環境悪化の抑制よりも環境規制の緩和に成功している。
サステナビリティを共に実現するために重要な役割を担うよう企業を動かすためには、規制緩和ではなく、よりよい規制が求められている。政府は身を引くのではなく、進み出るべきだ。環境問題の優先順位を高めるには、企業が「自分たちは相互に依存し合うエコシステムの一部である」と認識する必要がある。より幅広くかつ深くサステナビリティ実現に向けた行動を取れるよう、企業は、自らの製品やサービスの生産・流通・消費に関してもっと包括的に理解しなければならない。そのためには、経営学者のサンジェイ・シャルマとアイリーン・ヘンリクスが述べたように、「環境と社会へのインパクトを減らすための製品とプロセスの再設計、製品に対する責任のスチュワードシップ、生息域の保護、地域環境が耐えられる範囲内でのオペレーション、次世代の利益の保護、さらには社会のあらゆる階層間の公平なバランス」というステップを踏むことが求められている17。
効果的な規制によって、利益を最も優先する事業企画主義の束縛から企業を解き放たなければ、企業はごく狭い範囲の消費者に見える環境問題だけに注力しがちになる。また、利益が見込めそうな問題であっても、企業を動かすのに失敗することは頻繁にある。環境への投資判断と同じロジックを用いて、企業は利益の減少につながる案件を避けている。たとえば、「大きな経済的リターンと小さな環境改善効果があるプロジェクト」と「小さな経済的リターンと大きな環境改善効果があるプロジェクト」のいずれかを選べるとすれば、企業は経済的リターンが最大になるものを優先させるだろう。どちらのシナリオもウィン・ウィンではあるが、事業企画の論理に従うことで、環境的な目的よりも経済的な目的を優先することになる18。したがって事業企画主義のパラダイムは、より本質的な行動が求められている途方もなく大きな環境危機から、企業の目を逸らしてしまう。
事業企画主義のパラダイムがはびこることの究極的な問題は、深刻な環境問題と向き合わずに限定的な範囲の事業だけに投資するという歪みだけではない。時間が限られているにもかかわらず、限定的な事業が大量に乱立することで、より有意義な行動が締め出されてしまうことこそが問題なのだ。つまり企業は、自社のリソース全体を十分にコラボレーションに活用できなくなっている。また政府の介入が不十分なのは「政府が介入すると企業の自主性が損なわれる」という反論を懸念しているからだ。以上のことから、事業企画主義のパラダイムに基づくサステナビリティ事業の爆発的な成長は悪性腫瘍のようなものだ。他の領域に転移して、健全な介入を締め出し続ける期間が長くなるほど、人類が環境危機の大惨事から引き返せる希望を潰してしまうリスクは、ますます大きくなるだろう。
【原題】Business Case for Corporate Sustainability(Stanford Social Innovation Review, Summer 2021)
- The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Special Report: Global Warming of 1.5°C, Geneva: World Meteorological Organization, United Nations, 2018.
- Governance & Accountability Institute, Flash Report S&P 500, 2020.
- Rebecca Lindsey, “Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide,” ClimateWatch Magazine, August 14, 2020.
- Apurv Gupta et al., The Decade to Deliver: A Call to Business Action, The United Nations Global Compact―Accenture Strategy CEO Study on Sustainability, 2019.
- Tobias Hahn et al.,“Trade-Offs in Corporate Sustainability:You Can’t Have Your Cake and Eat It,”Business Strategy and the Environment,vol. 19,no.4,2010.
- Stuart L. Hart, “A Natural-Resource-Based View of the Firm,” Academy of Management Review, vol. 20, no. 4, 1995.
- 『企業の社会的責任(CSR)の徹底研究――利益の追求と美徳のバランス――その事例による検証』デービッド・ボーゲル著、小松由紀子、村上美智子、田村勝省訳(一灯舎、2007年)(David Vogel, The Market for Virtue: The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility,Washington, D.C.: Brookings Institution Press,2005)
- Katherine White, David J. Hardisty, and Rishad Habib, “The Elusive Green Consumer,” Harvard Business Review, July-August 2019.
- Ram Nidumolu, C. K. Prahalad, and M. R. Rangaswami,“Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation,” Harvard Business Review, vol. 87, no. 9,2009.
- Dominik Wiedenhofer et al., “Unequal Household Carbon Footprints in China,” Nature Climate Change, vol. 7, 2017.
- Johan Rockström et al., “A Safe Operating Space for Humanity,” Nature, vol. 461, 2009.
- Hélène Gorge et al., “What Do We Really Need? Questioning Consumption Through Sufficiency,”Journal of Macromarketing, vol. 35, no. 1, 2015.
- Mihaly Csikszentmihalyi, “The Costs and Benefits of Consuming,” Journal of Consumer Research, vol. 27, no. 2, 2000.
- Maike Gossen, Florence Ziesemer, and Ulf Schrader, “Why and How Commercial Marketing Should Promote Sufficient Consumption: A Systematic Literature Review,” Journal of Macromarketing, vol. 39, no. 3, 2019.
- Hamish van der Ven, Catherine Rothacker, and Benjamin Cashore, “Do Eco-Labels Prevent Deforestation? Lessons from Non-State Market Driven Governance in the Soy, Palm Oil, and Cocoa Sectors,” Global Environmental Change, vol. 52, 2018.
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services , New York: United Nations General Assembly, 2019; IPCC, Special Report: Global Warming of 1.5°C.
- Sanjay Sharma and Irene Henriques, “Stakeholder Influences on Sustainability Practices in the Canadian Forest Products Industry,” Strategic Management Journal, vol. 26, no. 2, 2005.
- Tobias Hahn et al., “Cognitive Frames in Corporate Sustainability: Managerial Sensemaking with Paradoxical and Business Case Frames,” Academy of Management Review, vol. 39, no. 4, 2014.


