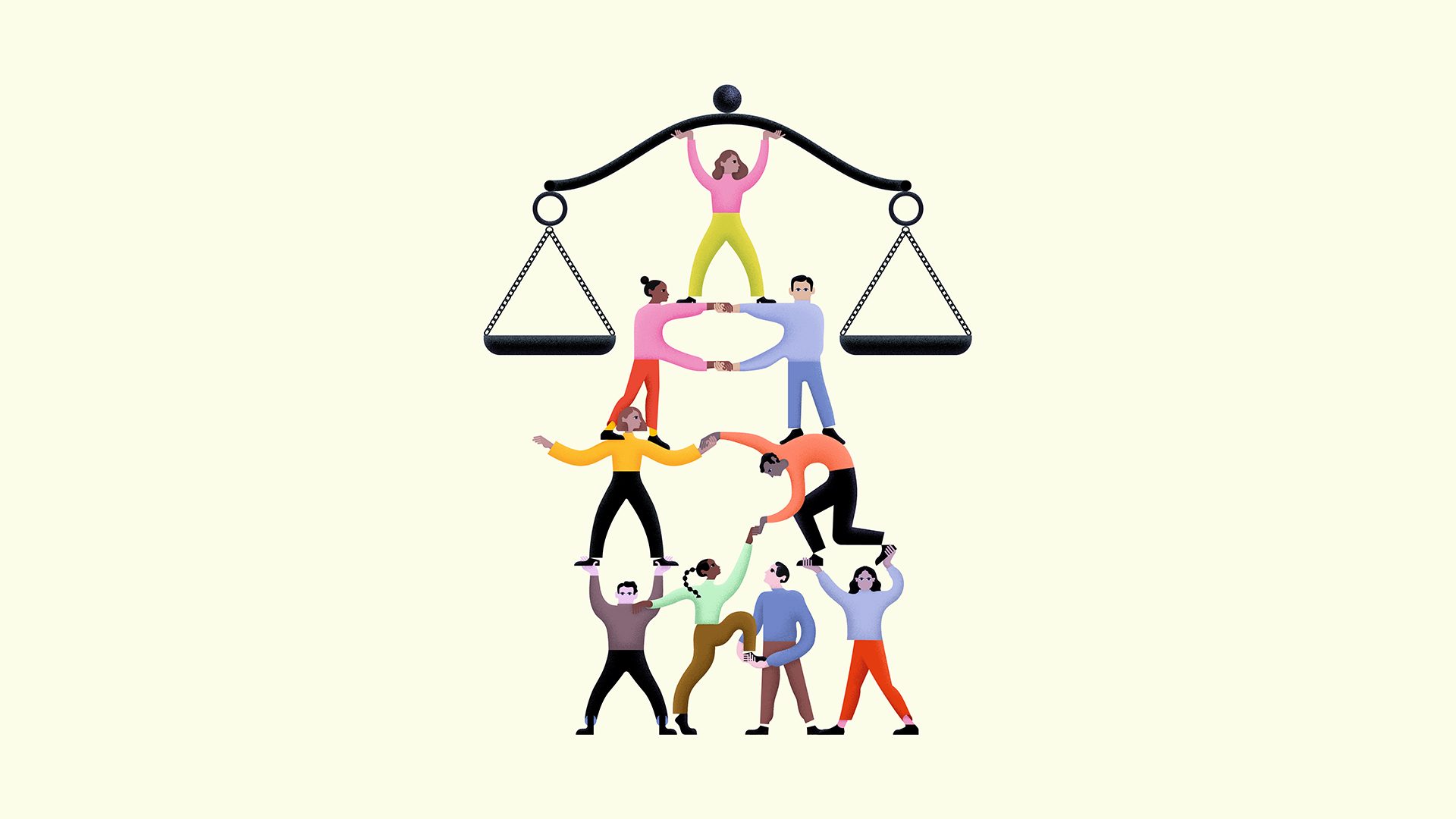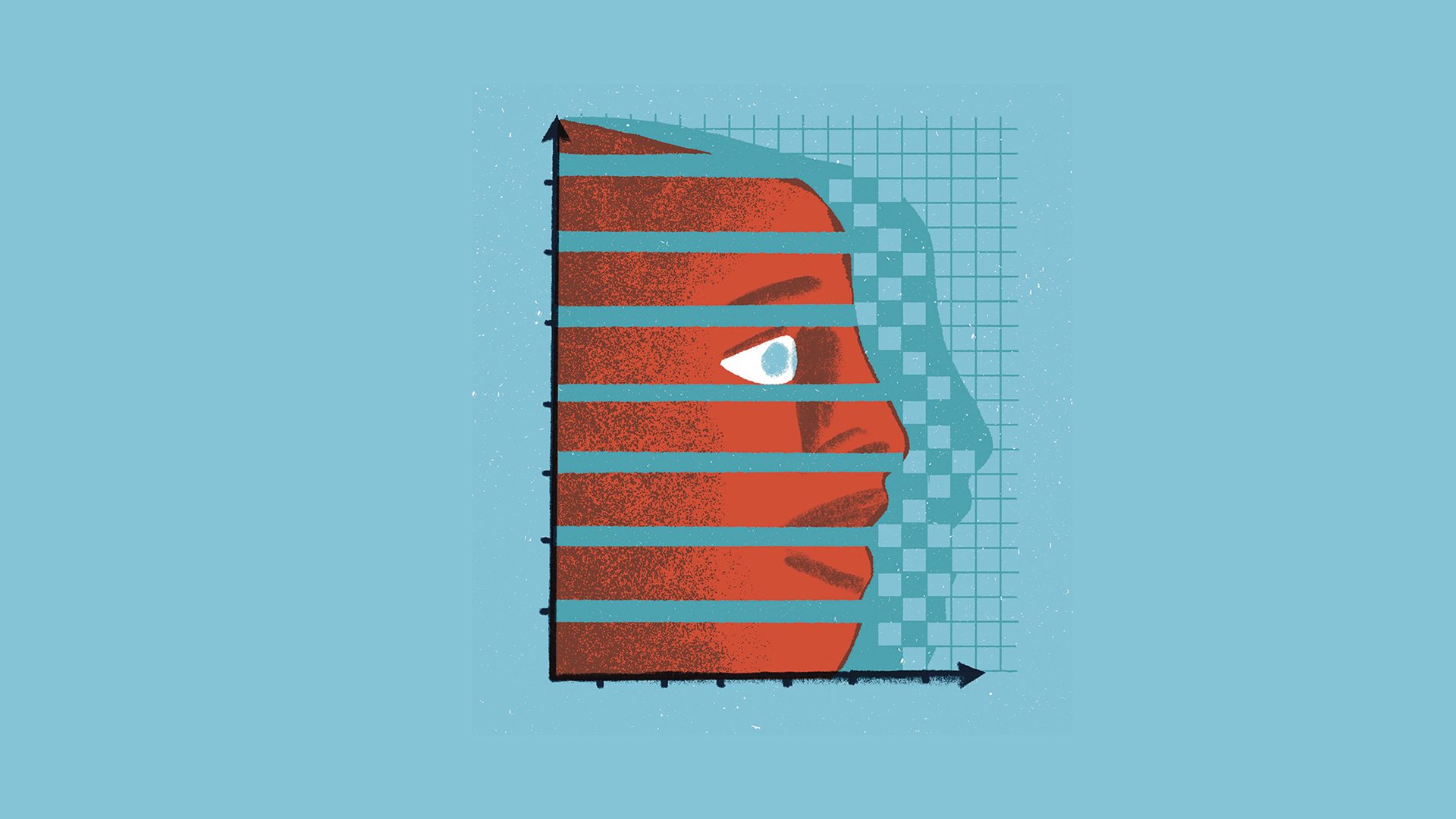正義を重んじる資金提供者は、コミュニティが自らの研究プロジェクトを主導できるよう支援すべきである。 メーガン・コラド (Megan Collado)リシカ・デサイ (Rishika Desai)ジャメイ・モリス (Jam […]
タグ: コミュニティ
日本で最も自殺の少ない町から学ぶ都市のデザイン:「路地」と「ベンチ」が援助希求行動を促す
徳島県南端にある太平洋に面した海部町(現海陽町)は日本で自殺率が最も低いことで知られている。この町を対象とした研究から自殺の危険を抑制するコミュニティの特性が見えてきた。それらの社会実装に向けた試みを紹介する。
Editor’s Note:コミュニティの可能性を諦めない
今号はコミュニティ特集です。社会課題の現場としてのコミュニティと、その課題解決のリソースとしてのコミュニティという2つの側面に光を当てました。
「奪い合う関係」を「与え合う関係」に変える仕組みとは
「応援する文化」をつくる新しいお金
なぜ「地域の声を聞く」だけではインパクトが生まれないのか
多くの取り組みが、現地コミュニティの「声」を大切に聞いている。しかし、コミュニティの「主導権」を強化し、リーダーシップを引き出している取り組みはどれだけあるだろうか?
より公正な社会を目指すためにはまず、パートナーシップ間の不均衡な力関係に目を向ける必要がある。
「現場のプログラムか、全体のシステムか」の二元論を越えるコレクティブ・インパクトのあり方
地域コミュニティをコレクティブ・インパクトの取り組みに巻き込むために、何が必要か。4人の実践者たちが、10年以上の経験から得られた学びを共有し、課題と展望について語り合う。
コレクティブ・インパクト、次の10年の課題と可能性
コレクティブ・インパクトの数々の取り組みは、これまで、システムレベルの変化に貢献し、コミュニティの多くの人々の生活を改善してきた。次の10年は、エクイティ、不均衡な力関係の是正、サステナビリティ、複数の取り組み間の協力体制の強化といった点に注力し、より持続性の高い社会変化を実現することが求められる。
コレクティブ・インパクトの実装に向けて
2011年に発表され、社会課題への新しいアプローチとして注目を集めた論文「コレクティブ・インパクト」。その後も世界各地で実践が広がり、追加の研究も実施されている。そこから見えてきた成功要因とは。
コレクティブ・インパクトの北極星はエクイティの実現である
この10年間にわたる社会課題解決に向けたコレクティブ・インパクトの実践からわかったことがある。それは、構造的不平等の解消を中心に据えなければならない、ということだ。
データ利用の植民地主義を脱却せよ
データ・コロニアリズム(データの植民地主義)が根強く残っているがそれを変えなければ真のエンパワーメントは実現できない。